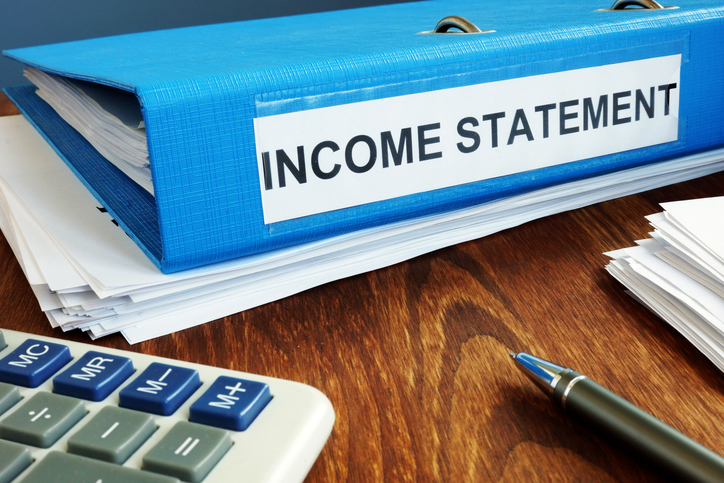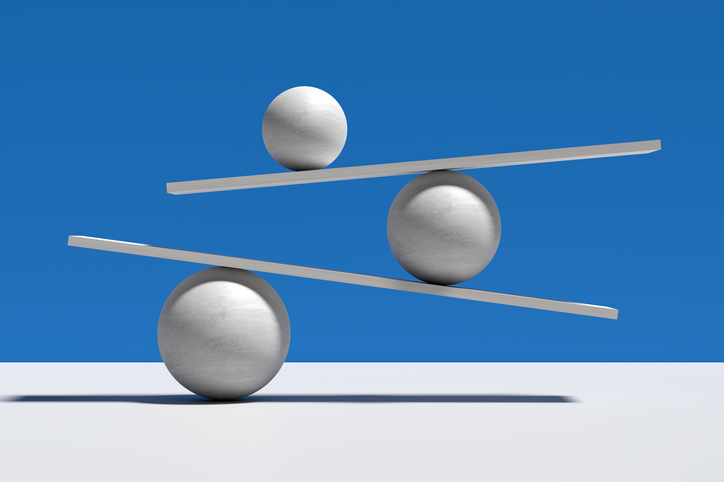損益計算書の書き方は?作り方と手順、注意点【テンプレート付き】

ビジネス現場で重要な役割を果たす損益計算書。作成するには一定の会計知識が求められます。じつは損益計算書は、基本項目をきちんと押さえれば難解すぎることはありません。
この記事では、損益計算書の作成手順や注意点についてわかりやすく解説します。さらに初心者にも使いやすいテンプレートを紹介。基礎から学びたい経理従事者の方も必見です。経理業務において重要な損益計算書の基礎知識を身につけましょう。
損益計算書の詳細については以下の記事もご参照ください。
経理プラス:損益計算書(P/L)とは?分析・作成時のポイントや貸借対照表との違い
損益計算書(P/L)の基礎知識
会社の経営状況を数値ではっきりと示す決算報告書は、情報の宝庫です。決算報告書を見ることで、企業のよいところ、改善すべきところが見えてきます。損益計算書は、決算報告書の1つであり、企業1年間にどれだけの利益または損失を出したのかを示す報告書です。ここでは損益計算書の基礎知識を解説します。
損益計算書とは?
損益計算書は、英語表記で「Profit and Loss Statement」と呼ばれ、その頭文字を取って「P/L」と呼ばれることがあります。Profit(利益)とLoss(損失)という英語表記からも、企業の儲けを生み出す力に着目した報告書であることがわかります。
損益計算書は、収益、費用、利益の3つのカテゴリーで構成されます。
「収益」とは主に売上のことで、企業が提供した価値の対価として得た金銭です。「費用」は、収益を生み出すために費やされた金銭です。たとえば、商品仕入代や従業員への給料、光熱費等です。そして、収益から費用を差し引いたものが「利益」です。(マイナスの場合は「損失」)収益の金額がそのまま利益となるわけではないので注意しましょう。
なお、決算報告書には損益計算書の他にも「貸借対照表」「キャッシュフロー計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」があります。各決算報告書の詳細は以下の各記事をご参照ください。
経理プラス:決算報告書の書き方や種類、読み方をわかりやすく解説!【テンプレートあり】
:貸借対照表とは?見るべき2つのポイントと財務三表の関係を解説
:株主資本等変動計算書で仕訳ミス発見!?基本を押さえて賢く活用
:個別注記表は必須の資料!中小企業が気を付けるべき項目を解説
損益計算書からわかる利益の種類
損益計算書では利益を、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益の5つに分けます。それぞれの利益の概要をまとめました。
| 利益の種類 | 概要 |
|---|---|
| 売上総利益 | 売上高から売上原価を差し引いたもので、粗利(粗利益)とも呼ばれる |
| 営業利益 | 売上総利益から営業経費(販売費および一般管理費)を差し引いたもの |
| 経常利益 | 営業利益から財テク収入といった本業以外で発生した営業外収益・営業外費用を差し引いたもの 特殊事情を加味せず企業の平常時での状況を示す利益で、経営状況を判断するうえで最も重視される利益の指標 |
| 税引前当期純利益 | 経常利益から通常では発生しない臨時的な損益(特別利益・特別損失)を差し引いたもの |
| 当期純利益 | 税引前当期利益から法人税等の税金を控除したもの 当期の最終的な業績 |
上記5つの利益はどれも経営分析を行ううえで重要な指標です。損益計算書の各段階の利益水準を分析することで経営判断が可能となります。たとえば、経常利益がプラスでも、最終的な当期純利益がマイナスの場合、臨時的な特別損失が発生したことによるものであれば、本業の経営状況が悪化したとはいえません。
経営状況を正しく判断するために、各段階の利益の持つ意味をしっかりと押さえましょう。
損益計算書の書き方【テンプレート付き】
ここでは、損益計算書の作り方と書き方を解説します。損益計算書を簡単に作成できる便利なテンプレートも紹介します。
テンプレートを使う
損益計算書作成の最も手頃な方法はテンプレートを使うことです。インターネット上には、損益計算書作成に役立つテンプレートが無料で配布されています。テンプレートの既定の項目の必要な数字を入力するだけで簡単に自動計算がされます。
会計ソフトを使う
会計ソフトの使用は広く一般的に活用されている作成方法です。会計ソフトに取引の仕訳を登録すれば、あとは自動で帳簿へ転記→試算表作成→決算書作成へと進みます。
最近の会計ソフトは銀行APIや経費システムなどの別システムとの連携が簡単に行え、AI搭載により一度発生した仕訳を学習。次の発生からは自動仕訳を行ってくれるものもあります。
税理士に依頼する
テンプレートや会計ソフトを使う場合は簿記の仕訳知識が必要ですが、税理士にアウトソースする場合、仕訳の知識は不要です。税理士に領収書等の取引証憑を提出することで、税理士側で会計ソフトへの仕訳登録を行います。決算報告書の作成までを一任できますが、毎月一定の顧問料がかかるため、他の方法に比べ高額になります。
作成に当たっては企業規模や費用対効果を勘案し、最適な方法を選択しましょう。
損益計算書の書き方の手順
損益計算書の書き方の手順を5stepで解説します。
Step1.日常仕訳の実施
最初のステップは取引の仕訳です。取引が発生するたびに、日付、取引内容、金額などの情報を適切な勘定科目を使って仕訳帳に記入します。
Step2.仕訳帳から総勘定元帳への転記
仕訳帳のデータを勘定科目ごとに総勘定元帳に転記します。総勘定元帳は勘定科目ごとの取引の記録と取引残高が集計されたものです。決算期には各勘定科目の期末残高が確定します。
Step3.試算表の作成
総勘定元帳の勘定科目ごとの借方・貸方の合計金額と残高を試算表に転記します。試算表を作成することで、決算をまたず収益と費用のおおまかな把握が可能です。また、試算表は借方・貸方の数値が必ず一致するため、数値が合わない場合、記帳ミスの発見につながります。
Step4.決算整理仕訳の実施
年度末の決算時には、決算整理仕訳を行います。会計年度の終了に伴い、翌期にまたぐ収益の未収分や未払費用の調整、減価償却費の計算などの決算整理仕訳を行います。決算整理仕訳を行うことで、正確な損益計算書を作成するための準備が整います。
Step5.損益計算書の作成
最後のステップでは実際の損益計算書を作成します。損益計算書の作成には試算表の情報を活用します。試算表から収益や費用の項目を取得し、損益計算書に記入すれば完成です。
損益計算書のテンプレート
損益計算書のテンプレートは、経理プラスの以下のURLからダウンロードできます。Excelで作成されているため使い勝手がよく、損益計算書の見本、テンプレート、サンプルとしてご利用いただけます。
経理プラス:【ビジネス書式テンプレート】損益計算書
損益計算書を作成するときの注意点
損益計算書を作成する際にはいくつかの注意点があります。ここでは、複式簿記による作成と勘定科目による表記変更の2つを解説します。
複式簿記で作成する
取引の記録方法には「単式簿記」と「複式簿記」があります。単式簿記は取引を現金の出入り一点にフォーカスし、記録する方法です。お小遣い帳をイメージするとわかりやすいでしょう。これに対し、複式簿記はひとつの取引を2つの視点から眺め、借方と貸方の2つの勘定科目を使って仕訳する方法で、正規の簿記の原則に従ったやり方です。
損益計算書を作成する際には、複式簿記による仕訳を行います。取引ごとに「費用」「収益」にカテゴライズされた適切な勘定科目を貸方と借方にあてはめ仕訳することで、収益と費用の差額である利益を算出できます。
勘定科目によって表記を変える
損益計算書では、試算表から必要な項目を抜き出す際に、たとえば、「売上」を「売上高」、「仕入」を「売上原価」というように勘定科目の表記を変更します。
まとめ
この記事では、損益計算書の基礎知識から、具体的な作成手順や注意点を解説しました。ここまでの開設内容を以下にまとめていきます。
- 損益計算書を構成するカテゴリーは「収益」「費用」「利益」の3つ
- 損益計算書の利益は「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「税引前当期純利益」「当期純利益」の5種類
- 作成方法は、テンプレートの活用や会計ソフト、税理士へのアウトソースなどがある
- 複式簿記の原則に従って作成する
- 勘定科目は適切な表記ルールに従う
損益計算書は企業の経営状況や収益性を把握する上で欠かせない情報源であり、経理部門は正確な作成を求められます。損益計算書の正確な理解と作成を通じて、経理業務の効率化や意思決定のサポートに役立てていきましょう。
損益計算書に関するQ&A
損益計算書は企業の収益と費用を明示し、経営状況の把握や将来計画の策定に役立つ重要な財務書類です。
ここでは、損益計算書に関する一般的な疑問に回答します。
Q1. 損益計算書と貸借対照表(B/S)との違いは?
損益計算書と貸借対照表では、「報告する内容」と「報告の対象となる期間」が異なります。
損益計算書は一定期間(決算期間)の利益の獲得状況を示しています。一方、貸借対照表はある一時点(決算日)の財務状況を表しています。会社が1年間にいくらの利益を生み出したかを確認するには損益計算書を、利益の増減によって会社の財務状況がどうあるかは貸借対照表で確認できます。
Q2. 損益計算書の報告式と勘定式とは何ですか?
報告式と勘定式は表示形式のことです。
報告式の損益計算書は、利益を段階的に計算し縦書きで表示します。一方、勘定式は縦書きによる表示ではなく、貸方に収益、借方に費用を計上し、左右に並べて表示します。
Q3. 損益計算書を作る目的は何ですか?
損益計算書を作成する目的は、会社の経営状況を把握して将来の経営計画の指針とすること、金融機関や株主など利害関係者からの信頼を得ることなどが挙げられます。特に金融機関から融資を受ける際は、過去数年分の損益計算書の提示を求められるケースがあります。
Q4. 損益計算書の提出先はどこですか?
損益計算書は、主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出します。主たる事務所の所在地は、法人であれば登記事項証明書に記載されている本店所在地で、個人事業主であれば住民票のある住所が該当します。
Q5. 楽に損益計算書の作成ができる方法はありますか?
損益計算書の基となる勘定科目のうち、日々発生する経費科目は大きなウエイトを占めいています。つまり経費取引の発生と同時に仕訳データの作成を自動化できれば、損益計算書の作成にかかる時間は大幅に削減できます。
「楽楽精算」は、システムに経費精算登録を行うだけで簡単に仕訳データが作成できます。作成された仕訳データを会計ソフトにインポートするだけで登録が完了。日々の経費精算の一元管理はもちろん、仕訳データから銀行振込データの作成を一気通貫、経理業務を効率化します。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。