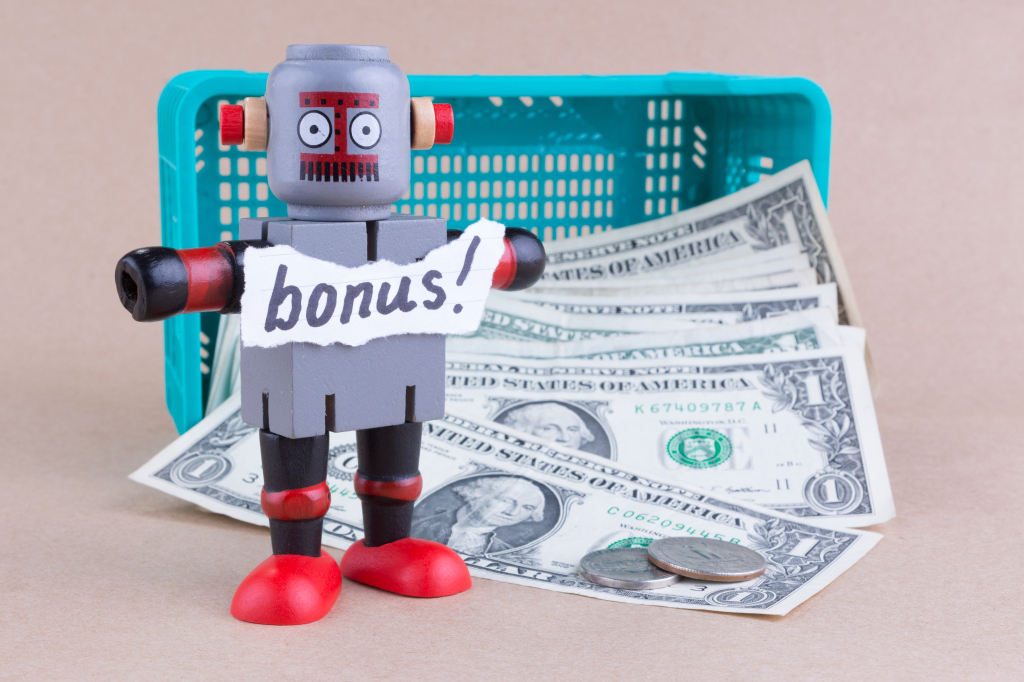売上原価とは?計算方法や製造原価との違いをやさしく解説

売上原価とは、売上を得るために直接的にかかった費用のことです。商品の仕入や製造にかかる材料費などが該当します。本記事では、売上原価の概要と計算方法、業態別の考え方を分かりやすく解説します。
期末に売上原価を計上する手順も紹介するため、決算に備えて実務をイメージしておきましょう。
売上原価とは
売上原価とは、売上を生み出すために直接かかった費用のことをいいます。たとえば、製造業における材料費や製造者の労務費、小売業であれば販売商品の仕入高などが該当します。「商品やサービスを作って売る」という、事業活動の基本的な部分にかかる費用が売上原価です。
売上原価を把握することで、「粗利(あらり)」を計算できます。売上高から売上原価をマイナスすると、粗利が分かります。粗利は売上総利益とも呼ばれ、損益計算書上で最初に計算される重要な利益です。
事業活動において重要な商品やサービスにかかる費用である売上原価は、費用のうち多くを占めます。売上原価を適切に管理し、仕入や製造における無駄を減らすことで、利益率の改善や財務の健全化が期待できます。
売上原価と製造原価の違い
売上原価は、売れたものの仕入や製造にかかった原価です。一方で、製造原価とは製造業で計上する費用であり、製品の製造にかかった原価にあたります。
売上原価と製造原価の違いは、原価を計算する対象です。製造業では、製造しても売れずに在庫が残ることも少なくありません。この在庫の原価は、売上原価には計上しませんが、製造原価には計上します。
売上原価の基本的な計算方法
会社の業態によって、売上原価に何を含めるかは異なります。基本的には、売上原価は以下の式で計算します。
上記の計算方法は、売上原価の計上の仕方として広く一般的に使われている「三分法」によるものです。期末に1年分をまとめて計算するため効率的な方法である一方、リアルタイムで売上原価がいくらなのかをつかみにくいというデメリットがあります。
なお、商品が売れるごとに売上原価を計上する「売上原価対立法」という方法も存在します。売上原価ではなく「商品販売益」を計上する「分記法」「総記法」という方法もありますが、あまり多くは使われていません。
業態ごとの売上原価の考え方
「商品を仕入れて販売のみ行う」「製造のみ行う」「製造も販売も行う」など、会社によって業態は異なります。以下では、上記の3業態について、それぞれの売上原価の考え方を解説します。
卸売業・小売業の場合
卸売業・小売業の場合は、売上原価は主に仕入高であり、期末に棚卸をして前述の方法で計算します。当期に売れた商品の仕入高のみを当期の売上原価とし、残った商品の仕入高は来期に回します。
製造業の場合
製造業の場合は、売上原価には売れた製品の材料仕入のほか、人件費や水道光熱費のうち製造に直接かかわったものも含めて計算します。受注生産で在庫を持たないという業態であれば、売上原価と製造原価は同じ数字です。
製造業では売上原価のほかに製造原価も計算し、製造にいくらかかったかを管理します。上場企業には期末に「製造原価報告書」の作成が義務付けられているものの、非上場企業であれば作成の義務はありません。
製造・販売ともに行う場合
工場と店舗を持ち、自社で製造も販売もしている会社であれば、期末に材料や製品の棚卸をして売上原価を計算します。この場合は、売上原価と製造原価は異なる数字となります。
なお、店舗の運営にかかる人件費・水道光熱費などは「一般管理費」として、売上原価とは別に計上することが一般的です。
売上原価を計上する手順
売上原価を計上するのは、決算のタイミングであることが一般的です。期末にどれだけ商品が残っているかを確認しなければ、当期にどれだけ商品が売れたのかを把握できないためです。以下では、期末に売上原価を計上する具体的な手順を解説します。
仕入・材料の実地棚卸
期末になったら、仕入れた商品や材料の実地棚卸を行います。仕入れた商品や材料が実際にどれだけ残っているか、実際の在庫を数えて確認する作業です。
商品や材料は帳簿でも管理する場合もあります。しかし、実際の在庫が帳簿上の在庫と合致しないことも少なくありません。実地棚卸は、売上原価を正確に計算するための大切な工程です。
決算整理仕訳
実地棚卸によって期末商品棚卸高を把握したら、帳簿上でその分の仕入額を当期の仕入額から外す「決算整理仕訳」を行います。すでに計上している仕入額の勘定科目を「仕入」から「繰越商品」に振り替え、来期の期首に逆仕訳(再振替仕訳と呼びます)することで、来期分の仕入とします。
この作業により、「仕入は当期に行ったが売れていない」という商品の売上原価は、当期分に計上されません。
なお、決算整理仕訳には上記の仕訳のほか、当期に前払いした費用を来期分に繰り延べたり、減価償却費を計上したりするなどさまざまな処理があります。
損益計算書への記載
売上原価を計算したら、損益計算書に反映させます。売上原価は損益計算書の「売上高」のすぐ下に記載されることが一般的です。
売上原価を効率的に管理する方法
売上原価の正確な把握や管理は大切であるものの、手間がかかります。特に製造業の場合は、売上原価を計算するために製造原価の管理が大切です。また、製造業以外でも、日々の受注や販売状況を管理することが正確な売上原価の算出につながります。
売上原価を効率的に管理するには、ツールの活用が有効です。工場の製造原価を管理できる機能や、営業活動における見積もりや受注状況を管理できる機能など、さまざまな機能を搭載したツールがあります。自社に合ったものをうまく採り入れることで、管理の効率化を目指せるでしょう。
まとめ
売上原価とは、売上を生み出すために行った仕入や製造に直接的にかかった費用のことです。売上原価を管理することで、会社の利益の基本となる粗利(売上総利益)を計算したり、自社の営業成績や財務状態を正確に把握したりできます。
売上原価は、期末に棚卸高を確定させて計算する方式が一般的です。そのため、日々の仕入や受注の正確な管理が、売上原価の正確な把握につながります。事業活動に役立つツールも多くあるため、自社に合ったものを有効活用しましょう。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。