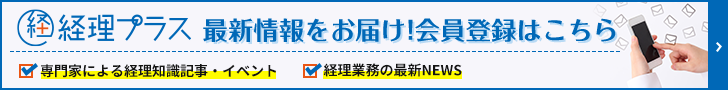どんな業種でも共通して使える「財務指標」とは

会社の経営状況を分析する指標は、いくつかあります。自己資本比率やROA、売上高経常利益率や労働分配率など、会社の安全性や収益性を、様々な比率で確認します。一般的に使われているこれらの財務指標の中には、実は他社と比較しても、まったく意味がないものがあるということは意外と知られていません。
業種によって比率は違う
たとえば、ホテルや旅館業など、建物や土地、大きな設備が必要な業種があります。自己資本比率は、「純資産÷総資産」ですが、このような業種は、借入により購入した長期的な資産で、長期的に稼いでいく業態ですから、当然、総資産は大きくなり、自己資本比率は低くなります。
逆に士業やコンサル業など、そもそも設備は不要で、仕入も在庫もない業種であれば、総資産は小さく、借入も必要ないので、利益が出れば自己資本比率は高くなります。
また、粗利益率は、美容業が90%、飲食業は70%、製造業は50%、卸売業は20%など、おおむね業界の特性により平均値があります。大きな仕入が必要な卸売業の会社が、ほぼ仕入がない美容業の会社の粗利益率を見て、「うちは、あの会社より粗利益率が格段に低いので、悪い経営だ」と比べても、まったく意味がないわけです。
これは業種による収益構造の違いであって、会社の経営状態が良い・悪いではないのです。
労働分配率の比較は意味がない
昨今の働き方改革で、生産性の重要性が叫ばれていますが、生産性を見る指標として一般的な、「労働分配率」も勘違いが多い指標です。
労働分配率の指標は、「人件費÷付加価値額(粗利益額)」で計算されます。労働分配率は会社が生み出した付加価値(粗利益額)に対する、人件費の割合です。この労働分配率を見ることで、会社がかけている人件費の割合はどうか、かけた人件費に対して、粗利益額がしっかりと稼げているかなどが分析できます。まさに、「人が稼いだ生産性」を把握できるわけです。
しかし、会社の生産性を上げるのは、人の力だけではありません。製造業であれば、工場や機械など、多額の設備投資をして、生産性を上げるのが一般的です。極端な話、すべてが機械化され、人が1人も必要ない工場を作れば、労働分配率は極限まで低くなります。人件費ではなく、多額の設備投資にお金が使われているという状態です。このような業種と、士業やコンサル業など、設備投資は不要で、雇った人の知識だけで稼ぐ業種の労働分配率とを比べても、生産性の比較としてはまったく意味がないということが分かるかと思います。
ですから、業種を問わない全国平均の労働分配率と、自社の労働分配率を比べて一喜一憂する必要はないのです。労働分配率を比べて意味があるのは、「過去の自社の労働分配率」だけです。自社が最も高い利益を上げていた時の労働分配率が、自社にとって最も適切で、効率的な社員数、人員配置であった可能性が高いのです。ですから、この時の労働分配率を目安にして、今後の目標設定にその数値を使うのが、正しい労働分配率の使い方ではないでしょうか。
売上高経常利益率の比較も意味がない
よく使われる財務指標である「売上高経常利益率」も、間違った見方が多い指標の1つです。売上高経常利益率は、売上高に占める、経常利益の割合です。売上のうち、どれだけ効率的に利益が残っているかという「収益性」を見る指標になります。京セラの創業者である稲盛和夫さんも、「10%くらいの利益率が出せないようでは、経営のうちに入らない」とおっしゃっています。苦労をして経営をし、10%の利益率も出せないのであれば、銀行にお金を預けて利息をもらった方が、お金の使い方としては、まだましだということです。
しかし、すべての業種でこの10%の売上高経常利益率は当てはまるものなのでしょうか。売上高経常利益率は、売上に占める経常利益の割合ですが、売上高から売上原価を引いて、粗利益額が出て、そこから固定費を引いて、経常利益が出ます。この最後の経常利益の段階で売上高の10%を出すためには、人件費や家賃などの固定費を払う前の粗利益額が、当然、経常利益の額よりも大きくないといけません。要するに、売上高に占める粗利益額を表す「粗利益率」が10%以上なければ、経常利益率の段階で10%が出るということはありえないということになります。
たとえば、野菜の卸売りや、文具の通販など、大手企業であっても、粗利益率が10%もない業種は実際に存在します。製造業であれば、社員数30名で、売上高10億円、売上原価5億円、粗利益額5億円(粗利益率50%)、固定費4億円、経常利益1億円の会社は、売上高経常利益率10%の会社です。一方、同じ社員数30名で、1つ1つの商品の粗利は安いが、取引額が大きい卸売業では、売上高100億円、売上原価95億円、粗利益額5億円(粗利益率5%)、固定費4億円、経常利益1億円の会社も存在します。社員数1人当たりで稼いでいる経常利益はまったく同じであっても、こちらの会社は売上高経常利益率で見るとたった1%になってしまいます。それでは、同じ社員数で、同じ経常利益を稼いでいるこの卸売業は、製造業と比べて、悪い会社なのでしょうか。まったく同じ商品を扱う同業他社と、売上高経常利益率を比較することは1つの目安になります。しかし、他の業種と、売上高経常利益率を比べても、実はほとんど意味がないのです。
業種・業界を問わず使える財務指標とは
それでは、あらゆる業種に適用できる財務指標とは何でしょうか。
それは、「損益分岐点比率」です。損益分岐点比率は、粗利益額と固定費との関係です。式にすれば、「固定費÷粗利益額」となります。実は、この指標は、業種にかかわらず、経営の安定度を、同じ比率で取り扱うことができます。前述の製造業と卸売業のように、業種の違う会社で、売上高経常利益率が10%と1%の差があったとします。
しかし、売上高経常利益率が10倍違っても、固定費と粗利益額が同じであれば、経営の安定度は同レベルと言えます。そして、両社とも、固定費4億円÷粗利益額5億円で、損益分岐点比率は80%ということになります。業種ごとの特性である粗利益率は、考えなくても良いということです。
この損益分岐点比率が、81%~90%であれば、どのような業種であっても、健全企業だといえます。100%になると、固定費と粗利益額が一緒だということですので、収支トントンということを表しています。そして、200%以上の数値であれば、倒産寸前です。稼いでいる粗利益額より、固定費が2倍以上になっている状態です。
逆に、この損益分岐点比率が低ければ低いほど良いかというと、そうではありません。中小企業では80%が理想の数値ですが、80%よりかなり低くなっている会社は、社員の給与が少なすぎたり、未来のための教育費、広告宣伝費、研究開発費などの「未来費用」を使っていないなど、将来のための固定費を、削りすぎているとも言えるからです。
まとめ
違う業種や、全業種平均の「労働分配率」や「売上高経常利益率」との比較で、自社の経営状態を判定することはできません。自社の事業構造をしっかりと把握して、まずは、損益分岐点比率90%を目標とします。それが達成できたら、理想の損益分岐点比率80%を目指していきましょう。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。