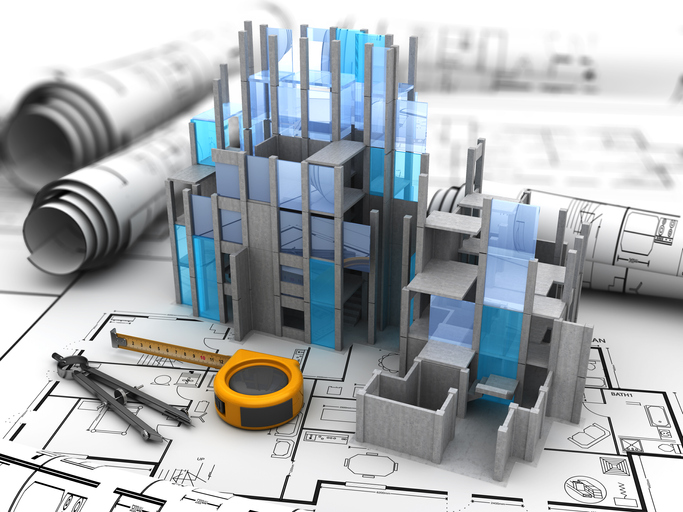流動資産とは?貸借対照表での書き方や棚卸資産の効率的な管理方法を解説

貸借対照表は、決算時点における企業の財政状況を表す重要な決算書類の1つです。損益計算書、キャッシュフロー計算書と合わせて財務三表と呼ばれ、企業の経営状況を把握するために欠かせません。貸借対照表の左側には会社が保有する「資産」を記入しますが、資産はさらに「流動資産」「固定資産」「繰延資産」の3つで構成されます。
流動資産には、現金預金や売上債権、棚卸資産などが含まれ、企業の資金繰りやキャッシュフローに大きな影響を与えます。適切な評価方法を選択し、勘定科目ごとに分類・管理することで、資産の流動性を高め、財務の安定性を確保することができます。
本記事では、流動資産の勘定科目や他の資産との違い、決算時の評価方法といった基礎知識を解説するとともに、資金繰りや貸倒リスクを踏まえた分析方法についても詳しく説明します。経理担当者や財務管理を担う方はぜひ参考にしてみてください。
流動資産の概要
まずは流動資産の概要について説明します。
流動資産とは
流動資産とは、短期間のうちにお金(キャッシュ)に変えられる資産のことです。「材料仕入→製造→在庫→販売→回収」という本業である営業サイクルの中で発生する資産や1年以内の短期に現金化できる資産が該当し、「短期」とは1年以内のことを指し、基準は決算日を起点に考えます。
なお、現金化するまでに長期(1年)を超えるような資産は「固定資産」と呼びます。固定資産についても後ほど解説します。
流動資産の種類
では、どういったものが流動資産に分類されるのか、確認していきましょう。
当座資産
当座資産は流動資産のなかでも、すぐに現金化できる資産を指します。具体的には、現金、預金、受取手形、売掛金、有価証券などが挙げられます。
| 勘定科目 | 内容 |
|---|---|
| 現金 | 手元に保有するキャッシュ、他社から受け取った小切手 |
| 預金 | 普通預金、1年以内に満期となる預金 |
| 受取手形 | 取引先から受け入れた手形 |
| 売掛金 | 商品を掛け売りした場合の未収代金 |
| 有価証券 | 株式、社債、国債、地方債で短期的に保有するもの ※売買を目的としないものや満期が1年超のものは「投資有価証券」に分類される |
棚卸資産
棚卸資産は、販売することで現金化できる資産を指します。具体的には、商品(製品)、仕掛品、原材料、未成工事支出金などが挙げられます。
| 勘定科目 | 内容 |
|---|---|
| 商品(製品) | 販売目的で仕入れた物品、製造した物品 |
| 仕掛品 | 製造途中の過程にある未完成品、半製品 |
| 原材料 | 製造のために仕入れた物品のうち、まだ消費されていないもの |
| 未成工事支出金 | 未完成の工事にかかった費用や支出(未完成のため売上ではなく資産として計上) |
その他の流動資産
当座資産と棚卸資産のどちらにも分類されない資産は、その他の流動資産に分類されます。具体的には、短期貸付金、貸倒引当金、前払費用、仮払金、立替金、未収入金などが挙げられます。
| 勘定科目 | 内容 |
|---|---|
| 短期貸付金 | 返済期日が1年以内の貸付金 |
| 貸倒引当金 | 売上債権(受取手形、売掛金)の回収不能に備える引当金 |
| 前払費用 | 企業が将来のサービスを受けるために、事前に支払った費用(家賃や保険料の前払いなど) |
| 仮払金 | 具体的な用途が確定していない支出や、一時的に立て替えたお金。決算時までに正式な勘定科目へ振り替える必要がある |
| 立替金 | 企業が本来支払うべきでない費用を、一時的に第三者(取引先や従業員など)に代わって立て替えて払ったお金 |
| 未収入金 | 企業が本業以外の取引で発生した代金で、かつまだ受け取っていない状態のお金(固定資産の売却代金の未回収分など) |
貸借対照表上での記載方法
これまで説明した「当座資産」「棚卸資産」「その他の流動資産」は、貸借対照表の「資産」、「流動資産」に記載します。原則的にキャッシュになりやすい順に記載します。具体的には、現金が一番上に記載され、普通預金、売掛金、有価証券、棚卸資産と続きます。
受取手形や売掛金といった売上債権は、取引先の倒産などで回収不能になる可能性はゼロではありません。しかし、契約によって権利が担保されているので現金に近い資産と言えます。一方、商品や製品などの棚卸資産はいくらで売れるか約束されているわけではなく、また、いつ現金化するかも決まっていません。
上記により、売上債権は棚卸資産より流動性が高いと考えられ、貸借対照表の表示は上に記載されます。
流動資産、固定資産、繰延資産の違い
貸借対照表の資産の部は「流動資産」「固定資産」「繰延資産」に区分されます。流動資産は、これまで記載してきた通り1年以内に現金化する資産のことです。現金そのものの他、売上債権や棚卸資産を含みます。
ここからは固定資産と繰延資産について説明します。
固定資産
固定資産は1年を超えて現金化する資産のことで、言い換えると長期的に所有する目的の資産です。固定資産はさらに下記3つに区分されます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 有形固定資産 | 土地、建物、機械装置など形のある資産 |
| 無形固定資産 | 特許権、著作権、のれん、ソフトウェアなど |
| 投資その他の資産 | 長期性預金、長期貸付金、投資有価証券など |
満期が1年を超える社債などの有価証券も、固定資産に含まれます。1年を基準として流動、固定に区分することを「ワン・イヤー・ルール」と呼ばれています。ワン・イヤー・ルールについては下記記事も参考にご覧ください。
経理プラス:正常営業循環基準とは?一年基準との違いなど具体例を解説!
上場株式や土地といった市場価格が形成されている固定資産は比較的現金化しやすいですが、専用の機械や工場などの建物は資産価値どおりに売れる可能性は低いと言えます。固定資産の中には、現金化しにくい長期的に保有する目的の資産が含まれることを理解しましょう。
繰延資産
繰延資産は既に支払が完了して役務の提供を受けているのに、その支出の効果が将来にも及ぶ費用であり、資産として計上し複数年に渡って費用化することで、具体的には創立費、開業費、株式交付費、社債発行費などです。たとえば会社の設立にかかる費用である創立費は、その会社が存続する限り効果が継続する費用と言えます。そのため、資産に計上し、決められた償却期間で費用計上するのです。元々は費用的な性質を持ちますので、現金化はできない資産と理解しましょう。
経理プラス:【税理士監修】繰延資産は「資産」ではない!?償却方法や仕訳方法を解説
流動資産の分析方法
会社は、現金がショートした場合に倒産します。そのため、短期の債務に対してどれくらいの支払い能力を持っているかが重要です。短期の返済能力は、流動資産と流動負債の比較により分析できます。ここで流動資産を使った分析方法について解説します。
流動資産>流動負債
貸借対照表の「負債の部」には、流動負債が記載されています。流動負債は、1年以内に会社から現金が出ていく負債のことで、買掛金、支払手形、短期借入金などが該当します。
流動資産が流動負債より大きければ(流動資産>流動負債)、短期的な資金繰りは余裕があると言えます。反対に流動資産が流動負債より小さい場合(流動資産<流動負債)、足りない現金を長期借入金などで調達する必要があり余裕がありません。
流動比率と固定比率について
では、どれくらい流動資産が流動負債より多ければ良いのでしょうか。資金の流動性を分析する代表的な指標に「流動比率」があります。金融機関が短期融資をする際に重要視する指標です。
流動比率は、短期的な債務の支払能力を判断する指標です。
流動比率が高いほど、資金の流動性に余裕があり安全と言えるでしょう。現金化するタイミング差を考慮し、理想的には200%、一般的には150%を超えていれば良いと言われます。
流動比率と固定比率
一方で、長期的な資金調達の適正性を判断する指標としては「固定比率」があります。固定資産がもっとも安定している自己資本で、どれくらいカバーされているかを見る指標です。
固定資産への投資は、返済義務のない自己資本で賄われることが望ましいと考えられています。そのため、固定比率は低い方が良く、100%未満であれば自己資本の範囲内で固定資産へ投資していることになり問題ないと言えます。
なぜなら、工場の建屋や機械装置といった固定資産は、製品を製造、販売し長期に渡って投下資本を回収するために購入されるものであり、棚卸資産のように資産自体を売却によって資金を回収するわけではないことが理由です。
流動比率を改善するために棚卸資産が果たす役割
流動比率を高めるには、流動資産を増やすことが重要です。ここで重要なのは短期的な支払能力を高めることであるため、流動資産の中でも、すぐに現金化できる資産を増やすことが特に重要です。
その点において、流動資産の中でも、棚卸資産(原材料、仕掛品、半製品、商品、製品、貯蔵品など)は現金化するために販売というプロセスが必要であるため、適正に管理し過剰在庫を抱えないようにしなければなりません。現金が少ないようであれば、たとえば、在庫の商品や製品を値引きで販売するなど、手元の現金を増やすことも選択しなければなりません。
棚卸資産を効率的に管理する方法
棚卸資産を適切に管理することで、経理業務の負担を軽減し、企業の資金繰りを改善できます。適切な評価方法を用いることで、決算書の精度が向上し、財務状況を正確に把握できるようになります。ここでは、棚卸資産を効率的に管理するための具体的な方法を解説します。
適切な棚卸の実施
棚卸資産を正確に管理するためには、定期的な実地棚卸(実際に数を数えること)が欠かせません。特に、在庫の数え間違いや記録ミスを防ぐために、棚卸ルールを明確にしておくことが重要です。期首からの在庫の動きを管理し、仕掛品や半製品も適切に把握することで、経理業務の効率化につながります。
過剰在庫の削減
過剰在庫は資金繰りを圧迫する要因となるため、適切な在庫管理が求められます。適正な在庫水準を維持することが重要です。また、不要な在庫は定期的に見直し、値引き販売や廃棄などの処理を検討することで、キャッシュフローを改善できます。
会計ソフトの導入
近年、会計ソフトの導入が進んでおり、会計業務や在庫管理の効率化に役立っています。会計ソフトを活用することで、売上債権や仕入の計算を自動化し、決算業務の負担を軽減できます。クラウド型の経理業務支援システムを導入することで、リアルタイムで在庫状況を把握し、正確な財務データを活用できるようになります。
棚卸資産に関する注意点
棚卸資産の管理を怠ると、決算時に想定外の損失計上が必要になることがあります。特に、税務処理に関するルールを理解し、適切な対応を行うことが重要です。ここでは、棚卸資産に関する注意点を解説します。
棚卸評価損の計上が必要になることがある
棚卸資産の価値が帳簿上の数字と合わない場合、決算書の正確性を維持するために適切な処理を行う必要があります。たとえば、商品の原価よりも時価が下がってしまった場合、帳簿との差額を棚卸評価損として損益計算書に計上します。また、商品の価値が下がった場合は、商品評価損を計上し、損益計算書に正しく反映させることが求められます。
評価方法について税務署へ申告しなければならない
棚卸資産の評価方法は、原則は「原価法」、届出によって選択すれば「低価法」となります。また、税務上は届出をしなければ、原則評価損が認められません。最終仕入原価法、移動平均法、売価還元法など、企業の業態や管理方針に応じた評価方法を選定し、申告を行うことが重要です。適切な申告を怠ると、税務調査の際に指摘を受ける可能性があるため、法人税の計算にも影響を及ぼす点に注意しましょう。
まとめ
今回は流動資産と、その中の棚卸資産について解説しました。
資金の流動性といった点では現金が優れていますが、現金を棚卸資産やそれを製造する固定資産に変えなければ収益は発生しません。資金の流動性と収益性のバランスに注目しながら、流動資産を分析してみましょう。
また、流動資産の中でも、棚卸資産の管理は重要です。棚卸管理を徹底し、適切な税務処理を行うことで、企業の財務状況を健全に維持し、効率的な経理業務を実現することができます。一度社内の現状を確認してみてはいかがでしょうか。
流動資産と棚卸資産に関するQ&A
最後に、流動資産と棚卸資産に関するよくある質問についてお答えします。
Q1.棚卸資産の評価方法にはどのようなものがある?
棚卸資産の評価方法には、大きく分けて原価法と低価法の2種類があります。
原価法は仕入や製造にかかった取得価額を基準として評価する方法で、個別法や先入先出法、総平均法などの種類があります。
低価法は棚卸資産の評価額が取得原価を下回った場合に、低い方の価格を採用する方法です。市場価格の下落などにより、時価が取得価額を下回る場合に適用します。
Q2.流動資産と棚卸資産の違いは?
流動資産は短期的(1年以内に)現金化できる資産全般を指し、棚卸資産はその中の一部で、販売目的で保有する商品や原材料を指します。
Q3.流動資産と固定資産の違いは?
流動資産は短期的(1年以内)に現金化される資産であり、固定資産は長期的(1年超)に保有し、事業に使用される設備や土地などを指します。
Q4.流動資産の主な勘定科目は?
現金預金、売上債権(売掛金・受取手形)、棚卸資産、前払費用、仮払金、貸付金、文房具などの消耗品などが含まれます。
Q5.会社の流動資産の確認方法は?
決算書(貸借対照表)を確認し、現金預金や売上債権、棚卸資産などの勘定科目をチェックします。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。