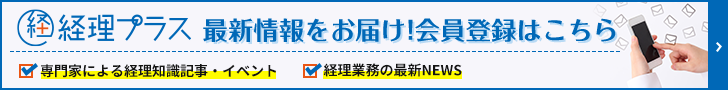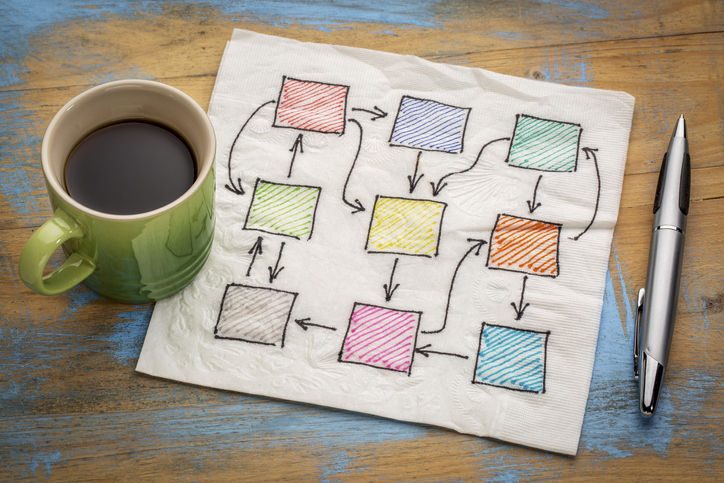領収書を紛失!再発行はできる?困った時の対処法

領収書とは?そもそも何のための書類なのか?
領収書とは金銭の受領を証する書面のことをいいます。手形などと違って現金には流通の記録が残りません。現金を渡しても後で「受け取っていない」と言われると実際に渡したことを後になって証明するのは非常に難しいです。そのため、金銭を受領した証拠として、受領した側が金銭を渡した側に交付します。これにより金銭の受渡の事実が明らかとなり、後々のトラブルを防ぐこととなります。
なお、代金を相互に相殺した場合や銀行で振込したとき、クレジットカードで支払ったときなどは現金の受渡がないため領収書を発行する必要はありませんが、このような場合でも領収書を発行することはあります。
印紙の必要性
領収書は印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書、領収書」にあたり、印紙税の課税物件です。収入印紙の額は、売上代金に係る受取書か売上代金以外の受取書かで変わってきますが、どちらにしても、領収書の記載金額が5万円未満のものは非課税となります(平成26年3月31日以前は3万円未満のものが非課税でしたが、非課税となる範囲が拡大されました)。
そのため、領収書の記載金額が5万円以上のときは、決められた収入印紙を領収書に貼り付けし、消印しなければなりません。ただし、たとえば、友人間でお金のやりとりをしたような場合など、営業に関連しないものは金額にかかわらず非課税となります。営業にあたるかどうかは、おおむね営利を目的として同種の行為を反復・継続して行っているかどうかを社会通念に照らして判断します。
5万円以上かどうかの判断は、通常は税込金額で行います。ただし、領収書に記載された金額に含まれる消費税額を明らかにしているような場合などには、税抜金額で判断してもよいこととされています。
領収書が必要になるのはどんなとき?
金銭の授受などがあったときは、経理担当者は領収書に基づいて経理処理をする必要があります。
また、領収書などの書類は、取引の事実を表す大事な書類ですので、一定期間保管しておかなければなりません。さらに消費税の仕入税額控除をするためには、原則として領収書(または請求書など)がなければなりません。
なくしたとき、領収書の再発行はできる?
領収書は金銭を受渡した事実を証明する書類なのでむやみやたらに再発行はしてもらえません。同じ内容の領収書が2枚あると、2回金銭の受渡があったこととなり、トラブルになりかねないからです。ただし、なくした事実を説明し、理解が得られた場合は、再発行しもらえることもあります。そのような場合は、通常、領収書に再発行であることが分かる記載がされます。商店や病院でも再発行してもらえることはあるでしょう。
しかし、電車やタクシーのような交通機関で、後から領収書を再発行してくれといっても、その事実を証明するのができないので、再発行してくれるかは難しいでしょう。
領収書を紛失したときの対処法
仮に領収書を紛失したときには、すぐに支払先、金額、内容等をメモに残してください。そして出金伝票や会社所定の書類にその内容を記載して、経理処理すれば、それが事実であると認められる場合に限り、税務上も経費処理することができます。
消費税の仕入税額控除に関しても、支払額が30,000円未満(税込)のときは、領収書(または請求書など)の保存は要件とされておらず、必要な事項を帳簿に記載しておけばよいこととされています。また、30,000円以上であっても、やむを得ない理由がある場合には、帳簿にやむを得ない理由などを記載しておけば、仕入税額控除は認められることとされています。
いずれにしても、帳簿への記載が要件ですので、領収書を紛失したときは、速やかに記録を残し、忘れないようにしておく必要があります。
領収書なしでの各種申請 ペナルティはある?
仮に領収書なしで法人税や消費税などの申告を行い、それが後に行われた税務調査などで判明すると、場合によっては経費の支出を否認され、法人税や消費税などが追加で課税される可能性があります。領収書がないからといって、すべてが直ちにアウトになる訳ではありませんが、その他の資料によっても支出の事実を裏付けることができないものが多額にあるような場合は、架空経費を計上しているときとの違いを明らかにすることができないので、否認される可能性はあります。そのような場合に追加で法人税や消費税が生じたときは、過少申告加算税などのペナルティが課されることとなります。
まとめ
領収書は経理処理や税金に係る大切な書類です。まずは受領したら紛失しないように保管しておきましょう。もし紛失してしまった場合には、再発行を依頼したり、その内容を明らかにするように出金伝票やその他のメモを直ちに作成し、保管しておく必要があります。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。