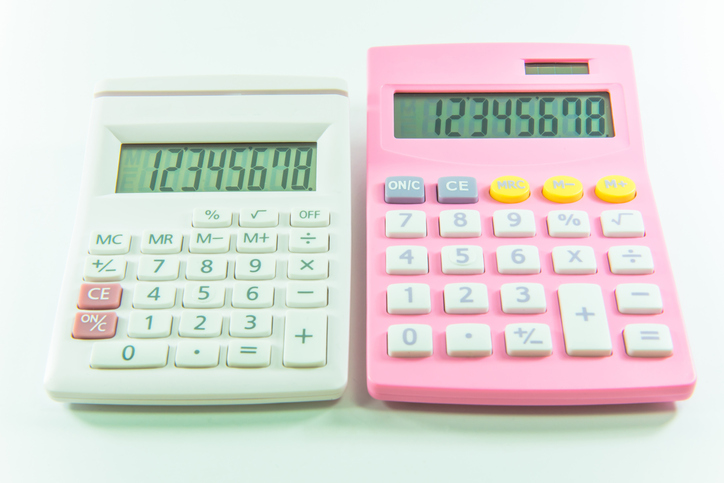原価とは?製造原価・売上原価の違いと分類方法、計算を行う目的

経理部門で原価の計算をしなければならなくなった場合、まずは原価とは何か、原価を計算する方法にはどのような方法があるのかを把握しておかなければなりません。適切に原価計算できれば、利益・コストを正しく把握できるためコストマネジメントが図りやすくなるため、収益性の向上といった経営管理にもつながるでしょう。
本記事では、原価とは何か、原価の分類方法、原価を計算する目的について解説していきます。
これらの基礎を知っておくことで、適切に原価計算を行えるようになるでしょう。
そもそも原価とは
企業が製品やサービスを提供する過程で発生する費用を総称して原価と呼びます。
原価の基本を理解することは、経営の効率化、価格設定、利益の最大化といったビジネスの戦略を練るうえで不可欠なものです。
以下では、原価についてその定義と考え方を解説します。
原価は、商品やサービスを生産・提供するために直接的にかかる費用を指します。
これには、原材料費、人件費、製造に必要な光熱費など、商品の完成までに必要なすべてのコストが含まれます。
原価を理解し、適切に管理することで、企業は費用を抑えつつ価値の高い商品を提供することが可能になります。
原価の定義
原価とは、商品を製造・販売する際にかかる費用のことを言います。経営活動における経済価値の消費を金銭的に表わしたものであり、商品やサービスを製造・販売する過程で発生する費用を指すものです。
原価には、直接的な材料費や人件費のほか、製品を市場に提供するための広告宣伝費なども含まれます。具体的には、製品の製造に必要な原材料の購入費、製造過程で働く従業員への賃金、製品を市場に認知してもらうための広告宣伝活動にかかる費用などが原価には含まれます。これらは全て、製品の価格設定や利益計算において重要な要素となるものです。
原価には製造原価と売上原価の2種類がある
原価は大きく分けて、製造原価と売上原価の2種類に分類されます。
製造原価は製品の製造に直接かかった費用、売上原価は売れた製品の仕入や製造にかかった費用を指します。売上原価は製造原価を含む、より広い概念です。
製造原価とは
製造原価は、製品の製造に直接関わる原価を意味します。製造原価には、使用された原材料のコスト、製造過程での労働に対する賃金、製造設備の維持に必要な光熱費などが含まれます。製造原価を把握することは、コスト削減の機会を特定し、製品の価格競争力を高めるために重要です。
また、製造原価の詳細については以下の記事をご参照ください。
売上原価とは
一方、売上原価は、顧客に売れた製品の仕入や製造にかかった費用を指します。売上原価の管理は、販売プロセスの効率化と利益率の最適化に寄与します。
売上原価の業種ごとの違い
売上原価は業種によって含まれる費用が異なります。
製造業では、材料の仕入原価の他に、製造・開発担当の人件費や生産コストが売上原価に含まれます。製造・開発などに直接かかわらなかった人件費については、配賦されて売上原価に計上されます。
小売業の売上原価は仕入原価が大部分を占めます。
サービス業については、サービスに必要な外注費などは売上原価となりますが、サービスを管理する社員の人件費は販売費及び一般管理費に分類されるため、売上原価に含まれません。
経理プラス:製造原価とは?売上原価との違いや分類・計算方法、計算時の注意点
原価の主な分類方法
原価を分類する方法には、その目的、製品やサービスとの関係性、および変動の有無に基づいて大きく3種類の方法があります。この分類は、企業がコスト構造を詳細に理解し、効率的な価格設定やコスト管理戦略を策定する上で重要です。形態別の分類は、原価をその発生原因により分ける方法です。製品との関連における視点別の分類は、製品やサービスの製造・提供過程における原価の関連性に着目しています。変動の有無による分類は、原価が生産量や売上の変動に応じてどのように変化するかを基準にしています。
形態別の分類
| 原価 | 概要 |
|---|---|
| 材料費 | 製品の製造に必要な原料や資源の仕入れにかかる費用 |
| 労務費 | 製品の製造に関わった従業員にかかる賃金や福利厚生費などの費用 |
| 経費 | 減価償却費や光熱費など、材料費と労務費以外の費用 |
形態別の原価分類は、原価を発生させる活動の種類に基づいています。
材料費は、直接的な製品製造に必要な物質的な資源に関わる費用を指し、労務費は製品製造に従事する従業員の労力に対する報酬を示します。
経費は、これらのカテゴリには含まれないが、製造プロセスや企業運営に必要なその他の費用をカバーします。
これらの分類により、企業はコスト構造を明確に理解し、コスト削減や価格設定の戦略を有効に立案できます。
製品との関連における視点別分類
| 原価 | 概要 |
|---|---|
| 直接費 | 原材料費や従業員の給与など、製品の製造に直接かかった費用 |
| 間接費 | 消耗品費や減価償却費など、製品の製造にかかった金額を特定できない費用 |
製品との関連における視点別の分類では、原価を製品製造やサービス提供における直接性の度合いに応じて分けます。
直接費は、特定の製品やサービスに直接帰属できる費用で、その製品やサービスのコストを正確に測定するのに役立ちます。一方、間接費は製品やサービスごとに費用を直接割り当てることが困難な費用であり、これらを適切に管理することが全体のコスト効率を高める鍵となります。
変動の有無による分類
| 原価 | 概要 |
|---|---|
| 変動費 | 生産量に応じて発生する原料費や消耗品費など |
| 固定費 | 生産量に関係なく発生する労務費や減価償却費など |
変動の有無による分類は、原価が事業活動の変化にどう反応するかをもとにした分類方法です。
変動費は、生産量や売上の増減に直接連動して変化する費用です。一方、固定費は、活動レベルの変化に関わらず一定のままであり、企業の固定的な負担となります。
これらを把握し管理することで、企業はより柔軟に財務計画を立て、リスクを低減できます。
原価を算出する主な目的
製品やサービスの原価を正確に理解することは、価格設定、コスト管理、利益最大化戦略の策定に直結します。このプロセスを通じて、企業は無駄を省き、競争力を高めることが可能になります。
原価計算の目的は多岐にわたりますが、主に無駄なコストの削減、損益分岐点の明確化、適正価格の設定、そして精度の高い予算計画の立案に役立ちます。原価を算出して適切に管理することで、企業は持続可能な成長を達成することができます。
無駄なコストを把握できる
原価を正確に算出することで、製品の製造や販売にかかる原価を具体的に把握することができます。
このプロセスを通じて、必要以上に発生しているコストや無駄遣いを特定でき、削減の対象を明確にすることが可能になります。
これは、企業の利益率を向上させるための重要なステップです。
損益分岐点がわかる
原価計算を行うことで、製品の製造にかかるすべての費用を算出することが可能になります。
これにより、企業は損益分岐点、すなわち利益がゼロになる売上高を正確に把握できます。
損益分岐点を知ることは、利益を出すための売上目標を設定し、事業の収益性を高めるために不可欠です。
適切な価格を設定できる
原価を把握することは、製品やサービスの価格設定においても極めて重要です。
原価に基づいて適正な利益を加えた価格を設定することで、企業は適切な収益を確保しつつ、市場競争力を維持することができます。
価格設定の適切さは、顧客満足度の向上や市場シェアの拡大にも寄与します。
精度の高い予算計画を立案できる
原価計算により、企業は製品製造やサービス提供にかかるコストを詳細に把握できるようになります。
この情報をもとに、より精度の高い予算計画を立案することが可能です。
予算計画は、資源の配分、投資の決定、財務戦略の策定など、企業運営の各側面において中心的な役割を果たします。
適切な原価計算は、未来の事業活動を効果的に計画し、経営の効率化を図るために不可欠です。
適正な利益を得られるよう製品・サービスにかかる原価の管理を行うことを原価管理と呼びます。原価管理の詳細については以下の記事をご参照ください。
経理プラス:原価管理のために押さえておきたい原価計算の基礎知識
原価計算を行う流れ
原価計算は、企業が製品やサービスのコストを正確に把握し、適切な価格設定やコスト管理を行うための基本プロセスです。この計算プロセスは主に3つのステップに分かれています。以下では、この3つのステップについて解説していきます。
Step1. 費目別原価計算
費目別原価計算では、原価を材料費、労務費、製造経費の3つの主要カテゴリに分類します。これらはさらに、それぞれが直接的に製品製造に関連するか、間接的に関連するかに応じて、直接費と間接費に分けられます。直接材料費は製品製造に直接使用される材料のコスト、直接労務費は製品を直接製造する労働者の賃金、直接経費は製品製造に直接かかるその他の費用を指します。一方で、間接材料費、間接労務費、間接経費は製品製造には必要だが、個々の製品に直接割り当てが困難な費用です。このステップを通じて、企業は費目ごとの原価を明確に把握できます。
Step2. 部門別原価計算
部門別原価計算では、企業内の各部門が負担するコストを計算します。このステップは、特に複数の製品を生産する企業にとって重要です。部門別に原価を計算することで、どの製造プロセスや部門がコストを多く消費しているかを特定し、コスト削減の機会を見つけることができます。間接費はこのステップで特に重要な役割を果たし、適切な基準に基づいて各部門に配分されます。
Step3. 製品別原価計算
最終ステップでは、各製品の原価を具体的に計算します。これには、Step1とStep2で計算した直接費と間接費の合計を使用します。製品別原価計算を行うことで、企業は各製品の利益率を正確に把握し、価格設定や販売戦略をより適切に策定できるようになります。また、製品のコスト構造を理解することで、コスト削減や製品改善のための具体的な方策を立てることが可能になります。
なお、原価計算の詳細については以下の各記事をご参照ください。
経理プラス:原価計算とは?目的・種類・計算方法・仕訳例など基本知識を解説!
経理プラス:個別原価計算とは?総合原価計算との違いや必要な書類、計算の流れ
経理プラス:標準原価計算とは?メリット・デメリットや計算の流れ、よくある質問もご紹介
経理プラス:総合原価計算とは?個別原価計算との違いやメリット、計算の流れ
まとめ
原価とは、製品やサービスの提供に必要な経済的価値の消費を指します。原価には製造原価と売上原価の2つがあります。製造原価は製品を製造する過程で直接かかる材料費、労務費、製造経費などを含みます。一方、売上原価は販売された製品のコストを指し、販売可能な製品を生産するために実際に消費された費用を表します。原価計算を行う目的は、コスト管理を効果的に行い、適切な価格設定や財務戦略の策定を支援することにあります。原価を計算することは、企業の競争力や効率性に直結する重要なものであることを認識しなければなりません。原価を適切に把握することで、利益率の設定、目標となる売上高の設定、予算の設定など、企業活動に欠かせない活動が可能となります。
原価に関するQ&A
正確な原価計算により、企業は適切な価格設定、利益の最大化、財務報告の精度向上を実現できます。ここでは、原価計算の方法、労務費と人件費の違い、財務諸表作成時の原価計算の必要性、および原価の管理や計算を簡単に行う方法についてのQ&Aを通じて、原価計算に関する一般的な疑問に答えていきます。
Q1. 原価計算の方法にはどんな種類がある?
原価計算の方法は、生産形態と原価の捉え方の2つの観点で大別されます。生産形態に基づく分類では、「個別原価計算」と「総合原価計算」があります。個別原価計算は、個々の製品や案件ごとに直接費用を計算する方法です。一方、総合原価計算は、一定期間内の生産コストを全体で計算し、後で製品やサービスごとに割り当てる方法です。原価の捉え方に基づく分類では、「全部原価計算」と「直接原価計算(部分原価計算)」があります。全部原価計算は、製品製造に関わるすべての費用を原価として計上する方法で、さらに「標準原価計算」と「実際原価計算」に分けられます。標準原価計算は、あらかじめ設定した標準のコストで計算する方法、実際原価計算は、実際にかかったコストに基づいて計算する方法です。直接原価計算は、製品の製造に直接関連する費用のみを原価として計上し、固定費などの間接費は原価に算入しない方法です。
Q2. 原価における労務費と人件費の違いは?
労務費は、製品の製造やサービスの提供に直接関わる従業員の賃金や福利厚生費などを指し、人件費に含まれます。人件費は、企業全体で支払われる賃金や福利厚生費など、従業員に対するすべての支出を広く指す用語です。
Q3. 財務諸表の作成時に原価計算は必要?
はい、損益計算書などの財務諸表の作成には原価計算が必要です。原価計算を行うことで、製品の製造にかかった費用を正確に把握し、財務諸表に正確な金額を記載することができます。これにより、企業の経営成績を正確に反映し、外部のステークホルダーに対して信頼性の高い情報を提供することが可能になります。
Q4. 原価の管理や計算を簡単に行う方法は?
原価の管理や計算を簡単に行う方法の一つに、システムの導入があります。特に、「楽楽販売」のようなクラウド型の販売管理システムは、複雑な金額計算や請求・売上計上を自動化し、販売管理の手間とミスを解消することができます。「楽楽販売」では、原価計算だけでなく、在庫管理や販売促進活動の管理も一元的に行うことが可能です。これにより、企業は原価の正確な把握や効率的な財務管理を実現し、経営の効率化を図ることができます。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。