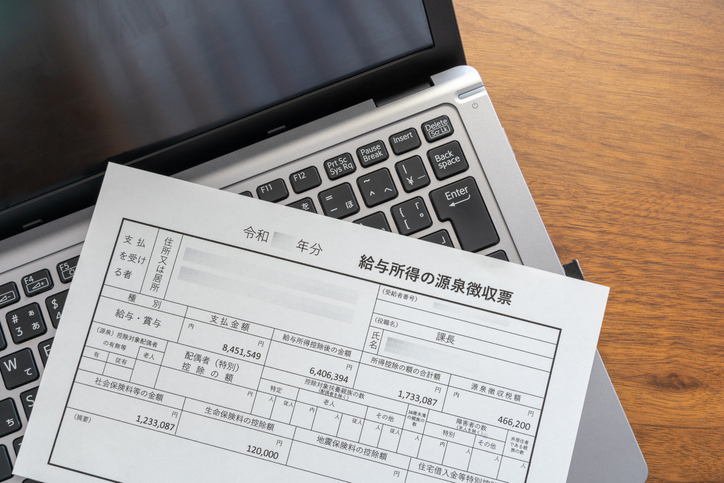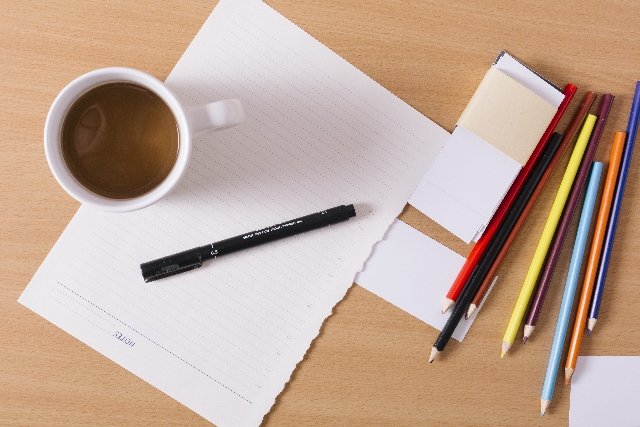電子帳簿保存法の事務処理規程とは?記載項目と作成時のポイント

電子帳簿保存法に対応するためには事務処理規程の備え付けが必要ですが、中小企業の経理担当者の方はどのように事務処理規程を作成し、備え付ければよいかでお悩みの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、電子帳簿保存法において取引データを保存する際に備え付けが原則として必要になる事務処理規程について、その作成方法を具体的に解説します。事務処理規程を備え付けることで事業者側にどのようなメリットがあるかについても解説するのでぜひ参考にしてください。
また、電子帳簿保存法については以下の記事をご参照ください。
関連記事:電子帳簿保存法とは?これを読めば電帳法の基本的な内容が分かります
電子帳簿保存法の事務処理規程に関する基礎知識
電子帳簿保存法では、電子取引データの改ざんを防ぐために、事務処理規程を設けることを求めています。電子取引の取引情報を電子データとして保存するためには、そのデータが本物であることを保証しなければなりません。保存された取引情報を保証するためには、改ざん防止手続きが必要です。
電子帳簿保存法の事務処理規程とは?
電子帳簿保存法では、以下の1〜4のうち、いずれかの改ざん防止手続きを行うことを求めています。
- タイムスタンプを付したあとに受け渡しを行う
- 授受のあと、速やかにタイムスタンプを付す
- データの訂正削除を行った場合、訂正削除の記録が残るシステム、またはデータの訂正削除を行うことができないシステムを利用してデータの受け渡しと保存を行う
- 訂正削除の防止について事務処理規程を備え付ける
この4つの要件は、「真実性の確保」の要件と呼ばれるものです。
なお、電子取引を行い、そのデータを保存する場合には、上で説明したデータが改ざんされていない本物であることの保証(真実性の確保)に加えて、保存されたデータの検索・表示ができるようにする必要があります。これは「可視性の確保」と呼ばれます。
「真実性の確保」とは?
電子帳簿保存法が求めている改ざん防止手続きは、上記1〜4のいずれかであるため、事業者はいずれかの要件を満たすことが必要となります。
1〜3は、電子帳簿保存法に対応したシステムを導入することで満たすことができますが、システムの導入にはコストや運用面を考慮することが必要です。そのため、必要最低限のシステムだけではなく、自社の状況に応じて事務処理規程等、さらに担当者のリテラシー向上なども併せて整備し、真実性や可視性を確保する運用体制を構築することが重要です。
事務処理規程を作成しなくてもよいケース
事務処理規程を作成する目的は、電子取引におけるデータ保存の際に求められる「真実性の確保」の要件を満たすためです。つまり、すべてのケースにおいて事務処理規程の作成が義務付けられているわけではありません。データの改ざん防止が他の手段で確保できる場合は、作成する必要はないことを知っておきましょう。
たとえば、電子取引に対応したシステムを導入し、タイムスタンプを付与したり、訂正・削除の履歴を保持できる仕組みを導入したりすれば、データの真実性が担保されます。その場合は、事務処理規定の作成は不要です。
電子帳簿保存法の事務処理規程の作成の流れ
電子帳簿保存法の事務処理規程を作成する流れは、以下のとおりです。
- ステップ1:国税庁のホームページからサンプルをダウンロードする
- ステップ2:自社に合わせて各項目を書き換える
- ステップ3:事務処理規程で定めた運用体制を整備する
それぞれの内容を解説します。
ステップ1:国税庁のホームページからサンプルをダウンロードする
事務処理規程は、ゼロベースから作成する必要はありません。国税庁が参考資料として公開しているサンプルを使用すると効率よく作成できます。
まず、国税庁のホームページにアクセスし、電子帳簿保存法に対応した事務処理規程のサンプルをダウンロードしましょう。
サンプルのままでは使用できないため、ダウンロードした文書を確認し、項目内容を把握したうえで、どの部分を自社向けに修正するべきかを確認しておきます。事前に規定内容を理解しておくと、自社向けの事務処理規程をスムーズに作成できるでしょう。
国税庁が公開している法人向けのサンプルは、こちらをご参照ください。
参考:国税庁「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(法人の例)」
ステップ2:自社に合わせて各項目を書き換える
サンプルの事務処理規程を基に、自社の電子取引の状況を踏まえて各項目を書き換えます。
たとえば、国税庁のサンプルにも電子取引の範囲は記載されていますが、あくまでも一例です。企業によって電子取引の範囲は異なるため、自社の電子取引の範囲を洗い出し、漏れなく記載する必要があります。固定の対象となるデータについても、自社の実態に合わせて修正しましょう。
ステップ3:事務処理規程で定めた運用体制を整備する
事務処理規程の作成が完了した後は、規定に基づいた社内の運用体制を整備します。具体的には、管理責任者や処理責任者を選定し教育を行う、電子取引データを授受する従業員にも運用フローを理解してもらうよう周知する、といった取り組みが求められます。
また、「取引情報訂正・削除申請書」や「取引情報訂正・削除完了報告書」についても、あらかじめ準備しておきましょう。事務処理規程は、一度保存した電子取引データの訂正・削除を原則禁止しています。
そのため、業務上やむを得ない理由によって、保存している取引関係情報を訂正・削除する場合は「取引情報訂正・削除申請書」を作成します。法人の場合はさらに、「取引情報訂正・削除完了報告書」の作成・保存も必要です。
電子帳簿保存法の事務処理規程の記載項目と作成時のポイント
電子帳簿保存法のもとでは、事務処理規程を作成しなければならないケースがほとんどです。事務処理規程を作成する場合、会社の事業規模やワークフローに合わせて、その記載内容を調整しなければなりません。次では、事務処理規程の記載項目と作成時のポイントについて解説していきます。
事務処理規程の記載項目
電子帳簿保存法に対応するうえでは、電子取引の保存について各事務処理を定めた規程等を準備する必要があります。
具体的には、以下で示す事項について事務処理規程等に盛り込まなければなりません。
全体の運用に関するもの
- 目的
- 適用範囲
- 管理責任者
電子取引データ保存
- 電子取引の範囲
- 取引データの保存
- 対象となるデータ
- 運用体制
- 訂正削除の原則禁止
- 訂正削除を行う場合の手順
事務処理規程を作成する際のポイント
事務処理規程については、国税庁がテンプレートを公表していることから、それを利用して作成するのが一般的です。ただし、事務処理規程を作成する場合には、自社の事業規模やワークフローによってその内容を調整しなければなりません。
したがって、以下では、国税庁のテンプレートをどのように調整すべきか、事務処理規程作成のポイントを説明していきます。
事務処理規程の最初には、「目的」・「適用範囲」・「管理責任者」という全体の運用に関する事項(総則)を記載します。これらの項目については、テンプレートをそのまま利用すれば問題ありません。
重要となるのは、次の電子取引データの保存に関する事項です。「電子取引の範囲」については、事務処理規程の対象となる電子取引の範囲を具体的に示さなければなりません。保存の対象となるかどうか事務処理規程の記載から判断できるようにするためです。
たとえば、自社の電子取引の実態に合わせるかたちで、以下のように記載をします。
- EDI(Electric Data Interchange)取引
- 電子メールにより送られてきた請求書データ(PDFファイル等)
- クラウドサービスで共有した電子請求書データ
- クラウドサービスを利用して取り込んだクレジットカード利用明細データ
- 電子マネーのデータ
- スマートフォンアプリによる決済データ
参考: 国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問2」、「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 問4」
このように、具体的かつ明確に電子取引の範囲を記載しておくことが大切です。利用している電子取引が他にもあれば、具体的に記載しておきましょう。
次に、「取引データの保存」について記載します。電子取引データについては、場所を取ることがないので、保存期間については必ずしも明示する必要はありません。
- 取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち、第6条に定めるデータについては、保存サーバ内に△△年間保存する。
さらに、「対象となるデータ」を記載します。代表的なものは次のとおりです。
- 見積依頼情報
- 見積回答情報
- 確定注文情報
- 注文請け情報
- 納品情報
- 支払情報
会社が取引先と交わす取引関係情報があれば、さらに記載が必要となります。
また、「運用体制」については、取引関係情報の責任者および処理責任者を明示します。
- 保存する取引関係情報の管理責任者及び処理責任者は以下の通りとする。
- 管理責任者 ○○部△△課 課長 XXXX
- 処理責任者 ○○部△△課 係長 XXXX
基本的に、国税庁のテンプレートをそのまま利用して問題ありません。
次に、事務処理規程のなかでも特に重要な事項である「訂正削除の原則禁止」を記載します。
- 保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。
上記のように訂正削除の原則禁止を明示したうえで、例外的に訂正削除を行う場合には、どのような対応が必要であるかを明示します。
- 業務処理上やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正または削除する場合は、処理責任者は「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、管理責任者へ提出すること。
- 申請日
- 取引伝票番号
- 取引件名
- 取引先名
- 訂正・削除日付
- 訂正・削除内容
- 訂正・削除理由
- 処理担当者名
- 管理責任者は、「取引情報訂正・削除申請書」の提出を受けた場合は、正当な理由があると認める場合のみ承認する。
- 管理責任者は、前項において承認した場合は、処理責任者に対して取引関係情報の訂正及び削除を指示する。
- 処理責任者は、取引関係情報の訂正及び削除を行った場合は、当該取引関係情報に訂正・削除履歴がある旨の情報を付すとともに「取引情報訂正・削除完了報告書」を作成し、当該報告書を管理責任者に提出する。
- 「取引情報訂正・削除申請書」及び「取引情報訂正・削除完了報告書」は、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、訂正・削除の対象となった取引データの保存期間が満了するまで保存する。
参考:国税庁「参考資料(各種規程等のサンプル)」
電子帳簿保存法の事務処理規程を作成しないリスク
電子帳簿保存法の事務処理規程を作成しないことで懸念されるリスクは、以下の4点です。
- 税務上で不利益を被る
- 罰則や過料が発生する
- 業務の混乱や企業の信用性の低下を招く
- データの検索性や真実性が危ぶまれる
それぞれの内容を解説します。
税務上で不利益を被る
電子帳簿保存法における事務処理規程を作成していないと、青色申告の承認が取り消される点がリスクの1つです。法人の場合は、欠損金の繰越控除ができなくなるなどの税務上における不利益を被ります。法人の場合は、欠損金の繰越控除ができなくなるなどの税務上における不利益を被ります。
罰則や過料が発生する
電子帳簿保存法では、直接的な罰金や刑事罰の規定はありません。しかし、税務調査で事務処理規程を作成していない・備えていないことが不備とみなされることがあります。結果的に、納めるべき税金が納付されていない場合は追加の税金が課せられたり、会社法による過料が課されるリスクが生じたりすることに注意しましょう。
業務の混乱や企業の信用性の低下を招く
業務の混乱や企業の信用性の低下を招きかねないことも、電子帳簿保存法の事務処理規程を作成しないことで懸念されるリスクの1つです。
事務処理規程がない場合、電子帳簿の管理や運用に一貫性を保持できないことから、データの改ざんや紛失などが起こりやすくなります。結果的に、企業の内部管理や対外的な信頼が揺らぎ、新たな業務上の課題が生まれる場合があります。
データの検索性や真実性が危ぶまれる
電子帳簿保存法における事務処理規程を作成していないと、データの検索性や真実性が危ぶまれることも、リスクとして挙げられるでしょう。検索性や真実性の確保に関する要件が満たされていない場合、税務調査が入った際に速やかに必要な情報を提供できない恐れがあるためです。
それにより、課税額が増えたり、罰金が発生したりするケースも考えられます。
システムを導入していても事務処理規程を作成したほうが良い理由
真実性を確保するためのシステムを導入している場合でも、事務処理規程は作成しておくべきです。なぜなら、システムで対応しきれないケースがあるからです。その他にも、様々な理由から事務処理規程を作成しておいた方が良いと言えます。
以下では、真実性を確保できるようなシステムを導入している場合でも事務処理規程を作成した方が良い理由を解説していきます。
システムが完全に対応していない場合がある
電子帳簿保存法の真実性の要件に合うシステムを導入している場合でも、システム上の制約から、事務処理規程の備え付けをした方が良いと言えるのは、以下のようなケースが考えられるからです。
- 取引先から受け取ったファイル形式が自社のシステムで授受できないケース
- 単一のシステム上で「授受」と「保存」の要件を満たせないケース
- タイムスタンプ付与の対象となるファイル形式でないケース
1のケースとは、取引先から送信されてきた電子データが自社のシステムで処理できないケースです。取引先の都合次第では、自社が運用しているシステムで電子取引データを授受・保存できるとは限りません。授受・保存できない場合には、事務処理規程に則って処理しなければなりません。
2のケースとは、システムAで授受・保存した電子取引データを、システムBに移行して保存した場合のことを言います。電子取引データは、単一のシステム上ですべて授受・保存をしなければなりません。
しかし、この場合、単一のシステム上で授受・保存の要件を満たすことができていないため、事務処理規程に則って処理することが必要です。両方に対応したシステムの導入はコストがかかり、該当するシステムで自社に合うものがない場合もあることから、事務処理規程を備え付けておく必要があります。
さらに、3のケースとは、たとえば、タイムスタンプが付与できるファイル形式が限られており、取引先から受け取った電子データがシステムに対応していないケースのことを言います。特定のシステムでは、.doc、xlsx、.csv、.tsvなどのファイル形式であった場合、タイムスタンプが付与できない場合があるので注意してください。自社のシステムがどのようなファイル形式に対してタイムスタンプを付与できるか十分に確認してください。
システム上の限界以外にも、事務処理規程の備え付けを行った方が良い理由としては、以下の事項が挙げられます。
- システムの移行がしやすくなる
- 内部統制の強化につながる
- 担当者が変わる際、業務の引き継ぎの負担を軽減できる
それぞれの理由について解説します。
1.システムの移行がしやすくなる
システムだけで電子帳簿保存法の真実性要件を満たそうとすると、システムの柔軟な運用ができなくなる可能性があります。たとえば、システムの移行を考えている際に、既存のシステムAと新しく導入するシステムBで処理できるファイル形式が異なる場合は、システムBへの移行が困難となります。
2.内部統制の強化につながる
事務処理規程を備え付ける場合、事務処理規程で訂正削除を行う場合の手順を明確に示さなければなりません。事務処理規程を守る義務が生じるため、電子取引データの取り扱いが社内で厳格になり、担当者の内部統制に対する意識を強化できます。
3.担当者が変わる際、業務の引き継ぎの負担を軽減できる
事務処理規程に訂正削除の手順が示されているので、担当者が変わっても業務の引き継ぎがスムーズにできることも事務処理規程を備え付けておく大きなメリットです。
電子取引制度への対応は文書管理システムの活用がおすすめ
電子取引制度に適切に対応するためには、文書管理システムの活用がおすすめです。電子取引制度でまず満たすべき要件は「真実性の確保」ですが、「可視性の確保」など、ほかにも満たすべき要件があります。
「可視性の確保」の1つが「検索機能の確保」であり、検索機能の確保を満たすためには、規則的なファイル名をつける、Excelなどで索引簿を作成するなどの対応が求められます。しかし、これらの対応は企業規模が大きくなるほど煩雑になるため、文書管理システムを導入することで、効率的に行えるようになるでしょう。
電子帳簿保存法への適切な対応を行いましょう
電子帳簿保存法は、電子取引データの真実性を保証するための一つの手段として、事務処理規程の備え付けを求めています。システムを活用することで、電子取引データの真実性を保証することも可能ではあるものの、電子帳簿保存法に対応したシステムの導入にはコストがかかります。しかし長期的には、場当たり的に対応するよりも、システムで一貫した対応にした方が事務処理の手間は格段に減少します。そのため、システムを導入したうえで、すべての事業者が事務処理規程の備え付けを考えておくべきです。
事務処理規程を備え付ける場合には、一から作成するのではなく、まずは国税庁が公開しているテンプレートを活用し、その内容を自社の状況に合わせて調整するのがおすすめです。事務処理規程の備え付けを怠った場合には、罰則もあるので注意してください。
電子帳簿保存法と事務処理規程についてのQ&A
最後に、電子帳簿保存法のもとでの事務処理規程についてのよくあるQ&Aを行います。
Q1.事務処理規程のサンプルはどこにある?
事務処理規程のサンプル(テンプレート)は、国税庁がホームページで公表しています。事務処理規程を作成する際には、一から作成しようとせず、国税庁のテンプレートを修正するかたちで作成するのが推奨されます。
Q2.スキャナ保存で規程は必要?
電子帳簿保存法に対応するためには、電子取引の保存に限らず、帳簿書類の電子保存、スキャナ保存についても、各事務処理を定めた規程等を準備する必要があります。そのため、スキャナ保存(スキャナによる電子化保存)にも規程が必要です。
スキャナ保存については、全体の運用に加えて、以下の事項について規程するようにしましょう。
- 対象書類・保存までの時期
- 保存の手順
- 見読性の確保
- 電子化に利用するデバイス
国税庁のホームページでスキャナ保存の事務処理規程についてもテンプレートが用意されているので参考にしてください。
参考:国税庁「参考資料(各種規程等のサンプル)」内、「スキャナによる電子化保存規程(Word)」、「 国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類(Word)」
Q3.事務処理規程の作成が必要なケースで、作成しない場合の罰則は?
事務処理規程の作成が必要なケースで作成を行わなかった場合には、電子帳簿保存法に違反することになるので、以下のような罰則が適用される可能性があります。
- 青色申告の取り消し
- 推計課税を受けたり、重加算税が課される可能性
- 会社法違反として、100万円以下の過料が課される可能性
Q4.電子帳簿保存法の改正でタイムスタンプが不要になったケースは?
スキャナ保存において、これまで領収書を受け取った本人がタイムスタンプを付与する場合には、受領からタイムスタンプ付与まで3営業日以内という期限がありました。
改正後は、「受領後最長2か月+概ね7営業日」以内にタイムスタンプを付与すれば良いことになっています。
ただし、電子帳簿保存法の改正によって、記録した事項(日付、金額など)を確認できる(あるいは訂正削除ができない)システムを利用してデータを保存したケースではタイムスタンプの付与は不要となりました。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。