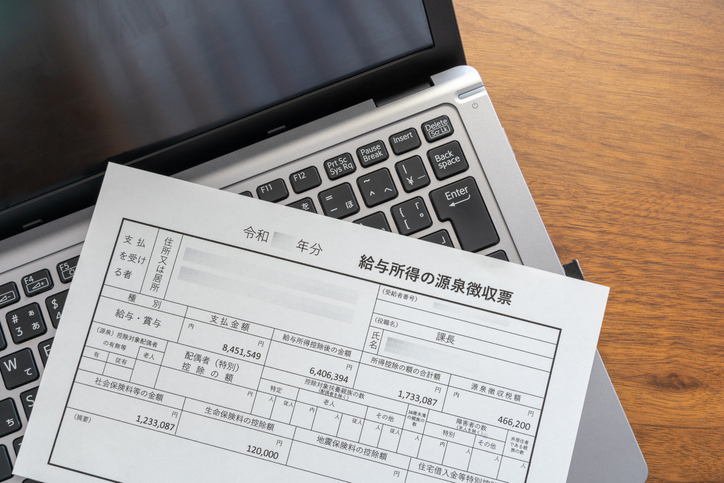減価償却明細書の無料エクセルテンプレートを紹介!固定資産台帳との違いや記載項目も解説
この記事では、誰でも利用できる減価償却明細書の無料エクセルテンプレートを紹介します。また、減価償却明細書と固定資産台帳の違いや、減価償却費の試算方法についても解説します。
テンプレートを使用し、社内における減価償却明細書の書式を統一したいと考えている方や、減価償却の基礎知識を再確認したい方は、ぜひ参考にしてください。
減価償却明細書の無料エクセルテンプレート
減価償却明細書を作成するのであれば、資産名や取得価額だけでなく、耐用年数や期末簿価などの事項を記載する必要があります。
ここでは、必要な項目があらかじめ記載された、減価償却明細書の無料エクセルテンプレートを紹介します。減価償却の管理を不備なくスムーズに行いたいと考えている方は、ぜひご活用ください。

今すぐ使える!無料ダウンロード
減価償却明細書とは
減価償却明細書は、会社が保有する固定資産にかかる減価償却費をまとめた書類です。
固定資産の中には、取得費を経費計上するにあたり減価償却が必要なものがあります。減価償却は、資産の種類によって決まっている年数をかけて、行わなければなりません。そのため、減価償却の進捗状況を管理するために作成するのが、減価償却明細書です。
ここでは、減価償却明細書の基本事項と、固定資産台帳との違いを解説します。
減価償却明細書の基本事項
減価償却明細書は、固定資産の減価償却費を一覧にしたものです。減価償却を正しく管理し、不備のない会計を実現するには、各資産の減価償却の状況や期末の帳簿価額などが一目でわかる減価償却明細書を作成することが、重要なポイントとなります。
なお、確定申告において減価償却明細書の提出は義務付けられていません。ただし、償却資産申告をする際には、自治体への提出を求められることもあるため注意が必要です。
固定資産台帳との違い
減価償却明細書と混合しやすいものとして、固定資産台帳があります。減価償却明細書と固定資産台帳の違いは、以下のとおりです。
- 減価償却明細書:減価償却の状況をまとめた明細
- 固定資産台帳:固定資産の情報をまとめた台帳
減価償却明細書は、固定資産のうち、特に減価償却に関する事項をまとめた書類です。一方、固定資産台帳は、企業が保有する固定資産の全体像を把握するための書類を指します。
減価償却の管理や計算を行う際は減価償却明細書を使用しますが、減価償却の対象となる資産を確認するには、固定資産台帳が必要です。
減価償却明細書への記載事項
減価償却明細書には以下の項目を記載します。
- 勘定科目
- 資産名
- 取得年月
- 取得価額
- 未償却残高
- 耐用年数
- 償却率
- 月数
- 当期償却費
- 期末簿価

それぞれを詳しく見ていきましょう。
1.勘定科目
勘定科目には、購入した固定資産の勘定科目名を記載します。一例を以下で確認しましょう。
| 購入した固定資産 | 勘定科目 |
| 営業車 | 車両運搬具 |
| パワーショベル | 機械装置 |
| 建物 | 建物 |
| パソコン | 工具器具備品 |
勘定科目の欄には、あくまでも会計上の分類となる科目のみを記載してください。購入した固定資産の具体的な内容は、「資産名」で詳しく記載します。
2.資産名
資産名には、購入した固定資産についての具体的な内容を記載しましょう。記載内容の一例には、販売メーカーや機種名、ナンバープレート、設置場所などがあります。
パソコンを複数台購入したときは、識別番号や設置場所を記載し、資産を特定できるようにしておきます。営業車も同様に、ナンバープレートや駐車場所を明記することで、車両を特定できるようにしましょう。
3.取得年月
取得年月には、固定資産を購入した年と月を記載します。年度の途中で購入した場合、減価償却費は購入月から期末までの月割計算で求めるため、日にちまで記載する必要はありません。
減価償却費は、償却率をもとに算出します。なお、償却率は制度改正により変更されており、定額法では2007年4月、定率法では2007年4月と2012年4月に見直されています。取得年月によっては、減価償却費に差が生じる可能性があるため、漏れなく記載することが重要です。
4.取得価額
取得価額は、固定資産の購入価格を記載します。仕訳の際に、車両運搬具や工具器具備品といった、各勘定科目で使用した金額を記載してください。
価格が大きい固定資産の場合、割賦払いやかけ取引で購入するケースもあるでしょう。一括払い以外の支払いをした場合でも、減価償却明細書の取得価額には購入価格を記載します。
5.未償却残高
未償却残高とは、減価償却が済んでいない金額のことです。
初年度は減価償却を一度も行っていないため、取得価額と未償却残高は同額になるはずです。期末が到来したら、未償却残高から当期償却費を差し引いて、期末簿価を算出しましょう。
2年目以降の期首の未償却残高は、取得価額から減価償却累計額を引いた前年度の期末簿価と同額になります。
6.耐用年数
耐用年数には、固定資産ごとに定められている法定耐用年数を記載しましょう。
減価償却費は、耐用年数をもとに算出します。ただし、固定資産が実際にどのくらい使用できるかは、使用頻度やメンテナンスなどによって異なるため、一概には判断できません。そのため、減価償却費を算出する際には、国税庁が定めた法定耐用年数を利用します。
たとえば、パソコンは4年、普通車は6年と定められています。法定耐用年数は、固定資産の種類や用途などによって細かく決められているため、耐用年数の記載にあたっては国税庁ホームページで確認しましょう。
7.償却率
償却率とは、減価償却費の計算で使われる割合のことです。償却率は、減価償却の方法や耐用年数、購入年月によって決められています。
償却率を間違えると、減価償却費の計算にミスが生じます。減価償却費の計算ミスは、確定申告の不備につながる恐れがあります。償却率を記載する際は、事前に国税庁ホームページで十分に確認しましょう。償却率がわからないときには、税務署の窓口で確認すると安心です。
8.月数
月数には、その年度で減価償却の対象となる月数を記載します。期首から期末まで、1年間保有している固定資産を減価償却する場合は、月数は「12」です。一方、期の途中で購入した場合は、購入月から決算月までの月数となります。
9.当期償却費
当期償却費には、当期に償却する減価償却費を記載します。期の途中で購入した場合は、減価償却費の年額を12で割り、対象となる月数を掛けて求めましょう。
たとえば、耐用年数5年の200万円の固定資産を購入した場合、定額法による減価償却費は40万円(200万円×0.2)です。仮に、月数が6か月とすると、当期償却費はおよそ20万円(40万円÷12ヵ月×6か月)となります。
10.期末簿価
期末簿価とは、期末時点での帳簿上の資産価値のことです。期末簿価は、「未償却残高-当期償却額」で求めます。
期末簿価は、来期の未償却残高になる点も押さえておきましょう。
減価償却費を試算してみよう
減価償却費は、定額法と定率法のいずれかで計算し、経費計上します。それぞれの特徴は、以下のとおりです。
- 定額法:毎年同額の減価償却費を計上する
- 定率法:未償却残高に一定の率を乗じて、期ごとに減価償却費を算出し計上する
ここでは、それぞれの試算を確認しましょう。
定額法での計算方法
定額法で減価償却費を求める計算式は、以下のとおりです。
- 定額法の減価償却費=取得価額×定額法の償却率
たとえば、2010年10月に200万円の営業車(普通自動車)を1台購入したとしましょう。普通自動車の耐用年数は、6年です。定額法における、耐用年数6年の固定資産の償却率は0.167です。
毎年の減価償却費は、33万4,000円(200万円×0.167)と計算できます。
定率法での計算方法
定率法による減価償却費の計算方法は、以下のとおりです。
- 減価償却費=未償却残高×定率法の償却率
仮に、耐用年数が5年の固定資産を2012年4月以降に、300万円で購入したとしましょう。償却率は0.4なので、1年目の減価償却費は120万円(300万円×0.4)です。
2年目の未償却残高は180万円(300万円-120万円)なので、減価償却費は48万円(180万円×0.4)となります。
定率法は、購入した期に近いほど、大きな額の減価償却ができる仕組みです。購入直後の税負担を軽減させたいときには、定率法は有力な選択肢となるでしょう。
まとめ
減価償却明細書とは、企業が保有する固定資産に関する減価償却費を一覧にまとめた書類です。
固定資産の購入費用を計上するには、原則として減価償却が必要です。取得日や償却率、耐用年数、当期償却費、期末簿価などを一覧表にすることで、減価償却の計算をスムーズにできるようになります。
特に、固定資産を多く持つ会社は、記載内容に漏れのない減価償却明細書を作成することが重要です。減価償却明細書の作成にお悩みの方は、本記事で紹介したエクセルテンプレートをぜひご活用ください。