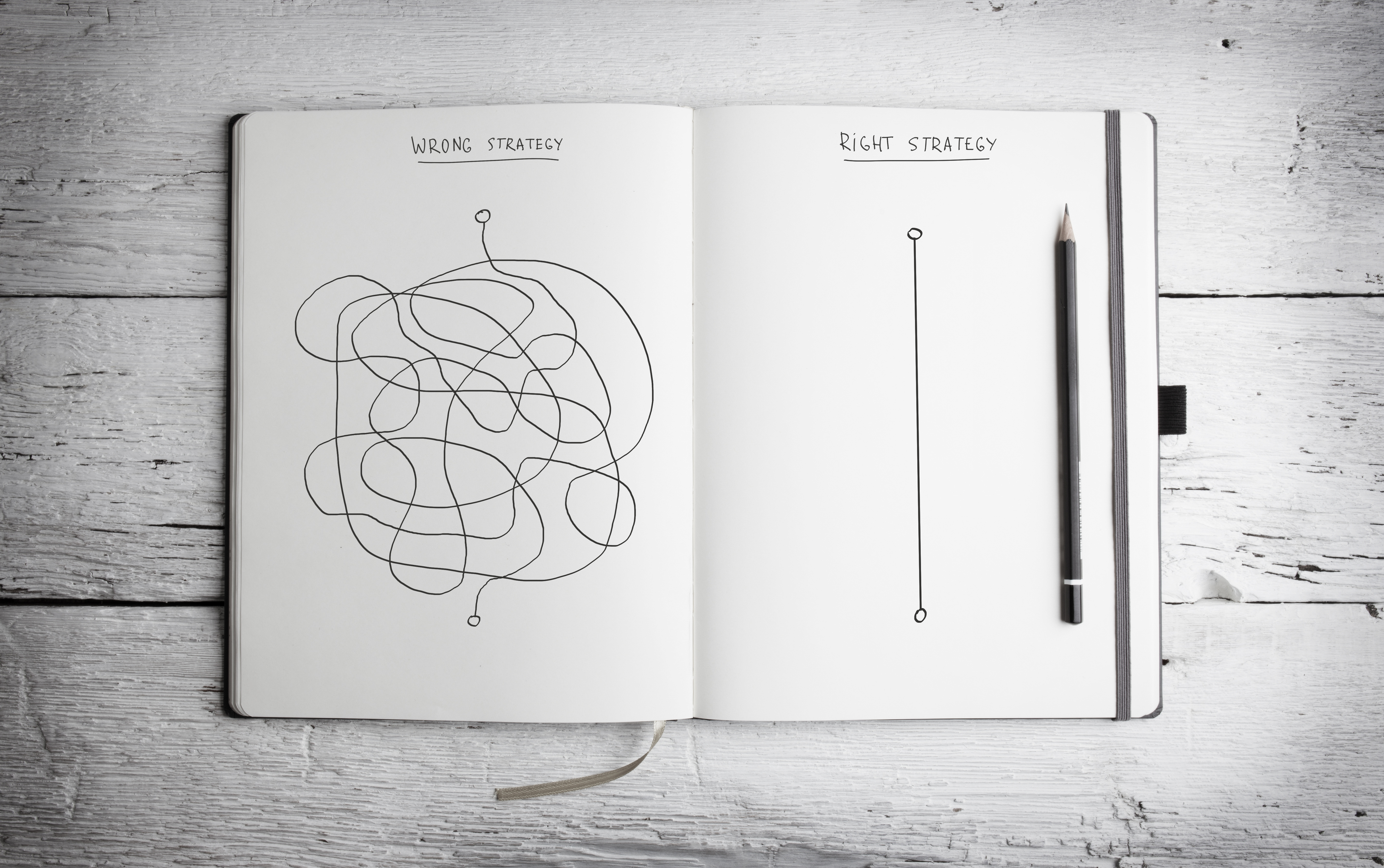なにから教えればいい?新人経理の教育方法

経理部門に新人が配属された際、先輩社員として、どのように教育を進めるのが良いだろうかとお悩みの方も多いのではないでしょうか。
経理といっても会社の規模や組織により、求められるものは異なります。規模が大きい会社では、業務が細分化され、深く狭い専門的な仕事を任されるのに対し、小規模な会社の場合は浅く広く仕事をしなければなりません。
また、小売業や製造業といった業種によっても経費の処理方法が異なります。経理の代表的な仕事である伝票入力も、システムの自動処理で行う会社もありますし、CSVなどのデータを一括で取り込んで処理を行う会社もあります。
つまり、会社によって適した教育方法は異なるということです。
今回は、その中でも共通の要素として押さえておきたい教育のポイントについてまとめてみました
会社の「お金」や「情報」の流れを教える
事業を営むからには、規模にかかわらず「お金」・「情報」・「人」・「もの」が動きます。これらが動くことにより「売上」や「費用」が発生し、「資産」や「負債」の増減が生じます。
これらの動きを「取引」といい、これらを帳簿に記録して管理することが経理の仕事です。
そのため、経理として働くうえで、会社においてどのような時に「取引」が生じるのかを理解しておくことが大切です。
売上の計上基準を例に考えてみます。
小売業、卸売業、建設業、製造業、サービス業、派遣業など業種によって売上の計上基準は異なります。商品販売をしている会社の場合、売上と認識するのは、原則、商品が取引相手に引き渡された時点です。
しかし、引き渡しの時点をいつとするかは、「出荷基準」「納品基準」「検収基準」と基準がいくつもあります。
まずは、会社がどの基準でどのように処理をしているかを理解してもらうようにしましょう。仕入れやその他諸経費に関しても同様です。
書類や証憑について教える
業務を行う上で書類や証憑のやりとりが発生します。外部の会社とやりとりする書類としては、見積書や注文書、注文請書、検収書、納品書、請求書、領収書などがあります。これらの書類を作成する目的は、「契約」や「取引」を証明するためです。各業務で「どの時点」で「どの書類」のやりとりがあるのかを教えましょう。
また、上記以外に独自の書類を利用している会社もあるでしょう。それらの書類はどういう意味があって、どの業務で必要となるものなのかを教えましょう。
私の会社では、各部門で発生する経費の請求書は、各部門長の確認を得て支払処理を行います。その際に、部門長が確認した経費の請求書の束に、「支払依頼書」という頭紙をつけて提出してもらいます。これは、確認した請求書の業者名と金額がリスト表示されている書類です。請求書の支払合計金額を確認するとともに、経理と各部門の間で請求書の授受がきちんとなされたという記録のために利用しています。
冒頭にて、経理は「取引」を帳簿に記録して管理するのが仕事だと述べました。
「取引」が発生する場合、必ず書類や証憑があり、それに基づいて記録しますので、新人経理にも、業務の流れと合わせて理解してもらうことが望ましいです。
経理規定を一読してもらう
経理規定は、経理業務の大枠を一通り理解するのに役立ちます。
後述するマニュアルは細かい処理方法を説明したものであるのに対して、規定は経理処理のルールをまとめたものです。処理方法の判断に迷った場合、上役に判断を仰ぐことが一般的ですが、新人のうちに規定ではどう書かれているのかを毎回確認する習慣をつけてもらうことは大事です。
経理のスケジュールを教える
経理に限った話ではありませんが、はじめての仕事を任されたときは、仕事の優先順位がつかめません。また、複数の業務があるなかで、それぞれをいつまでに終わらせればよいのかも、初めはわからないものです。
そこで「毎日の仕事」「毎月の仕事」「四半期の仕事」「年1回の仕事」など、経理として行う仕事の大まかなスケジュールを教えましょう。
ファイリングのルールを教える
経理には各所からさまざまな書類が届きます。また、問い合わせがあったときに、すぐに書類を確認して答えられなければなりません。そのため、各書類がルールに基づいてファイリングされていなければなりません。
どのような業務の流れで書類が経理に届き、どのような処理を経て、どのようにファイリングをするのかを教えましょう。
マニュアルを見ながら対応できるように教える
仕事の属人化は企業によくあることです。新人の加入は属人化している仕事を標準化する良いきっかけになります。
すでにマニュアルがあるなら、新入社員がマニュアルを見ながら対応できるようにサポートしましょう。社内にマニュアルがない場合は、できれば新入社員が配属されるまでに作成しましょう。マニュアルを読んでも一人で対応ができない場合、マニュアルに不足があると考えて修正します。
新人に業務を任せると同時に、実際に新人にマニュアルに触れてもらいながら、仕事を標準化するのに適した内容になるよう整備しましょう。
数字の確認方法を教える
経費精算システムや会計ソフトなどへの入力作業を終えた後、必ず入力したものが合っているか確認をする習慣をつけてもらうようにしましょう。
書類の数字を入力したのであれば、書類と一致しているかを確認する。データを取り込んで入力したのであれば、データの合計金額と取り込まれた合計金額が一致しているかを確認する……。どのような確認を行うかは処理内容によって異なりますが、必ず何かしらの確認をする習慣を浸透させましょう。
自分の仕事の意味を考える習慣をつけてもらう
新人の入社当初は、会計ソフトや業務システムへの入力が主な業務になると思います。ただ入力業務をこなすのではなく、それらの数字がどのように資料に落とし込まれていくのかを考えて仕事を進められるようにサポートしましょう。
簿記の勉強をしてもらう
経理であるからには「簿記」の理解は必須です。
「簿記」を理解するなら資格取得の勉強が効率的です。4月入社であれば、6月の試験に間に合う可能性が高いので、まずは3級合格を目標にして勉強してもらうようにしましょう。
情報に興味を持ってもらう
経理には、書類を通じてさまざまな情報が集まりますが、重要な情報は書類だけで入ってくるわけではありません。他の部署の社員との雑談などの中で重要な情報が出てくるケースもあります。
未確定の情報でも、それが実現した場合にどのような影響があるのかを想定しておく必要があります。この能力は経験によって身に付く部分が多いですが、自分に関係ない話と思わずに興味を持ってもらえるようにしましょう。
まとめ
当たり前ですが、経理だからといって経理の仕事だけを理解していればいいわけではありません。むしろ、経理は関わる部署が多いので、他の部署の業務についてもある程度理解していなければなりません。
そのためにも、経理の立場から全体を見てもらうことだけでなく、会社全体の中でどのように経理へ情報が集まってくるのかを意識してもらうことが大切です。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。