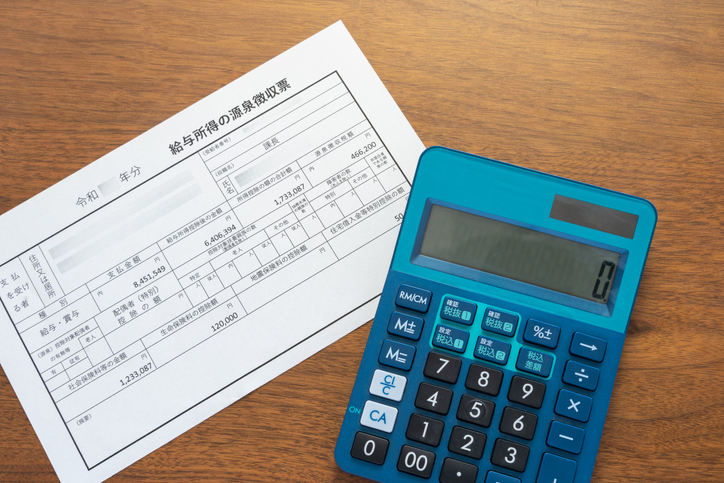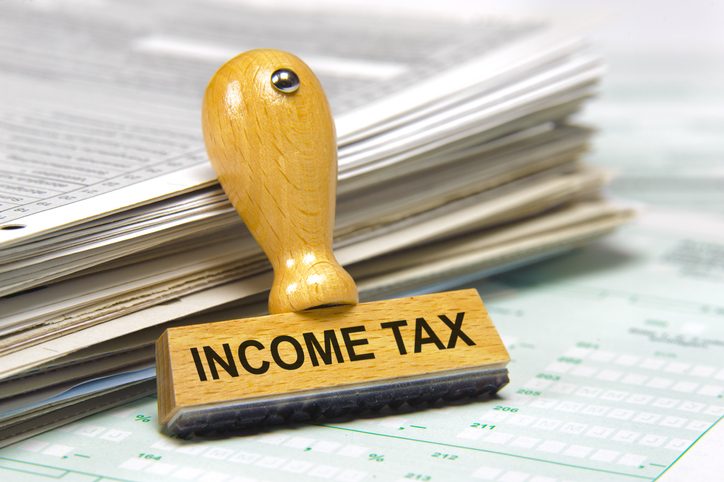源泉徴収票の書き方・作り方とは?記入例を使ってわかりやすく解説
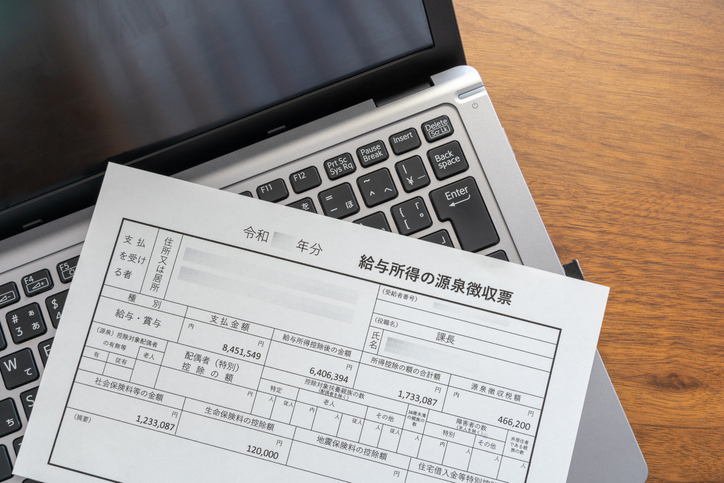
源泉徴収票の書き方で戸惑った場合は、国税庁の書式に沿って、支払金額や給与所得控除後の金額、源泉徴収税額などの記載項目を埋めていきましょう。また、作成時には、記入漏れ・計算ミスを防ぐことや、所得控除の額を間違えないことに注意が必要です。
本記事では、源泉徴収票の書き方について、記入例を交えながらわかりやすく解説します。
源泉徴収票作成のポイント
給与所得の源泉徴収票とは、会社が1年間に支払った給与や手当の金額、源泉徴収した税額などを記載した書類のことです。また、源泉徴収とは企業が従業員の給与・賞与などから税金を天引きし、代わりに納付することを指します。
会社の人事担当者や経理担当者らは、定期的に源泉徴収票を作成して従業員に交付しなければなりません。ここからは、源泉徴収票の発行時期や対象者について解説します。
発行する時期
源泉徴収票は、源泉徴収した税額の年間合計額と年税額を一致させる「年末調整」を実施した後に発行します。
従業員には、12月もしくは翌年1月の給与明細交付のタイミングで一緒に源泉徴収票を交付することが一般的です。また、所轄の税務署に対しても1月31日までに源泉徴収票を提出しなければなりません。
このほかに、従業員が退職する際も、源泉徴収票を発行するタイミングのひとつとして挙げられます。従業員の退職時には、退職年の1月1日から退職日までに支給した給与などに基づき、退職日以降1か月以内に源泉徴収票を発行します。
さらに、源泉徴収票を紛失した従業員から依頼されたときに、再発行することもあるでしょう。よくあるケースとして、源泉徴収票は、住宅ローンを申し込む際に金融機関から提出を求められる書類のひとつのため、従業員が必要とすることがあります。
対象者
源泉徴収票は、すべての受給者に対して対象年の翌年1月31日までに発行しなければなりません。そのため、社員・パート・アルバイト問わず、すべての従業員が対象です。
なお、税務署には一部の従業員の分の源泉徴収票は提出する必要がありません。たとえば、年末調整を実施したケースで、給与支払金額が150万円以下の法人役員や給与支払金額が500万円以下の従業員などは提出の対象外です。
参考:国税庁「No.7411「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」
【記入例付き】源泉徴収票の書き方・主な作成項目
源泉徴収票の主な作成項目は、以下のとおりです。
- 対象者の情報
- 支払金額
- 給与所得控除後の金額
- 所得控除の額の合計額
- 源泉徴収税額
- 控除対象配偶者の有無
- 控除対象扶養親族の数
- 社会保険料等の金額
- 生命保険料の控除額・地震保険料の控除額
- 住宅借入金等控除の額
- 控除対象者の氏名
- 支払者の情報
フォーマットは、国税庁が掲載している給与所得の源泉徴収票を使うとよいでしょう。【入力用】の様式なら、手書きをせずにパソコンから入力してスムーズに作成可能です。ここから、記入例と一緒に書き方を解説します。
対象者の情報
源泉徴収票の一番上に、対象者(支払いを受ける者)の情報を記載します。項目は、以下のとおりです。
- 住所(居所)
- 受給者番号
- 個人番号
- 役職名
- 氏名
受給者番号は社員番号のように会社側が独自に設定している番号、個人番号はマイナンバーを指します。従業員に発行する源泉徴収票については、個人番号の記載が不要です。
なお、住所や受給者番号には、源泉徴収票の作成日時点の情報を記載します。
住所又は居所:神奈川県横浜市〇〇区◇◇1ー1
受給者番号:100001
個人番号:ー
役職名:主任
氏名:山田□□
支払金額
対象者の情報の下に、左から「種別」や「支払金額」を記載します。
種別とは、給与・賞与・財形給付金など、従業員に支払った金額の種類のことです。役員に対して支払う場合は、報酬と記載することもあります。
支払金額とは、1年間に支払われる総額のことです。一般的に、額面の年収を記載します。通勤手当や旅費交通費のうち、非課税相当額については支払金額には含まれません。
1年間で従業員に支払った給与と賞与の合計額が550万円の場合、以下のように記載します。
種別:給与・賞与
支払金額:5,500,000(円)
給与所得控除後の金額
「支払金額」の右隣には、「給与所得控除後の金額(調整控除後)」を記載します。対象者の給与収入などの合計額から給与所得控除額や所得金額調整控除額を引いて、給与所得控除後の金額(調整控除後)を計算しましょう。
給与所得控除とは、源泉徴収票の支払金額に応じて決まる制度を指します。また、所得金額調整控除とは、本人・配偶者・扶養親族が特別障害者に該当する場合や、給与所得と年金所得の両方がある場合に控除できる可能性がある制度です。
2024年4月1日時点における源泉徴収票の支払金額と給与所得控除の額の対照表をまとめました。
| 源泉徴収票の支払金額 | 給与所得控除額 |
| 〜1,625,000円 | 550,000円 |
| 1,625,001円〜1,800,000円 | 支払金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001円〜3,600,000円 | 支払金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円〜6,600,000円 | 支払金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円〜8,500,000円 | 支払金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円〜 | 1,950,000円(上限) |
支払金額が550万円の場合、給与所得控除額は154万円です。そのため、源泉徴収票には以下のように記載します。
給与所得控除後の金額(調整控除後):3,960,000(円)
なお、令和7年度税制改正の大綱では、「給与所得控除について55万円の最低保障額を65万円に引き上げる」方針が示されています。そのため、計算する際は必ず最新の情報を確認しましょう。
参考:国税庁「No.1410 給与所得控除」、財務省「令和7年度税制改正の大綱(1/9)」
所得控除の額の合計額
「給与所得控除後の金額(調整控除後)」の右隣には、「所得控除の額の合計額」を記載します。
所得控除とは、要件を満たす場合に所得合計から一定の額を引ける制度のことです。以下15種類の所得控除があります。このうち、年末調整で適用できないのは、雑損控除、医療費控除、寄附金控除です。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
従業員によって、適用できる所得控除が異なるため注意しましょう。基礎控除のみ、一定の所得を越えない限り誰でも適用できます。
2024年度において、基礎控除(48万円)・配偶者控除(38万円)・扶養控除(38万円)を適用する場合の記入例は、以下のとおりです。
所得控除の額の合計額:1,240,000(円)
源泉徴収税額
「所得控除の額の合計額」の右隣には、「源泉徴収税額」を記載しましょう。源泉徴収税額とは、事業者が従業員から天引きで1年間に徴収した所得税額を指します。
所得税額の計算式は、「課税所得 × 所得税率 − 控除額」です。源泉徴収税額の詳しい計算方法については、後ほど解説します。
源泉徴収税額:178,100(円)
控除対象配偶者の有無
「種別」や「支払金額」などの下の段には、「(源泉)控除対象配偶者の有無等」を記載します。該当する場合は、「有」「従有」のいずれかの下に「◯」を記載しましょう。
主たる給与で年末調整を実施していて対象の従業員に控除対象配偶者がいるときや、年末調整を実施しておらず対象の従業員に源泉控除対象配偶者がいるときに、「有」の下に丸をつけます。一方、「従有」の下に丸をつけるのは、従たる給与で従業員に源泉控除対象配偶者がいるときです。
控除対象配偶者に該当するか源泉控除対象配偶者に該当するかは、対象者自身の所得や配偶者の所得によって異なります。また、主たる給与は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している従業員に支払う給与、従たる給与はそれ以外の従業員に支払う給与のことです。
控除対象配偶者が老人控除配偶者である場合は、「有」もしくは「従有」に加えて「老人」の下にも「◯」を記載しましょう。
さらに、「(源泉)控除対象配偶者の有無等」の右隣には、配偶者控除もしくは配偶者特別控除の額の記載も必要です。配偶者特別控除は、配偶者控除の要件を満たさない場合に適用できる可能性があります。
主たる給与で年末調整を実施しており、対象の従業員に配偶者控除の対象となる配偶者がいる場合の記入例は、以下のとおりです。
(源泉)控除対象配偶者の有無等 有:◯
配偶者(特別)控除の額:380,000(円)
控除対象扶養親族の数
「(源泉)控除対象配偶者の有無等」の右隣には、「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)」を記載します。扶養親族とは、従業員の配偶者以外の6親等内の血族・3親等内の姻族や都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人などの要件を満たす人のことです。
「特定」には特定扶養親族の人数、「老人」には老人扶養親族の人数、「その他」には「特定」や「老人」に記載していない控除対象扶養親族の人数を記載します。「従たる給与についての扶養控除等申告書」を従業員が提出している場合には、対象箇所の「従人」欄への記載が必要です。
一般の控除対象扶養親族が1人いる場合は、以下のように記載します。
控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)
その他:1人
なお、従業員の親族に対象者がいる場合は、「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)」の右隣の「16歳未満扶養親族の数」「障害者の数(本人を除く)」「非居住者である親族の数」にも人数の記載が必要です。
社会保険料等の金額
「(源泉)控除対象配偶者の有無等」や「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)」などの下の欄左側には、「社会保険料等の金額」を記載します。社会保険料とは、事業者や従業員が納付する健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・労災保険料・雇用保険料のことです。
「社会保険料等の金額」には、従業員から天引きした健康保険料や厚生年金保険料などと、小規模企業共済等掛金の合計額を記載します。
天引きした健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の合計額が85万円の場合、記入例は以下のとおりです。
社会保険料等の金額:850,000(円)
生命保険料の控除額・地震保険料の控除額
「社会保険料等の金額」の右側に、「生命保険料の控除額」と「地震保険料の控除額」を記載します。記載するのは、年末調整時に従業員が提出する「給与所得者の保険料控除の申告」に基づく金額です。
生命保険料控除が3万円、地震保険料控除が2万円の場合は以下のように記載します。
生命保険料の控除額:30,000(円)
地震保険料控除の控除額:20,000(円)
なお、生命保険料については、「(摘要)」の下にある「生命保険料の金額の内訳」(新生命保険料の金額・旧生命保険料の金額・介護医療保険料の金額・新個人年金保険料の金額・旧個人年金保険料の金額)にもそれぞれ記載が必要です。
住宅借入金等控除の額
「地震保険料の控除額」の右隣には、「住宅借入金等控除の額」を記載します。
住宅借入金等控除とは、従業員が住宅ローンなどを利用して家を購入したり建てたりした際に、要件を満たすと年末残高に応じて一定額を所得税額から控除できる制度です。年末調整時に従業員が提出する「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に基づき、「住宅借入金等控除の額」の欄に金額を記載します。
また、「生命保険料の金額の内訳」欄の下にある「住宅借入金等特別控除の額の内訳」にも記載が必要です。
「住宅借入金等特別控除の額の内訳」の「居住開始年月日(1回目、2回目)」には和暦で従業員が居住を開始した日付を記載し、「住宅借入金等特別控除区分(1回目、2回目)」は一般の住宅借入金等特別控除の場合に「住」と記載します。
従業員が住宅ローンを利用し、物件を購入(2023年10月1日入居)した場合の記入例が以下のとおりです。
住宅借入金等控除の額:50,000(円)
住宅借入金等特別控除適用数:1
居住開始年月日(1回目):R5(年)10(月)1(日)
住宅借入金等特別控除区分(1回目):住
住宅借入金等年末残高(1回目):9,000,000(円)
住宅借入金等特別控除可能額:63,000(円)
控除対象者の氏名
「住宅借入金等特別控除の額の内訳」の下には、控除対象者の氏名などを記載します。従業員に控除対象の配偶者がいる場合は、「(源泉・特別)控除対象配偶者」「配偶者の合計所得」「国民年金保険料等の金額」「旧長期損害保険料の金額」「基礎控除の額」「所得金額調整控除額」の欄に必要事項を記載しましょう。
また、扶養親族がいる場合は「控除対象扶養親族」の欄、16歳未満の扶養親族がいる場合は「16歳未満の扶養親族」の欄にも記載が必要です。それぞれ「区分」の欄は、該当する人物が非居住者である場合にのみ使用します。
さらに、「控除対象扶養親族」「16歳未満の扶養親族」の欄の下にある「未成年者」から「勤労学生」は、従業員本人や親族が該当する場合に「◯」を記載する欄です。その右側の「中途就・退職」欄には、従業員が年の途中で就職や退職をした場合に「◯」や就職(退職)の年月日を記載します。
「中途就・退職」欄の右にある「受給者生年月日」は、従業員の生年月日を元号で記載する欄です。
支払者の情報
源泉徴収票の一番下にある「支払者」の欄は、支払者(事業者)に関する情報を記載する場所です。
最初に、右詰でマイナンバーもしくは法人番号を記載しましょう。その下に住所・所在地、さらにその下に氏名・名称や電話番号を記載します。
なお、従業員に交付する源泉徴収票については、マイナンバーもしくは法人番号の記載が不要です。
源泉徴収税額を計算する際の流れ
源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、1年間に事業者が従業員から天引きで徴収した税額を記載します。計算で税額を把握したい場合は、以下の流れで進めましょう。
- 課税所得を計算する
- 所定の税率をかけて税額を計算する
従業員の年収(支払金額)が550万円、所得控除合計が124万円のケースで源泉徴収税額の計算方法を解説します。
課税所得を計算する
源泉徴収税額を計算するには、課税所得を把握しなければなりません。
今回、給与所得控除額は154万円(550万円 × 20% + 44万円)のため、給与所得は396万円(550万円 − 154万円)です。また、給与所得から所得控除合計(124万円)を引けば、従業員の課税所得額を272万円(396万円 − 124万円)と計算できます。
所定の税率をかけて税額を計算する
計算した課税所得に所定の税率をかけて、源泉徴収税額を計算しましょう。
課税所得が272万円(195万円〜329万円)の場合、所得税率は10%、控除額は9.75万円です。そのため、所得税額は17.45万円(272万円 × 10% − 9.75万円)と計算できます。ただし、2037年までは復興特別所得税として基準所得税額の2.1%(今回のケースでは約0.36万円)の納付も必要です。
なお、上記のような計算をしなくても国税庁の「源泉徴収税額表」を使えば源泉徴収する際の税額を手軽に求められます。
参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」、「令和7年分 源泉徴収税額表」
源泉徴収票を作成する際に気をつけること
源泉徴収票を作成する際は、以下の点に気をつけましょう。
- 記入漏れ・計算ミスを防ぐ
- 所得控除の額を間違えない
- 法改正の確認を怠らない
それぞれ詳しく解説します。
記入漏れ・計算ミスを防ぐ
源泉徴収票を作成する際は、記入漏れや金額の計算ミスなどがないように細心の注意を払いましょう。
万が一ミスがあると、やり直しをする際に余計な労力や時間をかけることになります。また、記載金額に誤りがあると、従業員が源泉徴収票を添付して住宅ローンなどを申し込む際にも支障をきたすでしょう。
記入漏れや計算ミスを防ぐためには、担当者限りにせず上司が入念なチェックをすることが大切です。
所得控除の額を間違えない
所得控除の額を間違えないようにすることも、源泉徴収票を作成する上で大切です。所得控除の額は、所得控除の種類や本人の合計所得金額などによって異なります。
たとえば、2024年4月1日時点で合計所得金額が900万円以下で一般の控除対象配偶者がいる場合、適用できる所得控除(配偶者控除)の額は38万円です。それに対し、本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の所得が95万円超100万円以下の場合は、36万円の所得控除(配偶者特別控除)を適用します。
所得控除の額を間違えないためにも、従業員が所得控除の要件を満たしているか、その額は間違えないかなどを確認しましょう。
法改正の確認を怠らない
法改正の確認を怠らないことも、源泉徴収票を作成する際に心がけましょう。なぜなら、法改正によって所得控除の額が変わることがあるためです。
「令和7年度税制改正の大綱」には、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引き上げることに加え、合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額を10万円引き上げることなども盛り込まれています。そのため、今までの数字で計算して間違えることがないように、常に最新の情報を理解することが重要です。
源泉徴収票をスムーズに作成するためのコツ
源泉徴収票をスムーズに作成するためのコツは、給与計算システムや経理ソフトなどを導入することです。システムやソフトを自社に導入すれば、入力が必要な箇所を把握して記入漏れを防いだり、最新の適切な控除額を把握したりしやすくなるでしょう。
給与計算業務に限らず、経費精算業務もシステムを導入した方がスムーズにできる場合があります。
まとめ
年末調整を実施したタイミング、従業員が退職したタイミングなどで、事業者は源泉徴収票を発行します。そのため、経理担当者や人事担当者らは、源泉徴収票の書き方をあらかじめ理解しておかなければなりません。
手元に書式がない場合は、国税庁のサイトからフォーマットをダウンロードし、従業員の支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・源泉徴収税額などを記載しましょう。作成する際は、記載漏れや計算漏れがないようにすることが大切です。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。