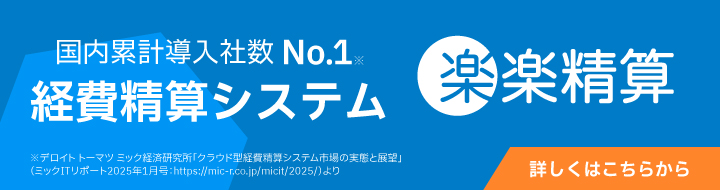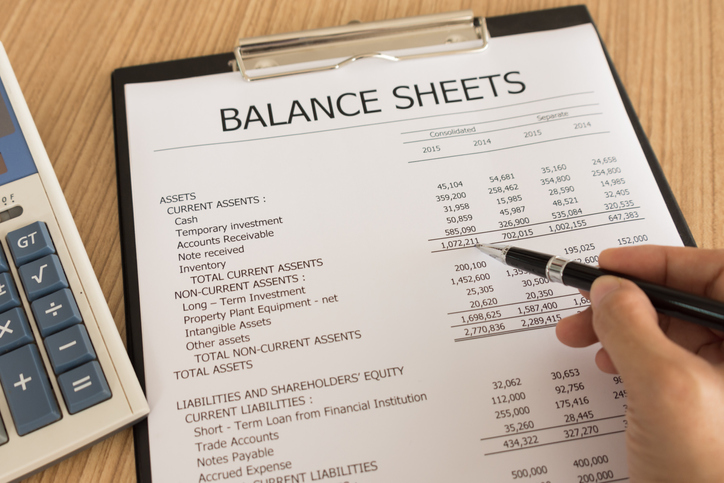損益計算書の勘定科目とは?作り方と注意点【テンプレート付き】

経理部門に従事している人にとって、損益計算書の勘定科目は毎日目にする言葉としてずっと付き合っていく存在です。勘定科目を理解すれば、「企業の成績表」を読み取れるようになりますので、経理に従事する者として重要かつ基本的な事項です。
この記事では、損益計算書の勘定科目の基本から、具体的な計上例までを簡潔に解説します。この機会に経理のプロフェッショナルとして、身に着けておきましょう。
経理プラス:損益計算書(P/L)とは?分析・作成時のポイントや貸借対照表との違い
損益計算書(P/L)と勘定科目の基礎知識
損益計算書(Profit and Loss Statement、略してP/L)とは、収益、費用、利益を明確にして企業の経営成績を示すための重要な財務諸表です。このセクションでは、損益計算書の概要と、それに含まれる勘定科目について紹介します。
損益計算書とは?
損益計算書(P/L)は、企業における一定期間(1年間や1か月間、四半期等)の業績を表す書類です。大きくわけて、収益、費用、利益の3つから構成されています。
勘定科目とは?
勘定科目は、企業で取引が行われるごとに発生したお金を分類・記録するために用いられる区分です。正確な損益計算書の作成には、経理担当者がそれぞれの勘定科目の意味を理解することが重要です。
勘定科目には、貸借対照表(Balance sheet 略してBS)に表すための「貸借科目」と損益計算書に表すための「損益科目」の2種類があります。
- 貸借科目:資産(現預金、売掛金、固定資産)負債(未払金、買掛金、借入金)純資産(資本金など)であり、ある時点での会社の資産と負債・純資産のバランスを表すために用いられます。
- 損益科目:収益(売上高)、費用(売上原価、一般管理費)などの一定期間の企業の業績を表します。
このように、勘定科目は「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5つのグループに大別され、損益計算書には「収益」「費用」に属する勘定科目が記載されます。
収益科目には、売上高やサービス収入などが含まれ、費用科目には、仕入高や人件費、家賃、広告費などが含まれます。すべての取引を記録していけば、一定期間経過後に、企業の経済活動がどのように収益に貢献し、どのように費用として発生したのかが一目でわかるようになるのです。
主な勘定科目の一覧については以下の記事をご参照ください。
経理プラス:勘定科目とは?仕訳の分類で迷わない科目一覧表を紹介
損益計算書で用いられる勘定科目
損益計算書を作成するには、それぞれの勘定科目がどのような取引を表しているのかについての理解が必要です。ここでは、損益計算書に登場する主要な勘定科目について詳しく見ていきましょう。
売上高
売上高とは、商品の販売やサービスの提供から得た収益の合計を示します。
「収益」に分類される主要な勘定科目であり、売上高は企業の主要な収入源を反映します。
収益に属する勘定科目のなかには、業種によっていろいろなものがあり、呼び方も様々です。たとえば、製造業や小売業では「売上高」、ですが、建設業では「完成工事高」、医療では「外来(入院)診療収益」等という具合です。値引き、売上返品、売上割戻しなど、売上高から差し引かれる分を計上するための科目もあります。
売上原価
売上原価は商品の仕入れ・製造に対して発生した費用のことを指し、損益計算書の「費用の部」に計上されます。売上原価の範囲はサービス業、製造業、建設業などの業種によって異なるので注意が必要です。たとえば、サービス業においては基本的に「期首商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高」で売上原価を算出することができます。
一方、製造業や飲食業においては、製品につくるうえで必要な材料費、労務費、諸経費について原価として明瞭な「直接費(直接材料費、直接労務費、直接経費)」のほか、人件費や燃料代といった直接的にコストを把握できない費用「間接費(間接材料費、間接労務費、間接経費)」なども定められた方法で配分する必要があるのです。
販売費及び一般管理費
製品やサービスの販売・提供にかかる費用をまとめたものを「販売費」といいます。具体的には、販売員として働く従業員の給料やPRのための宣伝広告費、商品を輸送するための発送費・配達費などが該当します。
一方、一般管理費は企業運営にかかわる一般管理業務にかかる費用のことです。文房具やコピー費といった消耗品費から通信費のほか、事務所家賃や水道光熱費のうち原価に含まれないものも一般管理費に該当します。
営業外収益
営業外収益は、主要事業活動以外から得られる収入のうち、経常的な収入を指します。たとえば、小売業の企業が本業とは別に、駐車場や建物を所有しており、賃貸料の収入がある場合などです。
営業外費用
営業外費用は主要事業活動以外の用途で支払われる費用のうち、経常的な費用を指します。企業における例として最も一般的な営業外費用が、銀行等に支払っている借入金の利息です。
特別利益
特別利益は、通常の事業活動からは発生しない一時的な利益のことです。例としては、災害等に遭った際の受取保険金などです。施設の移転等のため土地や建物を売却した際に得られた利益も、ここに計上します。
特別損失
特別損失は、通常の事業活動からは発生しない一時的な損失のことです。例としては、災害等に遭って損壊した企業の建物や設備などの額です。施設の移転等のため土地や建物を売却した際、もし損失が出たらここに計上します。
法人税等
法人税等には、会計期末で締め終わった後、納税額を計算し申告する額を計上します。法人税等は、「益金」といわれる課税されるべき収益から「損金」といわれる控除されるべき費用を差し引いた「課税所得」に税率を乗じて計算されます。
損益計算書の作り方と注意点【テンプレート付き】
損益計算書の作成は、企業の財務状態を理解し、投資家や関係者に報告するための重要なプロセスです。このセクションでは、損益計算書の作成方法と、作成時に留意すべき点について解説します。
損益計算書の作り方
損益計算書を作成する方法としては、下記のような方法があります。四半期・毎期に開示するために作成することになると思いますので、担当者として最も効率の良い方法で作成しましょう。
- テンプレートを利用する
- 表計算ソフトを利用する
- 会計ソフトを利用する
- 税理士に依頼する
テンプレートを利用する
仕訳数が少なく、内容が簡単な場合に適した方法です。あらかじめ用意したテンプレートに算出した数字を記入していけば完成します。テンプレートはネット上からダウンロードできるので利用するとよいでしょう。
表計算ソフトを利用する
テンプレートが自社に合わない場合や、独自の表し方がある場合などは、基本的な方針を守りつつ独自に表計算ソフトを用いて作成する方法があります。
会計ソフトを利用する
一般の企業の場合、この方法が多いと思われます。各種会計ソフトを使用したり、クラウド会計ソフトを利用したりすることで、自動的に損益計算書を生成することができます。
税理士に依頼する
頻繁な税制改正により、決算時だけではなく日常の取引の一つ一つについて素人では不明なことが増えてきています。些細な間違いの積み重ねが起こらないよう、月次決算の段階から税理士に依頼するケースも少なくありません。
損益計算書のテンプレート
損益計算書のテンプレートは経理プラスのサイトからダウンロードできます。以下のリンクをクリックしてください。
経理プラス:【ビジネス書式テンプレート】損益計算書
損益計算書を作るときの勘定科目に関する注意点
損益計算書を作る際、テンプレートを使うと簡単ですが、気を付けるべき点があります。ここでは3点ほど解説します。
勘定科目は会社により異なる場合がある
勘定科目は一般的によく使われる種類があり、基本的にはそれらをそのまま使いますが、法律で厳密に決められているわけではありません。すなわち、売上、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外損益等の区分がしっかりしていれば、中身は自由に決めてもよいのです。
たとえば、DXでこれまでになかったようなサービスが登場し、当てはまる勘定科目がないなどの場合、「AI利用料」などのような勘定科目を新たに作っても問題ありません。会社の業績を表して経営管理するのが目的ですので、多すぎず少なすぎない程度で管理に適した科目を設定してください。
1度決めた勘定科目を変更しない
会社の業績は、銀行や取引先、行政当局等に開示するのを原則とします。一定の決まりに従って誰が見ても理解できる損益計算書でなくてはなりません。
「会計原則」のなかに「継続性の原則」というものがあります。よほどのことがない限り一度決めたら同じ方法で会計し続けなければならないという原則です。昨年と今年で仕訳した科目が違えば、昨年と比較ができず、業績の変化がわからなくなる恐れがあるからです。
勘定科目を「報告用」と「仕訳用」に分類する
内部管理用(仕訳用)と外部報告用(報告用)の勘定科目を明確にわけることで、より効率的な財務管理が可能になります。月次で業績を管理する場合などでは社内で分かりやすいように仕訳用で作成します。
また、年に一度、行政当局から損益計算書の提出を求められるようなケースでは仕訳用に作成した損益計算書を報告用に直す作業が簡単にできるように整備しておきます。
損益計算書の書き方については以下の記事をご参照ください。
経理プラス:損益計算書の書き方は?作り方と手順、注意点【テンプレート付き】
まとめ
損益計算書と勘定科目についての知識は、経理担当者として最も中心的な知識であるといっていいでしょう。毎月の仕事のなかで自然と身についていくものと思いますが、会計原則の話など、学術的な知識も持ったうえで業務に当たれば、より知識が自分のものになると思います。
これらは、企業が業績を管理して意思決定を行うのに不可欠なプロセスですので、日々損益計算書と勘定科目にかかわっていくことで、経営に不可欠なスキルとしてより深い知識を身に着けてください。
損益計算書と勘定科目に関するQ&A
損益計算書と勘定科目に関して、よくある質問と回答を書いてみましたので参考にしてください。
Q1. 損益計算書に勘定科目を使う理由は?
A:損益計算書は決算書として作成する財務諸表の一部です。決算書類を作成するには必ず仕訳をしていく必要があります。仕訳とは借方(左)、貸方(右)が同じ金額になるよう勘定科目に振り分けていく作業です。
一定の決まりに従って仕訳をしますので、同じ方法による決算になり、昨年との比較が可能になります。したがってお金の流れは把握しやすくなるのです。
Q2. 損益計算書にはどのような種類がありますか?
A:損益計算書には、勘定式と報告式の二種類があり、一般的に報告式が採用されることが多いです。勘定式は、収益と費用を左右にわけて表示します。左側に費用、右側に収益が表示されます。一方、報告式は、企業の決算発表などで見られる形式で、上から下に一列で表示されます。
Q3. 損益計算書はいつまでに作る必要がありますか?
A:税務申告や行政への届け出を目的とする損益計算書は、会計年度の最終日から2か月以内に作成するのが一般的です。たとえば3月31日が決算日であれば、5月31日までに申告が済んでいなければなりませんので、決算後1か月中に決算を終えて作成するのが一般的でしょう。
また、経営管理のための月次決算や、株主に報告するための損益計算書は、できるだけ早期に作成し、いち早く経営層や株主に提示する必要があります。また、上場企業の場合、株主に提示する株主総会は、3か月以内となります。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。