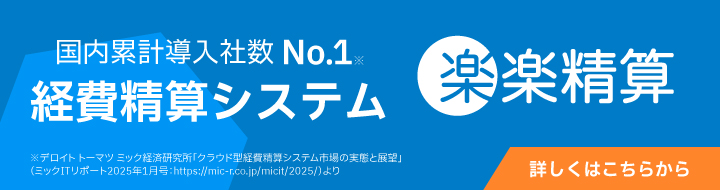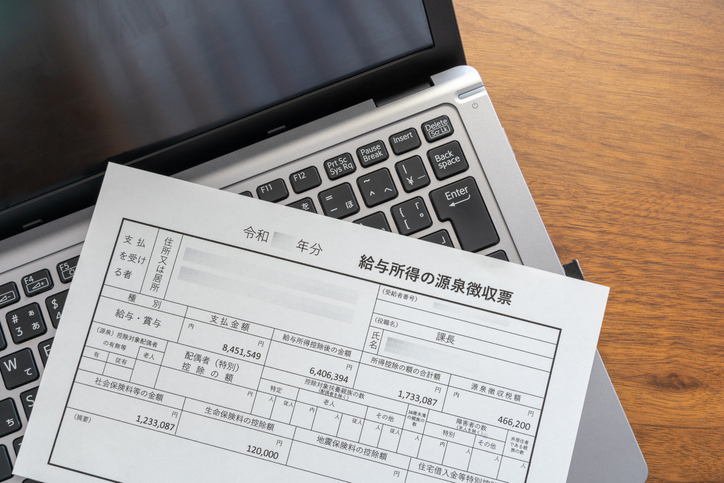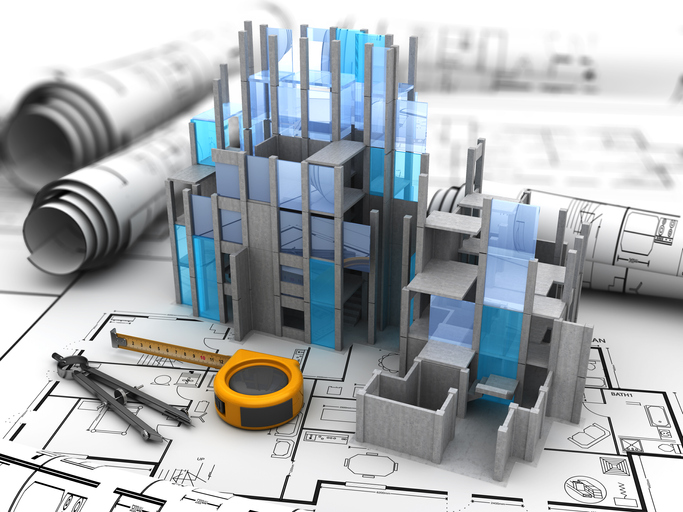消費税を仕訳する際の勘定科目とは?経理方式の選択法や注意点も解説

消費税を仕訳する際に使用する勘定科目は、「租税公課」「仮払消費税」「仮受消費税」「未払消費税等」「未収消費税等」の5種類です。さらに、仕訳方法は「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類があります。
本記事では、消費税を仕訳する際に用いる勘定科目について、それぞれどのようなケースで使用するのかを詳しく解説します。また、消費税の仕訳方法や計算方法についても、各方法の特徴やどのような場合に使うのかをお伝えするほか、ケース別の消費税の仕訳例もご紹介しますのでぜひ参考にしてください。
消費税を仕訳する際の5種類の勘定科目
消費税を仕訳する際に使用する勘定科目は、以下の5つです。
- 租税公課
- 仮払消費税
- 仮受消費税
- 未払消費税等
- 未収消費税等
それぞれの勘定科目の内容と、どのような場合に使用するのかについて解説します。
租税公課
租税公課とは、国や地方自治体に納める税金をあらわす「租税」と、国や地方公共団体等に納める会費・罰金等の「公課」を組み合わせた言葉です。消費税は、国や地方自治体に納める税金の一種であるため租税に該当します。
そのため、勘定科目としても租税公課を使用します。ただし、勘定科目として使用できるのは、仕訳時に使用する経理方式で「税込経理方式」を用いた場合のみです。
固定資産税や自動車税などは、勘定科目に租税公課を使いますが、すべての税金で租税公課を使用するわけではありません。たとえば、法人税や住民税、事業税などの所得に関する税金は、勘定科目に租税公課を使わないことを知っておきましょう。
参考:国税庁「租税公課」
仮払消費税
仮払消費税は、「税抜経理方式」で仕訳処理をする際に使う勘定科目です。税抜経理方式とは、仕入先に支払った代金や顧客から受け取った売上金などを、消費税と本体価格に分けて経理処理する方法です。
仕入れや経費が発生する取引における仕訳で、すでに支払った消費税を仮払消費税として取り扱います。
参考:国税庁「No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理」
仮受消費税
仮受消費税とは、税抜経理方式で仕訳を行う際に、受領した消費税を計上するための勘定科目です。税抜経理方式では、商品を売り上げた際に、その一部は消費税であるため確定申告で納税する必要があります。
なお、税込経理方式では、勘定科目として仮受消費税は使用せず、消費税額は売上に含めます。
参考:国税庁「No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理」
未払消費税等
未払消費税等は、決算時に仮払消費税と仮受消費税を相殺した際に、支払わなければならない消費税がある場合に計上する勘定科目です。基本的には、預かった消費税額が支払った消費税額よりも多い場合に使用します。
仮払消費税や仮受消費税が税抜経理方式でのみ使用する勘定科目であるのに対して、未払消費税等は、税込経理方式でも税抜経理方式でも使われることがポイントです。
未収消費税等
未収消費税等は、仮払消費税と仮受消費税の相殺時に、還付する消費税がある場合に計上する勘定科目です。
仮受消費税よりも仮払消費税の方が大きい場合があり、その差額は税務署から還付されます。この還付される予定の消費税を、「未収消費税等」として資産計上します。未払消費税等は、税込経理方式でも使われる勘定科目です。
関連記事:勘定科目の一覧と具体的な仕訳例|方法や注意点を解説
消費税の2種類の仕訳方法
消費税には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類の仕訳方法があります。処理に手間がかかるか否かや自社の事業規模、業種などを踏まえて、自社にあった方法を選択することが一般的です。
仕訳方法によって使用する消費税の勘定科目が異なるため、両者の特徴を理解することが大切です。それぞれの特徴やメリット、デメリットを解説します。
税込経理方式
税込経理方式とは、仕入時や売上時などに、商品やサービスの価格と消費税を合わせた金額で記帳する方法のことです。商品を売り上げた際に発生した消費税額は「売上」に、仕入れる際に発生した消費税額は「仕入」に含めて計上することがポイントです。
取引ごとに消費税を抜き出さずに仕訳ができるため、経理処理に不慣れでも対応しやすい点がメリットといえるでしょう。一方で、複数税率において10%の取引と8%の取引が混在しているようなケースでは、どの取引がどの税率に該当するのかを判断するのが困難になる点がデメリットです。
税込経理方式は、会計の知識が少なくても簡単に記帳できることから、中小企業で採用される傾向にあります。
税抜経理方式
税抜経理方式とは、消費税と本体価格を切り分けて計上する方法であり、売上や仕入れには消費税は含まれないことが特徴です。消費税を計上する勘定科目には、「仮払消費税」「仮受消費税」などを使います。
税抜経理方式は、消費税額が可視化されるため期中でも納税額を把握しやすく、支払税額を準備しやすい点や、税率改正時もスムーズに修正できる点などがメリットです。ただし、会計処理の手間がかかる点に注意しましょう。
設備投資による減価償却費や接待・交際費などの支出が多く、消費税の控除対象外となる項目の管理が必要な大企業は、対象となる取引の税額を明確に分けられる税抜経理方式を採用するケースが多くみられます。
各企業は、税込経理方式と税抜経理方式から、仕訳方法を任意で選択できます。ただし原則として、すべての取引において同じ方式で統一しなければなりません。
【課税方式別】選択できる経理方式
事業者が消費税を納める際に選択できる計算方法は、以下の3種類です。
- 本則課税
- 簡易課税
- インボイス制度の2割特例適用
それぞれの方法の特徴や、使用できるケースなどを解説します。
本則課税の場合
本則課税とは、売上にかかる消費税額から、仕入れや経費で支払った消費税額を差し引いて納税額を計算する方法で、誰でも選択できることが特徴です。
本則課税の計算式は、以下のとおりです。
本則課税で消費税の計算をする場合は、売上高と消費税額を明確に分ける税抜経理方式が適しています。
簡易課税の場合
簡易課税とは、売上にかかる消費税額に、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を適用して、仕入れにかかる消費税額を簡易的に計算する方法です。簡易課税を選択できるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税事業者のみである点を押さえておきましょう。
簡易課税の計算式は、以下のとおりです。
簡易課税方式のメリットは、会計処理の手間がかからない点といえるでしょう。仕入れ等にかかる経費を算出しなくてよいことから、税込経理方式での仕訳が向いています。
インボイス制度の2割特例適用の場合
インボイス制度の2割特例は、インボイス制度の導入に伴い、免税事業者から課税事業者となった小規模事業者を対象にした特例措置です。2023年10月1日から2026年9月30日までの間、免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合に適用される特例措置です。
インボイス制度の2割特例を適用すると、納税額は、課税売上高にかかる消費税のうち8割を控除した残りの金額となります。
計算式は以下のとおりです。
インボイス制度の2割特例については、税込経理方式と税抜経理方式のどちらも選択できます。そのため、会計処理の簡素化を希望する場合は税込経理方式、消費税の納税額を可視化したい場合は税抜経理方式がおすすめです。
インボイス制度の2割特例が適用されるのは2026年9月30日まで、それ以降の2029年9月30日までの期間は5割控除となり、2029年10月1日以降は経過措置が終了します。そのため、本則課税または簡易課税のどちらかに移行しなければなりません。
参考:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
【ケース別】消費税の仕訳例
ここからは、以下のケースにおける消費税の仕訳をご紹介します。
- 商品を仕入れたとき・売り上げたとき
- 返品や値引きがあったとき
- 決算のとき
- 消費税を納税するとき
それぞれの仕訳内容を確認しましょう。
商品を仕入れたとき・売り上げたとき
消費税10%の場合、11,000円の商品を仕入れたときと売り上げたときの仕訳は、以下をご確認ください。
税込経理方式では、売上や仕入れの金額に消費税を加えて計上します。
【税込経理方式:仕入れ】
| 借方 | 貸方 | ||
| 仕入高 | 11,000円 | 買掛金 | 11,000円 |
【税込経理方式:売上】
| 借方 | 貸方 | ||
| 売掛金 | 11,000円 | 売上高 | 11,000円 |
税抜経理方式では、仮払消費税や仮受消費税の勘定科目を使用して会計処理を行います。
【税抜経理方式:仕入れ】
| 借方 | 貸方 | ||
| 仕入高 | 10,000円 | 買掛金 | 11,000円 |
| 仮払消費税 | 1,000円 | ||
【税抜経理方式:売上】
| 借方 | 貸方 | ||
| 売掛金 | 11,000円 | 売上高 | 10,000円 |
| 仮受消費税 | 1,000円 | ||
返品や値引きがあったとき
消費税が10%の場合の、返品や値引きの仕訳もみていきましょう。11,000円の商品の返品を受けたときは、以下のように仕訳を行います。
【税込経理方式:返品・値引き】
| 借方 | 貸方 | ||
| 売上高 | 11,000円 | 売掛金 | 11,000円 |
【税抜経理方式:返品・値引き】
| 借方 | 貸方 | ||
| 売上高 | 10,000円 | 売掛金 | 11,000円 |
| 仮受消費税 | 1,000円 | ||
決算のとき
消費税は、決算時に金額を確定した後に納付します。
税込経理方式の場合、消費税は租税公課の勘定科目を使用して会計処理を行いましょう。納税すべき消費税額が確定しても、実際に消費税を納めているわけではないため、租税公課の相手科目には未払消費税等を用います。
納税予定の消費税額が1,000円の場合、仕訳は以下のとおりです。
【税込経理方式:税金の計上】
| 借方 | 貸方 | ||
| 租税公課 | 1,000円 | 未払消費税等 | 1,000円 |
税抜経理方式では、決算で仮受消費税と仮払消費税を処理します。それぞれの金額の差額は未払消費税として計上することがポイントです。
【税抜経理方式:税金の計上】
| 借方 | 貸方 | ||
| 仮受消費税 | 2,000円 | 仮払消費税 | 1,000円 |
| 未払消費税等 | 1,000円 | ||
消費税を納税するとき
消費税を納税するときは、決算で発生した未払消費税を消し込む処理を行います。仕訳例は、以下をご参照ください。
【税込経理方式:消費税の納税】
| 借方 | 貸方 | ||
| 未払消費税等 | 1,000円 | 現金 | 1,000円 |
【税抜経理方式:消費税の納税】
| 借方 | 貸方 | ||
| 未払消費税等 | 1,000円 | 現金 | 1,000円 |
消費税の仕訳における注意点
消費税の仕訳をする際は、以下の4点に注意しましょう。
- 消費税を経費計上できるのは租税公課を用いるときのみである
- インボイスとそれ以外は分けて処理する
- インボイス経過措置期間中の負担割合は時期によって変わる
- 税抜経理方式は処理に手間がかかる
それぞれの内容を解説します。
消費税を経費計上できるのは租税公課を用いるときのみである
消費税を経費計上できるのは、勘定科目に租税公課を用いるときのみです。消費税は、事業運営に欠かせない租税であるため、租税公課を使って経費計上できます。
ただし、消費税の勘定科目を租税公課と設定できるのは、税込経理方式で仕訳を行うケースに限られることに注意が必要です。
税抜経理方式の場合、売上にかかる消費税(仮受消費税)と、仕入れや経費にかかる消費税(仮払消費税)を分けて記録します。売上にかかる消費税(仮受消費税)は、事業者にとっては「預かったお金」または「一時的に支払ったお金」に過ぎず、最終的に税務署に納付するものです。そのため、経費として計上できないことを知っておきましょう。
インボイスとそれ以外は分けて処理する
消費税の仕訳では、インボイス(適格請求書)と、それ以外の普通の請求書は分けて処理する必要があります。インボイス制度では、適格請求書がないと消費税に仕入税額控除が適用されないためです。
さらに、10%と8%の税率が混在しているため、それぞれの税率別に会計処理を行わなければなりません。取引先の件数が多いほど会計処理業務が煩雑になりやすいことから、インボイス制度に対応した適切な消費税の会計処理を行うためには、前もって準備をしておくことが重要です。
インボイス経過措置期間中の負担割合は時期によって変わる
インボイス制度導入後、新たに課税事業者となった事業者の納税負担を軽減するために設けられた経過措置の負担割合は、時期によって変わることにも注意しましょう。
具体的には、インボイス制度が開始された2023年10月1日から3年間は、免税事業者等からの課税仕入れは80%の仕入額控除が認められています。さらに、2026年10月1日から3年間は、50%の仕入税額控除が認められることになりました。
なお、仕入税額控除の経過措置の適用を受けるためには、帳簿と要件を満たした請求書を保存していなければなりません。また、請求書には、経過措置の適用を受ける課税仕入れであることが明記されている必要があります。
税抜経理方式は処理に手間がかかる
税抜経理方式は、処理に手間がかかることも押さえておきましょう。税抜経理方式は、本体の価格と消費税を分けて会計処理を行うため、取引ごとに消費税額を計算して記帳しなければなりません。
税抜経理方式は消費税額が可視化されるため期中でも納税額を把握しやすい点がメリットである反面、処理に手間がかかる点がデメリットです。一方の税込経理方式は、消費税を含めた金額をそのまま用いて会計処理できるため、処理が複雑にならずに済みます。
さらに、複数税率が用いられていることから、税抜経理方式では消費税10%の取引と8%の取引に分けて会計処理を行わなければいけない点も、認識しておきましょう。
まとめ
消費税の仕訳を行う際には、「租税公課」「仮払消費税」「仮受消費税」「未払消費税等」「未収消費税等」の5種類の勘定科目を使用します。仕訳方法には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類が、計算方法には「本則課税」「簡易課税」「インボイス制度の2割特例適用」の3種類があります。
消費税の仕訳をミスなく行えるように、まずは5種類の勘定科目を把握しましょう。仕訳方法は、処理に手間がかかるかどうかや自社の事業規模、業種などを考慮して選択することが一般的といえるでしょう。
さらに計算方法については、本則課税は誰でも選択できますが、簡易課税は基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税事業者のみが使用できます。また、インボイス制度の2割特例は、免税事業者から課税事業者となった小規模事業者が対象です。
そのほか、消費税を経費計上できるのは租税公課を用いるときのみである、インボイスとそれ以外は分けて処理する、インボイス経過措置期間中の負担割合は時期によって変わる、税抜経理方式は処理に手間がかかるといった点にも注意しましょう。
消費税の処理はやや複雑ではあるものの、基本を押さえ、ルールに沿って対応すればスムーズに管理できます。消費税の仕訳を行う際の勘定科目や仕訳方法を正しく理解し、会計処理のミスを防ぎましょう。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。