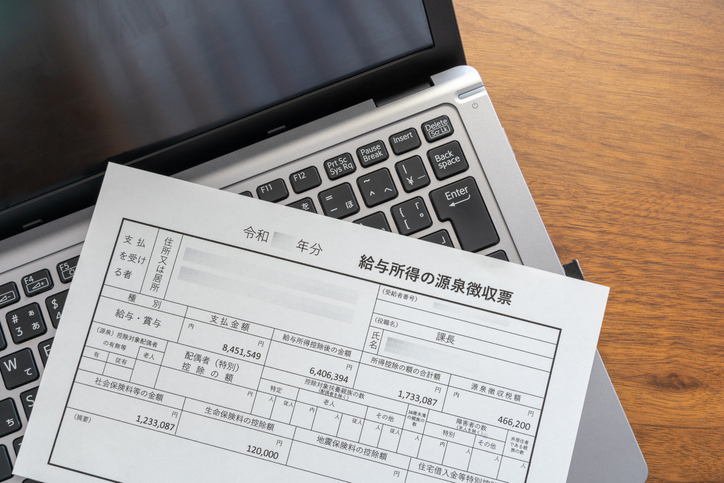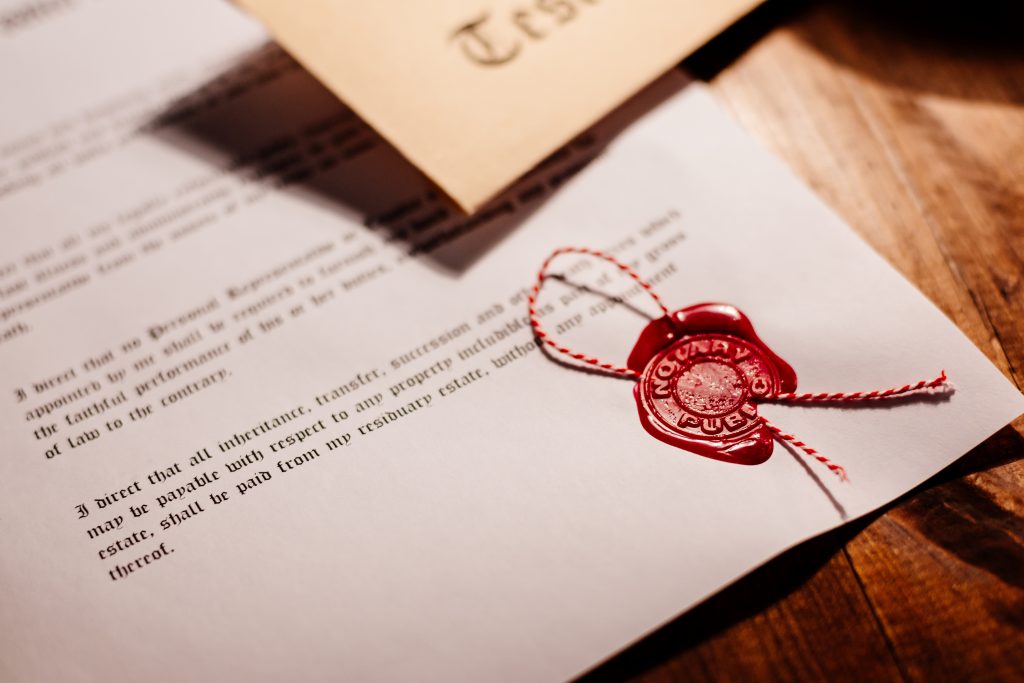【会計士監修】通勤手当は非課税になる?限度額や計算方法、交通費との違いを解説

業務上で発生する交通費は大きく次の2種類に分けられます。
- 役員や従業員の「通勤手当」
- 出張や移動などの「旅費交通費」
いずれも会社の経費となりますが、それぞれ課税上の注意点が存在します。ここでは交通費の中でも「通勤手当」の非課税限度額や社会保険料などについて詳しく解説します。
通勤手当は非課税?
交通費については、「通勤手当をいくら支給すればよいですか?」という質問がしばしば発生します。通勤手当は、あくまで会社が定める任意の金額で支給することが可能です。
従業員に支給される手当は、基本的に従業員個人に対する所得税の課税対象です。たとえば住居手当や残業手当、扶養手当など、全ての手当が課税対象となります。
しかし、通勤手当の場合、課税方法が他の手当と異なります。通勤手当は一定基準の範囲内であれば、所得税は非課税です。その理由は、通勤手当の性質が会社に出勤するための単なる実費の補てんであり、所得に馴染まないからです。
通勤手当と交通費との違い
通勤手当と間違えやすいものとして交通費があります。どのような違いがあるのか理解しておきましょう。
通勤手当
通勤手当とは、企業が従業員の通勤の費用を支給するものです。
労働基準法で定められているものではなく、支給の有無や金額、支給方法などは、会社ごとに異なります。詳しくは次の見出しで解説します。
交通費
交通費とは、従業員が営業先に行く際、また遠方に出張をする際などに発生する経費を指します。
従業員が一時的に支払い、後日経理や人事の担当者に領収書や交通費精算書を提出してもらい、精算するのが一般的な流れです。
通勤手当の計算方法
ここでは、多くの会社で採用されている通勤手当の計算方法を、3つの通勤手段別に解説します。
通勤手当の計算方法や支給額には、法律の規定がありません。一般的な計算方法を確認し、自社に合った方法を採用しましょう。
マイカーやバイクを利用する場合
マイカーやバイクを利用する場合は、通勤距離やガソリン単価を考慮して通勤手当を決定します。計算式の一例は、以下のとおりです。
仮に1kmあたりのガソリン単価が20円、通勤距離を片道10kmとすると、1日の通勤手当は400円です。
自転車を利用する場合
自転車を利用して通勤する場合、多くの会社では通勤距離が一定以上になったときに一定額を支給しています。具体的には、2kmを超えた場合に2,000円程度支給されるケースが多い傾向にあります。
自転車通勤をするのであれば、勤務先に駐輪スペースがある場合を除き、駐輪場を借りる必要があるでしょう。しかし、駐輪場の利用料は所得税非課税の対象にはなりません。
自転車通勤では、非課税で駐輪場代を支給するために、通勤手当の名目で一定額を支給すると考えてください。
公共交通機関を利用する場合
公共交通機関を利用する場合は、無駄がなく運賃が安いルートで通勤手当を計算します。支給方法は、以下のいずれかです。
- 「往復日額×出勤日数」
- 定期券
定期券は6か月で発行するケースが多いですが、利用する交通機関によっては、1か月または3か月定期券のみを取り扱っている場合もあります。電車やバスを利用した通勤手当を決定する際は、運賃を事前にシミュレーションし、より安い支給方法を選びましょう。
なお、リモートワークの導入により、郊外に居住し新幹線で通勤する方も増えています。新幹線通勤も、無駄がなく運賃が安いルートと認められれば、通勤手当の対象です。ただし、支給額が高額になるため、金額に上限を設けている会社もあります。
通勤手段別の非課税限度額を確認
先述のとおり、通勤手当の支給額や計算方法に法律の規定はないものの、通勤手当として所得税が非課税になる金額には上限があります。
ここからは、通勤手段別の非課税限度額を確認しましょう。
1.車両や自転車などの交通用具で通勤する人
車やバイク、原付、自転車は、通勤距離で非課税限度額が定められます。車であっても自転車であっても、非課税限度額が変わりません。そのため、不公平感はあるかも知れませんが、経理側としては覚えやすくてありがたい規定です。
なお、平成28年1月1日以後適用分の例では次のように定められています。
| 区分 | 課税されない金額 改正後(平成28年1月1日以後適用) |
|---|---|
| 通勤距離が片道2km未満である場合 | (全額課税) |
| 通勤距離が片道2km以上10km未満である場合 | 4,200円 |
| 通勤距離が片道10km以上15km未満である場合 | 7,100円 |
| 通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 | 12,900円 |
| 通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 | 18,700円 |
| 通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 | 24,400円 |
| 通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 | 28,000円 |
| 通勤距離が片道55km以上である場合 | 31,600円 |
区分や金額は更新される可能性があるため、適用する際は、必ず国税庁のホームページ等で最新の非課税限度額を確認しましょう。
参考:国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
車の場合、2点補足があります。
駐車場代を負担するかどうかは会社の自由
会社に駐車場がない場合、近隣の月極駐車場を利用することがあるでしょう。この駐車場料金を会社が負担するかどうかは、会社の自由です。ただし負担する場合は全額課税となりますので、非課税の通勤手当に含めることはできません。
有料道路の通行料金は非課税限度額に上乗せできる
2点目は有料道路を使用する場合です。通勤途中に有料道路を使用する際は、距離に応じた非課税限度額に有料道路の通行料金を合計した金額が非課税限度額となります。たとえば片道の通勤距離が60㎞で、うち30㎞が有料道路(通行料が1か月あたり5,000円)の場合、
31,600円(55km以上の非課税限度額)+5,000円=36,600円
となり、36,600円が非課税限度額です。ただし、1か月で15万円が上限となります。
関連記事:車通勤の交通費精算方法は?非課税限度額などの注意点を解説
2.公共交通機関を使って通勤する人
公共交通期間を用いて通勤する場合、運賃全額が非課税となります。ただし、上限金額は、1か月15万円です。運賃について、国税庁の通達では「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合」としています。そのため、通常の新幹線の場合は上限に収まっていれば非課税扱いとなりますが、グリーン車の利用料金は交通費とはいえ非課税とならない点に注意が必用です。
また、公共交通機関を使い実費精算を行っている場合は、毎回の申請が煩雑になりがちです。Suica®やPASMO®を使い効率的に申請する方法もありますので、併せてご覧ください。
関連記事:Suica®やPASMO®の履歴印字や請求書発行の手順と交通費精算の効率化について
3.複数の交通手段を使い通勤する人
たとえば、自宅から2㎞以上離れた最寄り駅まで自転車で行き、電車に乗る場合などが該当します。非課税限度額は前述した1・2の合計で、1か月15万円が上限です。
一方で徒歩通勤者に通勤手当を支給している場合は、当該通勤手当は課税対象となります。
課税通勤手当は毎月の給与計算・年末調整で給与に含める
課税通勤手当を支給した場合は所得税を課税するため、毎月の給与計算および年末調整で給与に含める必要があります。
給与計算ソフトを使用して課税・非課税を分離していると自動計算してくれるため、交通費の計算に間違いは起きにくいでしょう。ただし、もし手書きの給与明細書や社内で作成したエクセルなどで対応している場合は注意が必要です。毎月の給与明細上で、通勤手当の課税と非課税を確実に分けて記録しておきましょう。
通勤手当にかかる消費税は?
消費税の納税義務者である会社の場合、通勤手当が課税仕入となるか、非課税仕入となるかを迷うかもしれません。この点について、消費税法基本通達11-2-2によれば、通勤手当のうち通勤に通常必要であると認められる部分の金額は課税仕入れに係る支払対価として取り扱うとあることから、基本的に通勤手当は全額課税仕入れとなります。
個別対応方式における仕入税額控除の区分は、その従業員が課税売上にのみ貢献している場合を除き、共通課税仕入で処理することが一般的です。
通勤手当の具体例
それでは、いくつか具体例を挙げながら交通費に伴う通勤手当について見ていきましょう。
<パターン①:徒歩+電車>
- 条件
自宅~最寄りのA駅:徒歩
A駅~B駅:電車(1月の定期券代10,000円)
B駅~会社:徒歩
通勤手当10,000円支給 - 課税・非課税の別
課税通勤手当:0円
非課税通勤手当:10,000円 - 仕訳
借方 金額 貸方 金額 旅費交通費 10,000円 現金預金 10,000円
<パターン②:車+有料道路あり>
- 条件
自宅~会社:車30㎞(非課税限度額は、18,700円)
有料道路:1,000円
通勤手当:20,000円支給 - 課税・非課税の別
課税通勤手当:300円
非課税通勤手当:19,700円 - 仕訳
借方 金額 貸方 金額 旅費交通費 20,000円 現金預金 20,000円
<パターン③:2㎞未満>
- 条件
自宅~会社:車1.8㎞
通勤手当:2,000円 - 課税・非課税の別
課税通勤手当:2,000円
非課税通勤手当:0円 - 仕訳
借方 金額 貸方 金額 旅費交通費 2,000円 現金預金 2,000円
仕訳で非課税・課税に分ける必要はありません。エクセルで給与計算を行う会社の場合は、補助科目で課税・非課税を分けておくと、年末調整の際に残高試算表で付け合せがしやすくなるでしょう。
社会保険料の計算には通勤手当が含まれる
交通費について通勤手当を支給する場合に迷いやすいのが社会保険料の算定です。多くの会社が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、社会保険料は従業員ごとの「標準報酬月額」に基づき、健康保険料は都道府県ごとに定められる保険料率で、さらに厚生年金保険料は全国一律の保険料率を掛けて計算されます。実際には都道府県ごとの保険料一覧表があるため、難しい計算は不要です。
迷いやすいのは、この「標準報酬月額」を算定する算定基礎届の手続きの際に非課税の通勤手当を含めるかどうかです。結論から言えば、これは含めます。ここで、例を挙げて考えていきましょう。
<例>
- 月給:25万円
- 住宅手当:1万5,000円
- 課税通勤手当:800円
- 非課税通勤手当:4,200円
これらを毎月支給する従業員の標準報酬月額は、27万円です。
非課税通勤手当はあくまで所得税が非課税というだけで、他の税や保険料が非課税となることはありません。また、毎月計算する雇用保険料の計算も、通勤手当を全額含めて計算します。上記の例で言えば、27万円にそれぞれの事業に応じた保険料率を掛けて計算する形です。
こんな場合どうする?
働き方改革の推進によって、フレックスタイム制や在宅ワークなどを導入する企業が増えてきました。それに伴い、通勤手当の支給についても新しい事例が発生しています。在宅ワーク時の通勤手当の取り扱いや、2023年3月にJR東日本で導入されたオフピーク定期券を活用する場合の2ケースについて取り上げ、詳しく見ていきましょう。
1.在宅ワークなのに従業員が定期券を購入してしまった場合
新型コロナウイルスの感染予防対策により、在宅ワーク(テレワーク)が急速に普及しました。それに伴って、通勤手当でこれまで定期代を支給していたものを、出社日数に応じて実費支給に切り替えたという企業もあるのではないのでしょうか。
事前に「在宅ワーク時は通勤手当を支給しない」と通知したにもかかわらず、従業員が通勤定期券を購入してしまった場合、社員に対して、メールや上司による周知などを確実に行っており、就業規則やテレワーク規定との不整合がなければ、従業員側に過失があったと考えられます。
本人と面談し、在宅ワーク時は通勤手当を支給せず、出社日数に応じて実費で精算する旨を説明すると良いでしょう。トラブルになりそうであれば、双方の管理職に同席してもらってください。
2.JR東日本で導入される「オフピーク定期券」を活用する場合
JR東日本が2023年3月に販売を開始した、オフピーク定期券を活用する場合についてです。
オフピーク定期券とは
オフピーク定期券とは、首都圏のJR東日本路線で、平日朝のピーク時間帯以外に利用できる定期券のことです。土日や休日は通常の定期券として利用できます。ピーク時間帯(90分)の設定は各駅によって異なります。利用に制約がある反面、通常の定期運賃より約15%値下げされます。
オフピーク定期券の注意事項
フレックスタイム制や始業時間が遅い企業などは、オフピーク定期券の活用によって通勤手当を抑えられる可能性があります。一方、ピーク時に出社した場合は別途実費精算が必要となり、従業員、経理担当者とも手間が増えることも考えられます。時間によって費用が変わるので、交通費精算がかえって手間かもしれません。通勤費の支給方法としてオフピーク定期券を適用するかどうかは、さまざまなケースを想定して判断すると良いでしょう。
正しいルートで申請されているかだけでなく、利用時間に応じて費用があっているかの確認も必要になるため、紙やエクセルなどで交通費精算を行っている場合は、経理側のチェックに通常より時間がかかってしまうかもしれません。
この課題に対して、交通費精算システムを導入すれば、複雑な交通費精算も効率化できると考えられます。例えば、ICカードの乗車履歴をカードリーダーで読み取って、正しい運賃で交通費精算ができたり、申請されたルートが適切なルートであるか「早」「安」などのアイコンで確認できたりと、チェックの手間を省くことができます。
通勤手当の不正受給には注意が必要
通勤手当を導入するにあたっては、不正受給に注意が必要です。通勤手当の不正受給が発生する具体例は、以下のとおりです。
- 引っ越したのに通勤ルートを変更せずに通勤手当を受け取り続けた
- 電車の通勤手当を受けているにもかかわらず、自転車通勤している
不正受給の内容が悪質な場合は、懲戒解雇や返金請求を検討するケースもあるでしょう。ただし、交通費の不正受給を要因とする懲戒解雇は不当であるとされ、従業員の復職を命じた判例も過去にはあります。
万が一不正受給が発生し、対応が難しいと感じたときは、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
まとめ
最後に、交通費に伴う通勤手当のチェックポイントについてまとめます。
- 通勤手当の支給額や算出方法について法律の規定はない
- 受け取った側の所得税が一定要件下で非課税となる
- 通勤手当のうち非課税になる金額には上限がある
- 交通機関を使う場合は基本的に全額非課税
- 車両など交通用具は距離に応じて非課税限度額が変わるが、2㎞未満は全額課税
- 非課税額の上限は15万円
- 所得税以外の扱いでは課税・非課税の区別が不要
また、交通費・経費精算システムの「楽楽精算」なら、交通費精算だけでなく経費精算業務全体の時間短縮・効率化できる機能が豊富です。定期区間控除のチェックや検算作業など、毎月の処理が大変と感じている方は、交通費精算システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。
まずはこちらから資料請求!
「楽楽精算」の詳しい機能や事例に関する資料をメールでお送りします!
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。