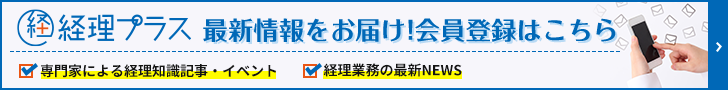子会社株式の減損処理の考え方・会計処理を解説!なぜ評価損が発生するか?

子会社の経営状況・財政状態が悪化し、親会社にとって子会社株式の実質価額が大幅に下落した場合は、子会社株式の減損処理が必要となります。そして、その評価差額は当期の損失として処理せねばなりません。今回は、子会社株式の減損処理や評価損の考え方について、分かりやすく解説します。
子会社株式の減損とは?
まず、「減損処理」とは何かについて説明しましょう。「減損」とは、「減損損失」のとこと。簡単に言うと「投資による失敗を、会計に反映させる」処理のことです。「子会社株式の減損」とは、子会社株式の金額を下げることで、「子会社の経営状況が悪いという事実を財務諸表で公表する」ことを指します。
その「取得原価または帳簿価格」と、「切り下げた額」の差額のことを、「評価損」と呼びます。
この「評価損」という概念は、他の有価証券取引ではあまり耳にしませんよね。通常、有価証券であれば、価格が下落しそうであれば、すぐに売却します。会社にとって、有価証券は配当や売却益を目的として保有しているからです。売買取引も多いため、時価も簡単に把握できます。
一方、子会社株式の保有目的は、「その会社を支配する」ため。ですので、あまり子会社株式の売買は行われません。取引自体が少ないので、時価の把握も難しくなります。子会社株式は取得時の原価で評価されますが、時価が著しく下落し、回復する見込みが無い場合は、評価を強制的に減損し、その差額を評価損として特別損失に計上しなくてはならないのです。
そのため、「子会社株式の減損処理」は、「強制評価減」とも言われます。
子会社株式の減損処理
では、具体的な処理の方法について解説します。
子会社株式の減損処理の対象となるのは、「取得時の原価と比較し、業績悪化等により、時価が著しく下落した有価証券」です。この「著しく下落した」というのは、時価が取得原価の50%以下まで下落したというのがおおむねの基準です。
時価の評価方法は、子会社の上場有無によって異なります。子会社が上場している場合は、常に客観的な時価が確認できますので、「取得原価」と「株式の時価」を比較し下落しているかどうかを判断します。上場していない場合は、「実質価額」を取得原価と比較します。実質価額とは、子会社の純資産金額や将来キャッシュフローなどを基にして算定されます。
比較の結果、時価が取得時より50%以上下落している場合は、減損処理を行います。その評価差額は、損益計算書(P/L)に評価損として特別損失を計上します。減損処理した後の時価は貸借対照表(B/S)に計上しましょう。
この際、頭に入れておきたい原則があります。それは、「一度減損した株式は、二度と取得原価には戻らない」というもの。これを「減損の戻し入れ禁止」と言います。
子会社株式の減損処理が不要な場合
取得時より50%以上時価が下落した場合は、強制的に減損処理が必要となりますが、例外もあります。それは、下落した時価の回復可能性がある場合です。
「回復可能性」は、事業計画等の十分な証拠によって裏付ける必要があります。さらに、この事業計画は実現可能で合理的なものでなければなりません。回復可能性の判定は、「おおむね5年以内に回復する」と見込まれる金額を上限として行われます。注意しておきたいのは、5年以内に「50%まで回復」ではなく、「取得原価まで回復」が求められているという点です。
また、回復可能性については、毎期ごとに見直しが行われます。5年以内であっても、業績が事業計画を下回ったり、予定通り回復していない場合は、減損処理をするかを検討するのです。
子会社の業績が悪化してしまった時の対応は、親会社にとっても経営上の重要な課題です。強制評価減をせざるを得ないのか、それとも回復可能性にかけ、事業計画実現に注力するのか。会計上においても多くの検討事項が発生します。イレギュラーな対応ではありますが、経理上の処理はシンプルなもの。いざというときに焦らず対応できるよう、基本的な考え方を頭に入れておきましょう。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。