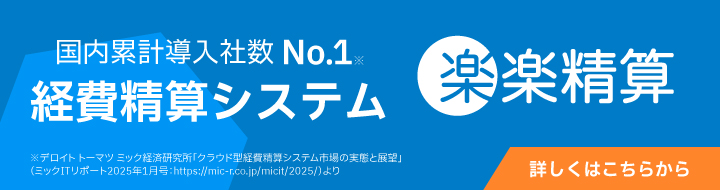法人税の計算はどう行う?算出する流れと計算式、納税の注意点

法人税は、法人が事業活動を通じて得た所得に対して課される国税のことを指し、代表的な法人の1つである会社は、法人税を納める義務を負っています。法人税を正確に計算するためには、法人税がどのように計算されるのかを知っておかなければなりません。この記事では、法人税の計算方法について簡単に知りたい方に向けて、法人税の概要と法人税の計算方法の流れについて解説していきます。
なお、法人税については以下の記事もご参照ください。
経理プラス: 法人税の計算方法とは?計算から申告までの流れを分かりやすく解説
法人税の基礎知識
法人税とは、法人がその事業活動から得た所得に対して課される国税のことです。この税金は、法人によって稼がれた利益に対する国の取り分を表し、法人の経済活動への貢献度に応じた税負担を求めるものです。
法人税とは?
法人税は、法人が一定の事業年度で得た所得にかかる税金です。法人税は、事業年度ごとに課税され、個人や個人事業主が支払う所得税に相当します。つまり、法人税は企業活動を通じて得られる収益から必要経費を差し引いた後との純利益に対して計算されます。
法人税の課税対象となる法人
法人税は、法人の事業活動から得られる所得に対して課される税金であり、その課税対象となる法人は特定の条件によって分類されます。具体的には、法人税は普通法人と協同組合等に課されることになります。これらの法人は、事業活動を通じて得た利益に対して税負担を負うことになります。
普通法人には、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、医療法人、相互会社、企業組合、監査法人、一般社団法人、一般財団法人(非営利型を除く)などが含まれます。これらの法人は、その事業活動によって得た所得に基づき法人税が課されます。たとえば、株式会社は利益を出すことが主な目的の1つであるため、得た利益に対して法人税を納める必要があります。
協同組合等には、農業協同組合、漁業協同組合、信用金庫、労働者協同組合などが含まれます。これらの組合は、組合員の利益を目的として運営されているが、その事業から得られる所得に対しても法人税が課されることになります。信用金庫は、地域住民の貯蓄や融資に関する業務を行うことで収益を上げ、その収益に基づき税金を納めます。
法人税の計算方法と手順
法人税の計算は、事業活動によって得た所得に対する税金を算出する過程です。この計算は法人の財務状況を正確に把握し、適正な税額を申告するために不可欠です。法人税計算の基礎から、具体的な手順までを理解することは、課税対象となるすべての法人にとって重要な責務といえるでしょう。
法人税が課される所得
法人税が課される所得は、「課税所得」と呼ばれます。この課税所得は、税法上の所得金額を意味し、具体的には「益金」から「損金」を差し引いた金額で算出されます。すなわち、課税所得の計算式は「課税所得(円)=益金(円)-損金(円)」で表されます。
益金とは、税法上認識される収益のことであり、事業活動によって得られる収入や、資産の売却益、受取配当金などがこれに含まれます。損金とは、事業活動に伴って発生した費用や、資産の評価損、損失など税法上認識される支出のことです。これら益金と損金の概念は、会計上の収益と費用とは異なり、税法に基づく特定の規則に従って定められています。
加算調整と減算調整
法人税の計算過程では、会計上の利益から税務上の課税所得を導出するために、「加算調整」と「減算調整」という2つのプロセスが必要になります。これらの調整は、会計上の利益と税務上の課税所得との間に生じる差異を修正することを目的としたものです。
加算調整は、税務上は収益(益金)に含まれるが会計上は収益に計上されない項目、または税務上は費用(損金)に含まれないが会計上は費用に計上される項目を課税所得に加える作業です。たとえば、無償で提供されたサービスから生じる利益や、税法により損金算入が認められない一定の交際費や寄附金の超過分がこれに該当します。
減算調整は、その逆で、税務上は益金に含まれないが会計上は収益に計上される項目や、税務上は損金に含まれるが会計上は費用に計上されない項目を課税所得から差し引く作業です。この例としては、受取配当金の一部や国からの補助金によって取得した固定資産の圧縮記帳額などが挙げられます。
これらの加算調整と減算調整を適切に行うことで、最終的な課税所得が算出され、その金額に対して法人税率が適用され、支払うべき法人税額が明確になります。
法人税の計算方法
法人税の計算は、企業がその事業年度において得た所得に対して行われる重要なプロセスです。この計算を通じて、企業が国に納めるべき税金の額が決定されます。法人税の計算方法は、一見シンプルに見えますが、適用される税率や控除項目の多様性により複雑な場合があります。具体的には、「課税所得」に「法人税率」を乗じて得た金額から「税額控除」を差し引くことで、納税額が算出されます。
法人税率と課税所得
法人税の基本計算式は以下の通りです。
ここで、課税所得とは、企業がその事業年度で得た益金から、法定された損金を差し引いた後の残額を指します。法人税率は、後で説明するように、会社の種類や規模によって異なり、一般的には資本金の額や事業年度の所得額に応じて設定されます。日本では、中小企業と大企業で税率が異なる場合があり、具体的な税率は税制改正により変更されることがあるので注意が必要です。
税額控除
税額控除は、納付する法人税額を直接減らすことができる重要な制度であり、二重課税の排除や特定の政策目的から設けられています。主な税額控除には以下のようなものがあります。
- 外国税額控除
国外で発生した所得に対して外国で支払った税金を、日本の法人税から控除することができる制度。これは国際的な二重課税を防ぐために設けられています。 - 所得税額控除
源泉徴収された所得税を法人税から控除できる制度。特に、配当収入に対する所得税がこれに該当します。 - 租税特別措置法による税額控除
経済活動の促進や雇用の創出など、特定の政策目的を達成するために設けられた控除。これには、試験研究費の特別控除や雇用促進措置などがあります。
税額控除の適用には、それぞれ特定の条件があり、適用可能な控除額には上限が設けられている場合が多いです。そのため、企業は適用可能な税額控除を正確に理解し、適切に計算に反映させる必要があります。
<法人税の税率>
| 区分 | 適用関係(開始事業年度) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平28.4.1以後 | 平30.4.1以後 | 平31.4.1以後 | 令4.4.1以後 | |||||
| 普通法人 | 資本金1億円以下の法人など(注1) | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| 適用除外事業者(注2) | 19%(注3) | 19%(注3) | ||||||
| 年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | ||||
| 上記以外の普通法人 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | ||||
| 協同組合等(注4) | 年800万円以下の部分 | 15% 【16%】 | 15% 【16%】 | 15% 【16%】 | 15% | |||
| 年800万円超の部分 | 19% 【20%】 | 19% 【20%】 | 19% 【20%】 | 19% | ||||
| 公益法人等 | 公益社団法人、公益財団法人または非営利型法人 | 収益事業から生じた所得 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| 年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | ||||
| 公益法人等とみなされているもの(注5) | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% | |||
| 年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | ||||
| 上記以外の公益法人等 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% | |||
| 年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | 19% | ||||
| 人格のない社団等 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% | |||
| 年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | ||||
| 特定の医療法人 (注6) | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% 【16%】 | 15% 【16%】 | 15% 【16%】 | 15% | ||
| 適用除外事業者(注2) | 19%(注7) 【20%(注7)】 | 19%(注7) | ||||||
| 年800万円超の部分 | 19% 【20%】 | 19% 【20%】 | 19% 【20%】 | 19% | ||||
※図に記載の注釈情報については、以下出典元の情報をご参照ください。
たとえば、普通法人に該当し、資本金の金額が1億円以下の法人であって、年間の課税所得が800万円未満であり、適用除外業者でない場合には、15%の法人税率が適用されます。
なお、表の中の【 】は、協同組合等または特定の医療法人が「連結親法人」であるケースの税率を示したものです。
法人税の計算後の注意点
最後に、法人税を計算した後に注意すべきポイントを解説していきます。
赤字の場合は法人税を納める必要はない
赤字決算の場合、課税所得がマイナスとなるため、法人税の納付義務は発生しません。これは、税務上の赤字、つまり益金よりも損金の方が多い状態を意味します。赤字の金額は、翌年以降に繰り越して、将来的に発生する黒字と相殺することが可能です。この繰越欠損金の制度により、最大で10年間、赤字を前年度から繰り越して利用することができます。
ただし、会計上の赤字であっても、税法上は一部の支出が損金に算入されないため、実際には黒字となる可能性があります。特に、交際費などは限度額を超える部分が損金算入できず、この部分が黒字に転じる要因となることがあります。したがって、交際費等の処理により税務上は黒字になり、結果として法人税の納付義務が発生する場合もあることを理解しておきましょう。
法人税の申告・納税は期限までに終わらせる
法人税の申告および納税の期限は、事業年度の終了日から2か月以内と定められています。この期限内にすべての手続きを完了させることが法的義務です。また、前年度の納税額が20万円を超える法人には、事業年度の途中である中間期に中間申告を行い、中間納税をする義務があります。この中間申告は、年度末の確定申告における納税額を調整する役割を果たします。
確定申告に誤りがあった場合や申告が遅れた場合には、延滞税が課される他、過少申告加算税や無申告加算税、重加算税などのペナルティが課される可能性があります。特に重加算税は、税務調査によって後から不正が発覚した場合に高い税率で加重されるものであり、企業の信用にも大きな損害を与えます。また、無申告加算税が課されないよう期限内に正確な申告と納税を行うことが重要です。
まとめ
法人税を正確に計算する上で大切なことは、法人税法上認められている益金と損金の種類を正しく理解することです。基本的に、益金から損金を差し引いて課税所得が計算されるため、益金・損金にミスがなければ正確に課税所得を計算することが可能です。この課税所得に対して、一定の法人税率を乗じた上で、税額控除を行うと、法人税の納税額を計算することができます。
法人税の計算についてのQ&A
法人税の計算は、企業の財務担当者にとって重要な業務の1つです。適正な計算と申告は法人の義務であり、間違いのないように計算することが求められます。ここでは、法人税計算に関する一般的な疑問にお答えします。
Q1. 法人税の計算の際、端数処理はどうすれば良い?
法人税の計算における端数処理には、具体的なルールが定められています。課税所得の計算においては、1,000円未満の端数を切り捨てることが基本とされています。つまり、課税所得を算出する際には、1,000円を単位として計算し、それ未満の金額は計算に含めません。
一方、法人税額の計算では、100円未満の端数を切り捨てます。この場合、計算された法人税額から100円未満の部分を除外し、その結果を納税額として申告します。このような端数の処理は、税務申告を行う上で非常に重要であり、正確な税額を計算するために遵守する必要があります。
Q2. 法人税の計算を間違った場合はどうなる?
法人税の計算を間違えて申告した場合、その訂正には更正の請求または修正申告という2つの手続きがあります。もし税額を多く申告してしまった場合は、更正の請求を行い、納付し過ぎた税金の返還を求めることができます。一方、税額を少なく申告してしまった場合は、修正申告を行い、不足分を追加で納税します。間違いを見つけた際は、速やかに適切な手続きを取ることが重要です。このプロセスを通じて、正しい税額の申告と納税が確保されます。
Q3. 法人税を節税する方法はある?
法人税の節税方法は多岐にわたり、自社の規模や事業内容に応じて最適な策を選択することが重要です。ここでは、特に効果的な節税テクニックの一部を簡単に解説します。
- 役員報酬を損金計上:適正な範囲内で役員報酬を設定し、これを損金として計上することで、法人税負担を軽減できます。ただし、役員個人の所得税増加には注意が必要です。
- 社宅を利用:経営者や従業員に対する社宅の提供は、支払家賃と受取家賃の差額を所得税が課税されない現物給与として損金に計上できるため、節税に寄与します。
- 旅費日当の支給:経営者の出張に際して旅費日当を支給し、これを経費として計上することが可能です。
- 赤字の繰り越し:発生した赤字を最大10年間繰り越し、将来の黒字期に相殺することで節税につながります。
これらのテクニックは、法律の定める範囲内で効果的に利用することで、法人税の負担を軽減することが可能です。節税策を検討する際には、専門家との相談を通じて、自社に適した方法を選択することが推奨されます。
Q4. 法人税の実効税率とは?
法人税の実効税率は、企業が実際に納める法人税額と課税所得との割合を示すもので、「法定実効税率」とも呼ばれます。これは、表面税率と実際の納税額の間の差を反映したものであり、法人事業税の損金算入などにより、表面税率よりも低くなることが一般的です。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。