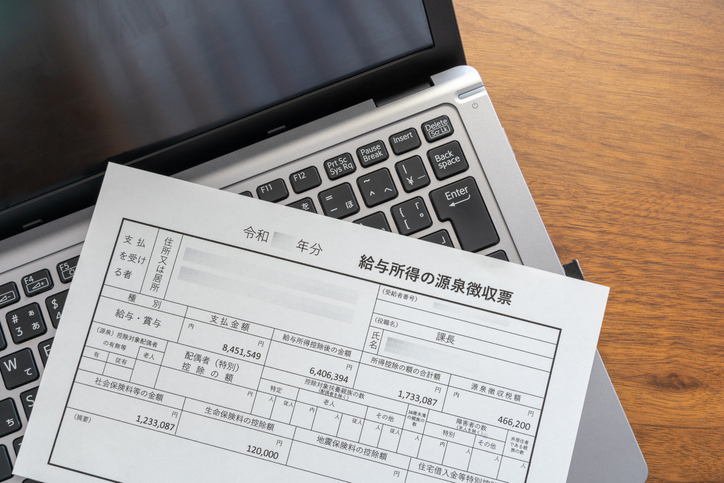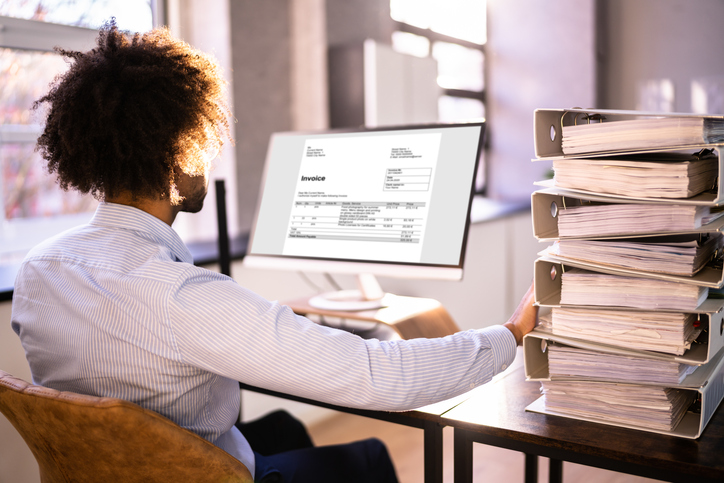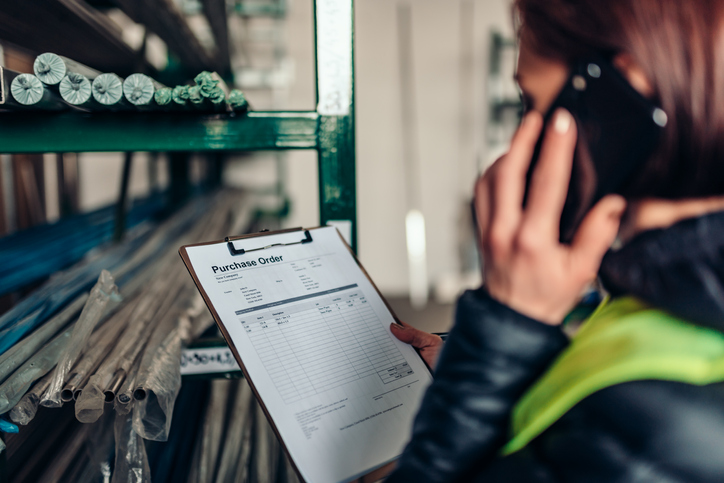注文請書とは?無料テンプレートや書き方、収入印紙が必要なケースを解説
この記事では、請書のテンプレートや書き方を詳しく解説します。また、注文請書を作成する際の注意点と、印紙の要否をケース別に紹介します。
請書は、契約トラブルから自社を守るために重要な書類の1つです。不備のない請書の書き方を知りたい、書類の書式を揃えるためにテンプレートを採用したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
注文請書の無料テンプレート
請書(注文請書)は、契約を結ぶ際に受注する側が作成する書類です。ビジネスにおいて頻繁に作成される書類の1つですが、注文請書を初めて作成する場合には、書き方が分からないと悩む方もいるでしょう。
ここでは、誰でも迷わずに注文請書を作成できるよう、Excel形式のテンプレートを用意しました。項目があらかじめ記載されているため、テンプレートに沿って必要事項を入力するだけで、注文請書を作成できます。
個人・法人どちらの方でも利用できるため、ぜひ活用してみてください。
注文請書とは?
注文請書とは、商品やサービスの申込を受けた際に承諾の意思を示す書類のことです。ここではまず、注文請書の必要性と、発注書や契約書との違いを見ていきましょう。
注文請書の必要性
注文請書とは、受注者が発行する契約関連の書類の1つです。法的に作成が義務付けられているわけではありませんが、注文内容や金額、納期などが明記されているため、万が一契約トラブルが発生した場合に、証拠として役立てられる可能性があります。
日本では、注文を受注した際に、発注者が発行する注文書のみをやり取りするケースも多くあります。しかし、契約に関するトラブルを回避するためには、注文請書も発行しておくと安心です。
発注書や契約書との違い
契約に関する書類には、注文請書のほかに発注書や契約書もあります。それぞれの違いを、以下で確認しましょう。
| 注文請書 | 注文書(発注書) | 契約書 | |
| 発行者 | 受注者 | 発注者 | 受注者と発注者 |
| 目的 | 注文の申込を承諾するため | 注文の申込のため | 取引条件に合意し契約をしたことを証明するため |
| 作成するタイミング | 注文書を受け取った後 | 注文をするとき | 契約時 |
| 法的効力 | 原則としてなし | 原則としてなし | あり |
契約をする中で、最初に発行されるのが注文書です。注文書を受け取った受注者は、注文請書を発注者に渡します。注文書と注文請書により、双方が合意したことが明らかになったら、契約書で契約を結びます。
注文書と注文請書には、原則として法的効力はありません。ただし、必要事項が記載された注文書と注文請書が揃った場合には、法的効力が認められるケースもあります。
経理プラス:発注書(注文書)の無料エクセルテンプレート|記載項目と注意点は?
注文請書の書き方
注文請書を作成するにあたっては、以下の必要事項を漏れなく記載することが大切です。それぞれを詳しく見ていきましょう。
- 発行日
- 発注者の名称
- 受注者の名称および住所
- 受注の条件
- 注文内容
発行日
注文請書には、発行日を記載しましょう。発行日には、書類の作成日を記載します。
発行日を記載する際のポイントは、注文書の日付と同日または、注文書の日付より後の日付とすることです。注文請書は、注文書の内容を承諾したことを示す書類です。発行日が注文書より前の日付になっていると、契約の流れに食い違いが発生し、書類の信頼性が下がってしまいます。
注文請書を作成する際はまず、契約の流れとして正しい日付であることを確認することが重要です。
発注者の名称
誰から注文を受けたかを明確にするため、注文請書には発注者の企業名や担当者名を記載します。契約に不整合が発生することを防ぐには、注文書に記載された発注者の名称と同じ名前を記載することが肝心です。
発注者の名称は、「(株)」などの省略文字を使用せず、正しく記載しましょう。誰が見ても発注者が明確に分かるよう、正式な名称を記載することがポイントです。
受注者の名称および住所
注文請書には発注者の名称と併せて、受注者側の会社名や住所、連絡先、部署を記載します。受注者についても、誰が見ても分かるように記載することで、責任の所在を明確にできます。
規模が大きな会社であれば、部署内の担当者名まで記載しておきましょう。これにより、取引先はもちろん、社内トラブルの防止にもつながります。
受注の条件
注文請書には、受注の条件についても詳しく記載する必要があります。具体的な項目は、以下のとおりです。
- 納期
- 納品方法
- 支払い方法
納期や納品方法に認識のずれがあると、「希望の場所に商品が届かない」「商品が間に合わず多額の損失が発生する」など、大きなトラブルが発生するおそれがあるため注意が必要です。
また、支払い方法の確認を怠ると、予定日に入金されず、資金繰りに影響が出る可能性もあります。
スムーズな取引を目指すのであれば、発注者と受注者で受注条件を十分に確認し、トラブルの発生を防ぐことが肝心です。
注文内容
注文請書には、以下の注文内容も記載しましょう。
- 納品する商品やサービスの内容および規格
- 数量
- 単価
- 税抜きの合計金額
- 税込みの合計金額
注文請書は、印紙の貼付が必要な場合があります。印紙代は、税抜き金額を基に計算しますが、税額がはっきりしないときには税込みの合計金額が適用されます。
正しい印紙代を計算するためには、税抜きと税込みの合計金額を求め、注文請書に両方の金額を記載しておくと良いでしょう。
注文請書に関する注意点
注文請書を作成する際には、以下の注意点を押さえる必要があります。
- 双方で内容を確認し署名と捺印をする
- 一定期間保管をする
- 収入印紙代をどちらが負担するか事前に決めておく
それぞれを詳しく解説します。
双方で内容を確認し署名と捺印をする
注意点の1つ目は、請書の内容を受注側と発注側の両方でチェックし、認識に相違がないことを確認したうえで、署名と捺印をすることです。法的義務はありませんが、双方が同意したことを明示するために、多くのケースで署名と捺印が行われます。
印鑑は、会社印や実印を使用しましょう。押す場所に規定はありませんが、社名や住所の右横に押印するのが一般的です。
一定期間保管をする
注文請書には、法律により一定期間の保管が義務付けられている点も、押さえておくべき注意点です。保管期間は以下のとおりです。
【注文請書の保管期間】
- 個人事業主:原則5年
- 法人:7年(※)
※欠損金の繰越控除を受ける場合は10年
取引が多い企業だと、保存する注文請書の量が膨大になります。保存状態によっては、書類が破損したり紛失したりする可能性もあるでしょう。
保管場所の確保や管理にかかる負担を削減したいのであれば、電子保存も選択肢です。電子保存をするには、法律の要件を守る必要があります。規定や要件を事前に十分確認し、不備のない保存を目指しましょう。
収入印紙代をどちらが負担するか事前に決めておく
収入印紙の貼付が必要な注文請書の場合、印紙代を受注者と発注者のどちらが負担するかを事前に決めておくことも、注意点です。
印紙代は、契約する金額によって決まります。契約額が大きい場合、数万円以上の印紙代が必要になるケースもあります。注文請書発行時にトラブルが発生しないよう、印紙代の負担について事前に取り決めておくと安心です。
注文請書に収入印紙は必要?ケース別に紹介
注文請書に収入印紙が必要かどうかは、契約金額や取引形態などによって異なります。
注文請書への収入印紙の貼付漏れが発生すると、過怠税を徴収されます。場合によっては、本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税を徴収されるかもしれません。
収入印紙の取り扱いを事前に十分に確認し、不備のない書類作成を目指しましょう。
収入印紙が必要なケース
収入印紙が必要なケースは、契約金額が1万円以上の場合です。税額は、契約金額によって次のように決まっています。
| 注文請書に記載された契約金額 | 印紙代 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 |
| 契約金額の記載がないもの | 200円 |
印紙税を納めるために重要なのは、注文請書に正しい契約金額を記載することです。貼付した収入印紙が、本来納めるべき税額よりも少ない場合、過怠税の対象になるケースもあります。
注文請書を作成する際には、税額の根拠が明確になるよう、単価・数量・小計・消費税・合計額などを明記しましょう。
収入印紙が不要なケース
契約金額や契約の内容、注文請書の形態などによっては、収入印紙が不要なケースもあります。不要な印紙代を納めることがないよう、しっかりと確認しましょう。
契約金額が1万円未満の場合
契約金額が1万円未満の場合は、印紙の貼付は不要です。ただし、金額が記載されていない場合は、「契約金額の定めのない請負契約書」とみなされ、200円の収入印紙が必要になることは覚えておきましょう。
なお、契約金額に消費税は含まれません。ただし、注文請書に税額が明記されていない場合は、すべてが契約金額とみなされ、印紙税が増える可能性がある点には注意が必要です。
売買契約の場合
売買契約に関する注文請書の場合も、印紙の貼付は不要です。
具体的には、カタログを通じてオフィス用品などを販売するケースが挙げられます。このような場合、注文を受けた商品名や数量を確認するために、注文請書を発行するケースも少なくありません。この取引は売買契約になるため、印紙は不要です。
印紙の要否について判断が難しいときは、税理士や所轄の税務署などに相談すると安心です。
電子取引の場合
電子取引で注文請書を交わしたときにも、印紙代は不要です。印紙の対象となるのは、紙の書類で注文請書を発行した場合のみです。
そのため、電子取引で請書を作成したときは、印紙を貼付する必要はなくなります。契約金額や契約件数によっては、印紙代が嵩むケースもあります。印紙代を抑えたいときは、電子取引を検討しましょう。
電子取引を導入するには、新たなシステムの導入や電子保管体制の整備、取引先との合意形成など、事前の準備が必要です。
契約書に収入印紙を貼付している場合
注文請書以外の契約書が存在し、契約書に収入印紙を貼付している場合も、注文請書への貼付は不要です。
なお、注文請書と契約書の両方に貼付すると、二重で税金を納めたことになります。多く納めすぎた印紙代は、過誤納金として還付を受けられます。
還付を希望する場合は、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入のうえ、納税地を管轄する税務署長宛に提出しましょう。
参考:国税庁 No.7102 請負に関する契約書
参考:国税庁 No.7130 誤って納付した印紙税の還付
まとめ
注文請書は、契約に関する書類の1つです。商品やサービスの注文を受けたときに、承諾したことを明示する目的で発行します。
注文請書の発行について、法的な義務はありません。しかし、契約時のトラブルを防止するには、必要事項を記載した注文請書を発行することが肝心です。
この記事では、誰でも無料で利用できるExcel形式のテンプレートを用意しています。業務負担を抑えてスムーズな請書の作成を希望している方は、ぜひご利用ください。