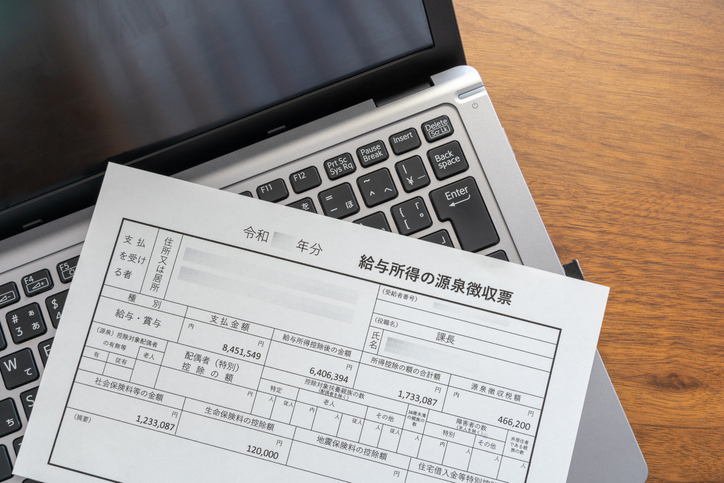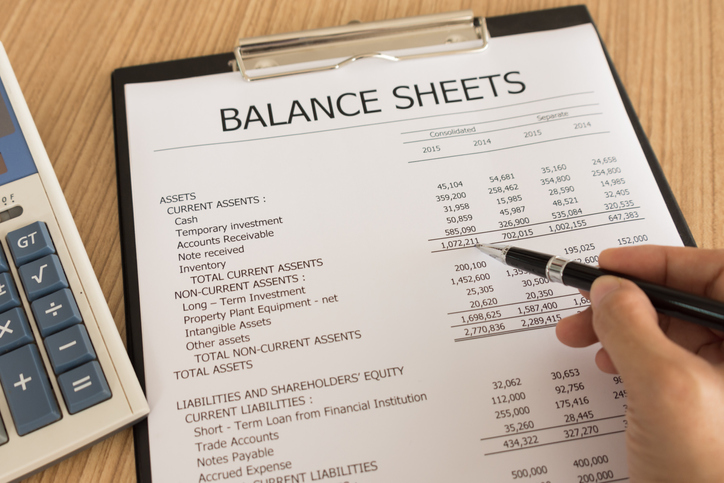管理会計とは?財務会計との違いや導入のポイントを分かりやすく解説

管理会計とは、社内で経営判断の材料にするために行う会計処理です。経営の意思決定などを目的に、予実管理や経営分析などの業務を行います。社外向けに決算報告書を作成する財務会計とは異なり、実施は義務付けられていません。
本記事では、管理会計と財務会計の違いや導入のメリット、デメリットなどを紹介します。
管理会計とは?
管理会計とは、社内向けに活用することを目的とした企業会計のことです。
ここでは、管理会計の目的や財務会計との違いを解説します。
管理会計の目的
管理会計は、経営者が自社の経営状況を把握して経営の意思決定に役立てるとともに、業績や課題などを確認して改善策を立てることを目的に行います。
適切な経営の意思決定には、自社が現在どのような状況かをタイムリーに確認できなければなりません。適切な判断をするためには客観的なデータが必要であり、管理会計では経営判断に必要な自社のデータをリアルタイムで可視化することが求められます。
管理会計はあくまで社内で活用することを目的としており、財務会計のように法律で作成が義務付けられているわけではありません。しかし、管理会計の実施により経営状況を把握・管理でき、収益性や生産性、成長性などを判断できるというメリットがあります。そのため、経営を正しい方向に導くために、多くの企業で導入されています。
財務会計との違い
管理会計が「社内向けの会計」であるのに対し、財務会計は「社外向けの会計」です。
両者は目的や対象が異なり、作成する資料や手法、実施する時期も違います。具体的な違いは、次のとおりです。
| 管理会計 | 財務会計 | |
| 対象 | 内部向け(経営者や管理責任者など) | 外部向け(投資家・債権者・税務署などの利害関係者など) |
| 目的 | 経営の意思決定など、自社の経営に活用 | 経営状況・財務状況の開示 |
| 手法 | 決まりなし | ・法律や会計基準に沿って実施 ・財務諸表を作成 |
| 導入 | 任意 | 義務 |
| 期間 | ・決まりなし ・年ごと・月ごと・週ごとなど自由 ・リアルタイム性を重視 | ・会計年度内に実施 ・1年・半年・四半期など |
財務会計は、債権者や投資家といった利害関係者に向けて、企業の財務状況や経営状況を報告するために行います。会社法をはじめとする法令の規定に基づき、決算報告書の作成が必要です。
決算報告書とは、企業が所有する資産や負債など、財産状況をまとめた書類です。貸借対照表や損益計算書、キャッシュ・フロー計算書といった書類が含まれており、財務諸表とも呼ばれています。
管理会計の業務
管理会計には、次の4つの業務があります。
- 予実管理
- 経営分析
- 原価管理
- 資金繰り管理
それぞれ、詳しく解説します。
予実管理
予実管理とは、利益目標の達成に向けて期初に予算計画を策定し、実績を把握して分析することです。一定期間ごとに予算と実績を比較することで、売上の達成状況が分かります。
予算計画と実績がかけ離れている場合は原因を究明し、改善策を検討します。想定のコスト以上に経費を使っていることが分かれば、それ以降の経費を抑えるなどの対応が可能です。
予実管理の目的は、目標に向かって進むプロセスをリアルタイムで可視化し、実績を目標に近づけていくことです。そのため、予実管理ではまず予算目標を立てることから始めます。
目標は、高すぎず、かつ低すぎないことが大切です。企業が成長できる目標にするためには、努力すれば達成できる程度に実現可能な予算目標を立てましょう。
目標が明確になれば、目標を達成するために人材・物資・資金などの資源がどの程度必要になるかを把握できます。
経営分析
経営分析とは、会社の経営状態を把握し、経営戦略に役立てるために行われる分析です。財務諸表をもとに、収益性や生産性、安全性、成長性など、さまざまな角度から分析を行います。
ただし、すべての指標を分析に使うのは時間がかかり、担当者の負担も大きくなるでしょう。また、情報が多すぎると結論を出しにくくなるため、自社の課題や目標に合わせた指標に絞って分析することが大切です。
経営状態を把握するためには、内部の状況だけでなく、競合他社との比較や社会の変化などの外部要素も含めた分析が必要です。
経営分析により、自社の強みや弱みを把握できます。強み・弱みを知ることで市場における自社の位置を的確に判断でき、企業の成長に向けた戦略の策定ができるでしょう。
原価管理
原価管理は、製品製造やプロジェクトごとにかかるコストを管理する方法です。目標となる標準値の原価を設定し、実際にかかった原価との差を把握して、適正な原価を検討します。
たとえば、実際にかかった原価が目標よりも高い場合、どの費用に問題があるのかを特定し、原価設定を見直します。
原価管理を行うことで無駄なコストを把握しやすくなり、無駄を省いて原価を抑え、利益を増やすことが可能です。
また、原価管理では損益分岐点も把握できます。損益分岐点とは、売上と費用がまったく同じ金額で利益がゼロになる売上のことです。損益分岐点を把握できれば原価に対してどれくらい利益が出るのか分かり、経営における意思決定の判断材料になります。
原価管理は特定の製品やプロジェクトにかかるコストを管理するもので、経営全体を管理する予実管理とは異なります。予実管理を構成する要素のひとつといえるでしょう。
資金繰り管理
資金繰り管理とは、資金の入出金の流れを管理して不足が出ないように管理することです。資金の動きは常に変動するため、日々管理することで、資金不足のリスクを事前に把握できます。
資金繰り管理では、特に売掛金などすぐに現金化できない債権の管理が重要です。資産の多くが債権である場合、債権回収のタイミングによっては、手元の資金が不足する可能性があります。
債務の支払いが滞るリスクがあるため、債権が現金化されるタイミングと債務の支払い時期を正確に把握しなければなりません。
管理会計を導入するメリット
管理会計を導入することで、経営状況の可視化など、さまざまなメリットがあります。
ここでは、管理会計を導入するメリットを解説します。
経営状況を見える化できる
管理会計により、経営状況をリアルタイムで見える化できる点がメリットです。
財務会計の場合、決算報告書の作成を目的に行うため、四半期や年度末など決まった時期に行います。そのため、現状の経営状態を明確に把握できない点がデメリットです。
一方、管理会計は月単位や週単位、部署別・事業別など、社内のルールで実施できるため、目標達成の進捗状況など、現状の数字をタイムリーに確認できます。迅速な経営判断と意思決定ができ、問題が起きたときも早めに経営改善の戦略を立てやすいでしょう。
部門(セグメント)単位で評価できる
事業規模が大きくなると、分析の対象となる数値の種類が増えていきます。分析の難易度も高くなるため、財務状況を部門(セグメント)別に把握し、評価する必要があります。
部門ごとに経理状況を把握する管理会計を行えば、財務諸表では見えてこない、部門別の利益状況、成績を把握できるでしょう。その結果、現場ごとに課題や改善点が分かり、適切かつ具体的な目標を立てられるようになります。
コスト管理・コスト削減につながる
管理会計で部門(セグメント)ごとに評価することで、予算設定や予算の達成状況、コストを把握しやすくなります。無駄なコストが明確になり、削減に向けた取り組みがしやすくなるでしょう。
部門ごとの経営状況・財務状況を可視化すれば、従業員に予算やコストを共有できます。各自が無駄をなくすにはどうすればいいかを考え、自主的に業務改善を行う意識を醸成できるでしょう。
また、方針転換などにより現場の業務が変更される場合にも、その目的について従業員に理解してもらいやすくなります。
管理会計のデメリット
管理会計の導入にはメリットばかりではなく、デメリットや課題もあります。具体的には、担当者の業務負担が増えること、分析には専門知識が必要になることがあげられます。
管理会計のデメリットについて、詳しくみていきましょう。
業務負担が大きくなる
管理会計の導入により、社員の業務が増えるというデメリットがあります。管理会計を行う場合、財務会計で扱う情報だけでは十分でなく、さらに詳しい情報の収集と分析が必要です。経理担当だけでなく営業の協力が必要になることもあり、負担が増える範囲は広くなるでしょう。
また、管理会計をExcelで行う場合、データを手入力することから、入力ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
従業員の負担や人為的ミスを減らし、効率的な管理会計を行うためには、会計システムの導入も必要になるでしょう。そのためのコストが増えることもデメリットとなります。
専門知識が必要
管理会計の導入では、ただ業務量が増えるだけでなく、分析のスキルや専門知識も必要になります。現在の経理担当者では対応が難しい場合、研修を行うか、スキルを持つ人材の新たな採用が必要になるでしょう。
管理会計は経営の意思決定に直接関わるもので、スキル不足のままで精度の低い分析を行ってしまうと、間違った経営判断を招くことにもなりかねません。
データの入力ミスや、自社の経営分析に合わない分析手法を採用している場合も、経営を混乱させるリスクがあります。正しく管理会計を行うためには、正確な数値の提示を行うための対策が必要です。
管理会計を導入する際のポイント
管理会計を導入する際は、次のポイントを押さえましょう。
- 事前準備を行う
- 専門家の力を借りる
- システムを活用する
それぞれ、詳しく解説します。
事前準備を行う
管理会計の実施にあたり、定期的な情報収集や資料作成、分析が必要になり、経理担当者をはじめとする社員の負担が増えます。スムーズな運用をするためには、導入に際して事前準備が必要です。
まず、管理会計をなぜ導入するのか目的を明確にして、全社員に管理会計の目的について説明を行いましょう。
また、管理会計の業務は専門知識を要する業務のほか、必要なデータの抽出や計算などの定型業務も多いため、これらの業務は誰でも作業できるよう、マニュアルやチェックリストを用意しておくとよいでしょう。
専門家の力を借りる
管理会計には専門知識が不可欠であり、社内で対応が難しい場合は公認会計士や税理士といった専門家に依頼するのもよいでしょう。
税理士は税務の専門家であり、税務申告の代理や税務書類の作成、 税務相談に対応します。一方、公認会計士は監査を独占業務とし、企業が作成した決算書が適切に作成されているかをチェックします。
どちらの専門家も会計のプロであり、データをもとに管理会計の分析を依頼できるでしょう。ただし、依頼先を決める際は、正確な経営判断をするため、「管理会計の業務に豊富な実績がある」「自社の業界に精通している」といった視点での見極めが必要です。
システムを活用する
管理会計の導入により、新たな業務をが増えるため、もしまだ会計システムを活用していない場合は、システムを導入することがおすすめです。
一般的な会計システムは財務会計での使用を前提としているものが多いため、管理会計に特化したシステムを選ぶか、予実管理や原価管理、部門別の損益管理など管理会計向けの機能が搭載されているシステムを選びましょう。
管理会計に特化したシステムであれば、資料作成や分析など管理会計の業務をより効率化できます。
規模の小さい会社であれば、Excelでも管理会計は可能です。Excelは自由度が高いため、熟練した社員であれば自社に合わせたフォーマットを作成し、運用できるでしょう。
ただし、Excelは自由度が高いだけに属人化しやすく、異動や退職の際に引き継ぎが難しくなるというデメリットがあります。また、部署や自社製品・サービス、プロジェクトが増えるに従い管理が必要なExcelのシートの数が増え、管理が難しくなるでしょう。
システムを導入すればこのような不都合を回避し、入力や集計、分析にかける時間を短縮して業務の負担を軽減できます。
管理会計システムの選び方
管理会計システムにはさまざまなタイプがあるため、自社に合うものを選ぶことが大切です。
ここでは、管理会計システムの選び方を紹介します。
導入目的に合うシステムか
管理会計システムを選ぶ際は、まず導入目的を明確にしましょう。その目的に合わせ、必要な機能が搭載されているかを確認してください。
管理会計システムには、主に次のような機能が搭載されています。
- 帳票作成・管理
- 予実管理
- 会計情報の分析
- レポート
帳票作成・管理の機能では、経営関係の書類の作成と管理を行います。予実管理は、企業の予算・実績の管理を行う機能です。会計情報の分析の機能では、部門ごとのデータを分析・シミュレーションできます。さらに、分析したデータについてレポートを作成する機能もあります。
また、システムには経営管理に幅広く使えるタイプや予実管理に特化しているタイプ、財務会計システムに管理会計の機能が搭載されているタイプなどさまざまなタイプがあるため、企業規模や管理したい内容に合わせて選びましょう。
なお、システムごとに対応している帳票の種類は異なります。汎用的に対応するものもあれば、あらかじめ出力できる帳票が決められているものもあり、さまざまです。
そのため、自社の業務で作成する帳票や分析の範囲に対応できるかも必ずチェックしてください。
自社の運用に適切なタイプか
管理会計システムの利用形態も確認しましょう。システムには、パッケージ型、オンプレミス型、クラウド型の3種類があり、それぞれ以下のような特徴があります。
パッケージ型
パッケージ型は、ソフトウェアを購入して自社のパソコンやサーバーにインストールして利用します。オフラインで操作できることがメリットです。
既存システムと連携し、自社に特化したシステムも構築できます。ただし、バージョンアップや法改正への対応は自社で行わなければなりません。
オンプレミス型
オンプレミス型は、自社に設置したサーバーにシステムを構築する形態です。サービスを提供する事業者のシステムを利用するか、自社で独自にシステムを開発します。
ニーズに応じてカスタマイズしやすく、セキュリティを強化できる点がメリットです。
ただし、導入から運用まで自社で対応するため、業務の負担は増えるでしょう。パッケージ型と同じく、バージョンアップや法改正への対応も必要です。
クラウド型
クラウド型は、インターネット経由で事業者が提供するサービスです。インターネット環境があれば、デバイスや場所を選ばず操作できます。法律改正時には自動でシステムがアップデートされるのが特徴です。
また、オンライン上にサーバーがあるため、システム構築などの手間や初期費用を抑えられます。
利用形態のそれぞれにメリット・デメリットがありますが、できるだけ社内の負担を抑え、業務効率化を図りたい場合はクラウド型の管理会計システムが適しています。
また、頻繁に変わる法制度改正への対応や、最新技術へのアップデートなどを考えれば、クラウド型のメリットは大きいといえるでしょう。
既存システムに連携できるか
すでに導入しているシステムがある場合には、連携できるかどうかの確認も必要です。既存システムと連携ができれば、管理会計システムでのデータ収集や分析をより効率化できます。
異なるシステムからのデータを統合することで、データの一元管理ができ、アクセスも容易になります。システム間でのデータ転送を自動化できれば手入力によるミスを削減し、業務効率も高まるでしょう。各システムのデータを活用することで、より詳細な分析ができるのもメリットです。
システム間で即時にデータ共有できれば、リアルタイムに情報を共有でき、より迅速な意思決定が可能になるでしょう。
主な連携方法としては、API連携やCSV連携が挙げられます。API連携はシステム同士が直接データをやり取りする方法で、リアルタイムに同期できます。CSV連携は、データをCSV形式でエクスポート・インポートする方法です。連携方法についても確認し、自社に合う方法を選びましょう。
まとめ
管理会計は財務会計と異なり、実施は義務ではありませんが、迅速な経営判断を行うため、導入する企業は少なくありません。管理会計の導入により経営状況をリアルタイムで可視化でき、財務状況を部門(セグメント)ごとに把握できる点がメリットです。
管理会計の導入によって社員の負担が増えますが、システムを導入することで効率的な運用ができます。システムにはさまざまな種類があるため、目的を明確にして、自社に合うものを選びましょう。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。