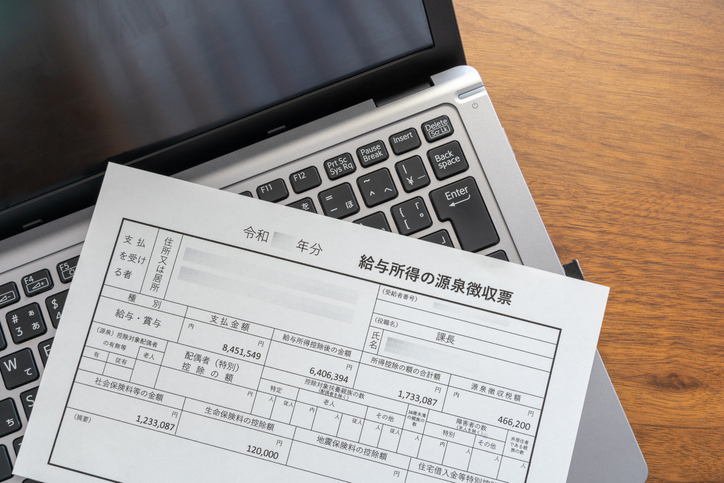預り証の無料テンプレートを紹介!書き方や注意点も解説
預り証は、金銭や物を預かったときに預かった側が発行する書類です。この記事では、預り証の無料テンプレートや書き方を解説します。また、作成の際の注意点や印紙の取扱いも解説します。テンプレートの活用により作業負担を軽減し、不備のない書類作成を目指す方はぜひ参考にしてください。
預り証(金銭のみ対応タイプ)の無料テンプレート
預り証のテンプレートです。金銭のみ対応のタイプです。Excelで作成してあります。預り証の見本、テンプレート、サンプルとしてご利用ください。
その他のテンプレート
預り証を発行するタイミングとしては、金銭だけでなく物や資産を預かるケースもあります。
ここでは、「金銭、物品両用対応タイプ」のExcel形式のテンプレートを紹介します。誰でも無料で利用できるため、ぜひ活用してください。
預り証の基本事項
預り証とは、他社の物やお金を一時的に預かって保管する際に、預かった側が発行する書類のことです。
物やお金といった資産を預ける取引では、何らかのトラブルが発生するケースも少なくありません。預り証を発行することで、取引の透明性と信頼性の確保や、トラブル発生時の早期解決が期待できます。
ここでは、預り証の基本事項として、領収書との違いや預り証の種類を見ていきましょう。
預り証と領収書の違い
領収書も物やお金の受け渡し時に使用する書類の1つです。領収書は、商品やサービスの代金授受を証明する目的で作成されます。
預り証と領収書の主な違いは、以下のとおりです。
| 預り証 | 領収書 | |
| 目的 | 物やお金などを預かったことを証明する | 代金の授受が行われたことを証明する |
| 発行するタイミング | 物やお金などを預かったとき | 商品やサービスに対する支払いが行われたとき |
| 所有権の移転 | なし | あり |
| 返却の必要性 | 原則としてあり | なし |
預り証と領収書は使用目的が異なりますが、実際には預り証を領収書の代替としているケースも見られます。
物やお金の授受に関するトラブルを防ぐには、それぞれの違いを押さえ、使い分けることが肝心です。
預り証の種類
預り証は、預かる目的によって以下の4つの種類にわけられます。
- 代金支払い目的のもの
- 担保目的のもの
- 預託目的のもの
- 運搬・保管目的のもの
それぞれの特徴を確認し、目的に合った適切な使いわけを行いましょう。
代金支払い目的のもの
代金支払い目的の預り証は、売上金の一部を手付金や内金として支払ったときに発行します。一般的に預り証というときには、この代金支払い目的のものを指します。
代金の一部が支払われてはいるものの、預り証のため所有権は移転しません。内金の支払いから契約締結までの間に、何らかの理由で解約された場合は、預り証との交換により手付金が返金されます。
担保目的のもの
担保目的の預り証は、担保として物やお金を預ける際に使用される書類です。具体的には、質屋に物を預けお金を借りた場合や、賃貸借契約の締結にあたり敷金を支払った際などに発行されます。
預かった物やお金は、契約終了時に預り証との交換により返却されます。ただし、賃貸契約における敷金の一部は、契約終了時の必要経費として使用されるケースがあることは覚えておきましょう。かかった費用によっては、返金される金額が少額または、ほとんどない可能性もあります。
預託目的のもの
預託目的の預り証は、運用や積立を目的としてお金や債券を預けたときに、金融機関から発行される書類です。具体的には、預金の預け入れや積立、投資信託を預託した場合が挙げられます。
なお、預金の預け入れは頻度が高いため、預り証を都度発行していると業務負担が大きくなります。そのため、預金の預け入れでは預り証の発行は省略されることがほとんどですが、通帳で出入金の記録が確認できるため、取引内容に関してトラブルが発生する可能性は低いでしょう。
運搬・保管目的のもの
運搬・保管目的の預り証は、運搬や保管を目的として物やお金を預けたときに発行する書類です。
利用される具体的なケースとしては、配達のために宅配業者に荷物を預ける場合や、貸倉庫を借りて荷物を保管する場合などがあります。倉庫に預けた荷物を出したいときには、預り証の提示によりスムーズな手続きが可能になるでしょう。
なお、運搬・保管目的で預り証を発行する場合、運賃や保管料の代金の領収書と兼ねた書類が作成されるケースも少なくありません。特に、宅配業者に荷物を預けた際には、ほとんどの場合で領収書の役割を併せ持った預り証が発行されることは覚えておきましょう。
預り証の書き方
預り証の書き方に、法的な決まりはありません。しかし、日付や預かった物の内容など、記載すべき項目がいくつかあります。主に以下の項目を記載することが一般的です。
- 預けた側の名前
- 預かった金額
- 但し書き
- 預かった日付
- 預かる側の名前および住所
ここでは、現金預り証のテンプレートを参考に、書き方を見ていきましょう。

預り証にはまず、預けた側の名前を記載します。預ける方が個人の場合は、個人名を記載します。法人や組織、団体等の物やお金を預かる場合は、会社名や団体名を記載しましょう。書類の効力を高めるために、名前に加えて住所の記載や捺印を行うこともあります。
次に、預かった金額を記載します。お金ではなく物を預かったときには、物の名前や数量を書いてください。併せて、取引内容の詳細を但し書きに記載しましょう。
最後に、預かった日付と預かる側の名前および住所を記入します。場合によっては、預かった側の捺印もします。預かった物の返却が決まっている場合は、返却条件も記載することがポイントです。
預り証に関する注意点
ここからは、預り証に関する以下の注意点を解説します。
- 署名と捺印を行う
- 紛失時には 紛失証明書を作成する
- 預り証を回収したら保存する
- 決算時には売上計上のタイミングに気を付ける
それぞれを十分に確認し、トラブルのない預り証の作成・運用を目指しましょう。
署名と捺印を行う
預り証の作成には、細かな規定はありません。そのため、単に預かった記録を残すだけであれば、預けた方と預かった方の名前を記載するだけで足ります。
しかし、預り証を法的な効力のある書類にするには、双方の署名と捺印が必要です。特に預かる商品が高価な場合は、万が一トラブルが発生したときの証拠として、署名と捺印がある預り証を作成しましょう。
また、さらに効力が高い預り証を目指すのであれば、預けた側に実印で捺印をしてもらい、さらに印鑑証明書を提出してもらうと安心です。
紛失時には紛失証明書を作成する
万が一預り証を紛失しても、大きな問題になることはほとんどありません。なぜなら、契約書など他の書類で双方の合意を確認できるケースが多いからです。
また、預り証はコピーを作成し、双方で保管しているケースも多くあります。そのため、どちらか1通を紛失しても、もう1通で確認ができると考えられます。
ただし、預り証の紛失が発生したときには、二重請求に注意が必要です。二重請求を防ぐには、預かった側は預けた側に紛失証明書の作成を依頼し、双方で保管しましょう。
預り証を回収したら保存する
預り証は、税法の規定により7年間の保存が義務付けられています。預かった物やお金を返却し預り証を回収したら、紛失しないように保管しましょう。
預り証の回収方法は、預り証の種類によって異なります。担保目的や預託目的、運搬・保管目的の場合は、物やお金を返却する際に預り証を回収しましょう。代金支払い目的の預り証は、代金残額の決済と商品の引き渡しを行う際に、領収書と交換してください。
預り証を多数発行する会社の場合、保管場所の確保や書類の管理を負担に感じることもあるでしょう。預り証は、電子データでの保存も可能です。電子データで保存すれば、管理業務にかかる負担を軽減できます。
ただし、電子データは、「電子帳簿保存法」で定められた規定に則り保存しなければなりません。また、保存するためのシステムを新たに導入する必要もあるでしょう。システムの利用手順を社員に周知するなど、体制を整えるにはある程度の時間もかかります。
電子データでの保存を希望する場合は、計画的に準備を進めることが大切です。
決算時には売上計上のタイミングに気を付ける
預り証を売上代金の一部として発行している場合には、決算時の取扱いに注意が必要です。売上計上のタイミングは、預り証を発行した日付ではありません。
物品の売買で預り証を発行したときには、物品の引き渡し後に売上が確定します。一方、サービスの提供で預り証を発行した際には、役務提供を終えたサービス部分のみの売上を計上する点に注意が必要です。
計上するべき売上が計上されていなかった場合、税務署から指摘を受けたり追徴課税を受けたりする可能性があります。トラブルのない税務申告を行うためには、決算における預り証の取扱いに十分注意しましょう。
預り証における印紙代の取扱い
預り証を発行する際には、印紙代が必要な場合と不要な場合があります。
不要な印紙を貼付した場合は、納税地の所轄税務署で手続きをすれば、過誤納金として還付可能です。一方で、必要な印紙を貼付しない場合には過怠税を課せられる可能性があります。
印紙代が必要なケースと不要なケースを理解し、不備のない書類作成を目指しましょう。
物品の預り証では印紙代は不要
印紙代が不要なケースは、以下の3つです。
- 物品の預り証
- 額面が5万円未満の売上代金の預り証
- 額面が5万円未満の売上代金以外の預り証
物品の預り証の場合は、印紙代は不要です。また、売上代金または売上代金以外の預り証のうち、5万円未満の場合も印紙代は課せられません。
額面が5万円以上の現金や有価証券の預り証は印紙代が必要
額面が5万円以上の現金や有価証券を対象とする預り証には、印紙代が必要です。印紙代は、売上代金の預り証と、売上代金以外の預り証で異なります。
それぞれの印紙代は以下のとおりです。
| 預り証の記載金額 | 売上代金の預り証 | 売上代金以外の預り証 |
| 5万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 | |
| 200万円超300万円以下 | 600円 | |
| 300万円超500万円以下 | 1,000円 | |
| 500万円超1,000万円以下 | 2,000円 | |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 4,000円 | |
| 2,000万円超3,000万円以下 | 6,000円 | |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 1万円 | |
| 5,000万円超1億円以下 | 2万円 | |
| 1億円超2億円以下 | 4万円 | |
| 2億円超3億円以下 | 6万円 | |
| 3億円超5億円以下 | 10万円 | |
| 5億円超10億円以下 | 15万円 | |
| 10億円超 | 20万円 |
なお、預り証に受取金額の記載のないものは200円の印紙代が必要です。
参考:国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
参考:国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
参考:国税庁 No.7130 誤って納付した印紙税の還付
まとめ
預り証とは、物やお金を預かった際に、預かった側が預けた側に発行する書類です。発行は法律で義務付けられてはいませんが、預り証を作成することで、取引の透明性と信頼性の確保が期待できます。
預り証には、預かった側と預けた側の名前や住所を記載します。そのほか、預かった金額や但し書き、日付などの記載も必要です。
預り証を初めて作成する方や、作成数が多く業務負担が大きい方は、テンプレートの活用がおすすめです。この記事では、誰でも無料で利用できるExcel形式のテンプレートを紹介しているので、ぜひご利用ください。